本記事の内容
本記事は、位数が12の群の分類について、その一部を解説する記事です。
本記事を読むに当たり商群、二面体群、生成された部分群、シローの定理について知っている必要があるため、以下の記事も合わせて御覧ください。
↓商群の記事
↓二面体群の記事
↓生成された部分群の記事
↓シローの定理の記事
数回に渡ってやること
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その32から数回に渡って何を解説するか、というと、結論としては次の定理の証明です。
定理0.
\(G\)が群で、\(\left|G\right|=12\)であれば、\(G\)は次の1.から5.のどれかと同型である。また、1.から5.の中で自分以外と同型になるものは存在しない。- \(\mathbb{Z}/{3\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{4\mathbb{Z}}\left(\cong \mathbb{Z}/{12\mathbb{Z}} \right)\)
- \(\mathbb{Z}/{3\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}\)
- 交代群\(A_4\)
- 二面体群\(D_6\)
- \(\left\langle x,y\middle|x^4=y^3=1,\ xy=y^2x\right\rangle\)
「なぜ12なの?」と思うかも知れませんが、12という数を選んだのは、位数が小さい群の中では位数12の群が一番興味深いと言われているからです。
また、分類の過程で群論に関して今までに学んだことのほとんどを使うことになるからです。
要するに、位数12の群は群論の基礎知識をフル稼働させるため、群論の全体像をつかみやすくするだけでなく「群のイロハが詰まっている」という理想的な状況なのです。
定理0.の証明の流れ
割とシンプルです。
- ① 出現する全ての群が同型でないことの証明(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その33で証明済み)
- ② \(G\)が位数12の群なら、1.から5.のうちのどれかと同型になることの証明
- 1.と同型になる場合→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その33で証明済み
- 2.と同型になる場合→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その33で証明済み
- 3.と同型になる場合→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その33で証明済み
- 4.と同型になる場合→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その35を御覧ください。
- 5.と同型になる場合→今回
今回は、②の5.を証明します。
※注意※ (証明に入る前に)
先程、「位数12の群は群論の基礎知識をフル稼働させる」と述べました。
しかし、出現するものを具体的に列挙して復習すると寧ろくどく、証明の全体像が見えにくく成ってしまうと思うので、都度都度参考リンクを貼ることにします。
前回までの証明
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その32では出現する全ての群が同型でないことを証明し、
としたとき、\(H\cong \mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}\times \mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}\)であることと、\(H\)が正規部分群であることを証明しました。
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その32での考察から、\(H\)と\(K\)のうちどちらかは正規部分群なので、\(HK\subset G\)は部分群です。
\(H,K\subset HK\)なので\(\left|HK\right|\)は\(3\)と\(4\)で割り切れます。
\(\left|HK\right|\leq12\)なので、\(\left|HK\right|=12\)です。
故に、\(HK=G\)となるのでした。
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その33では、それを踏まえて
- 場合1:\(H\)と\(K\)の双方が正規部分群のとき
- 場合2:\(H\)のみが正規部分群のとき
について考察し、それぞれ
- 場合1:1.と2.のいずれかに同型
- 場合2:交代群\(A_4\)に同型
であることを示しました。
前回(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その34)では、場合3.(\(K\)のみが正規部分群のとき)を更に
- (a) \(H\cong\mathbb{Z}/{4\mathbb{Z}}\)
- (b) \(H\cong\mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}\)
で場合分けし、(a)のときに
$$
\left\langle x,y\middle|x^4=y^3=1,\ xy=y^2x\right\rangle\cong G
$$
であることを示しました。
今回は、(b)の場合について考察します。
いざ、証明(Part.4)
$$
H\cong\mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}
$$
のときを考えます。
本題に入る前に、少々復習
\(K_1,\dots,K_4\)を\(K\)の共役とします。
\(G\)は共益により集合\(\left\{K_1,K_2,K_3,K_4\right\}\)に作用します。
ここで、シローの定理を使います。
定理1.(シローの定理)
\(G\)を有限群、\(n=\left|G\right|\)、\(p\)を\(n\)の素因数とし、\(p^a\ (a>0)\)を\(n\)を割り切る\(p\)の最大のベキとする(すなわち、\(n=p^am\)で\(m\)と\(p\)は互いに素である)。このとき、次の1.から4.が成り立つ。- \(\left|H\right|=p^a\)となるような\(G\)の部分群\(H\)が存在する。このような部分群\(H\)をシロー\(p\)部分群という。
- シロー\(p\)部分群を一つ固定する。部分群\(K\subset G\)に対して\(\left|K\right|\)が\(p\)ベキならば、\(K\subset gHg^{-1}\)となる\(g\in G\)が存在する。特に、\(K\)を含む\(G\)のシロー\(p\)部分群が存在する。
- \(G\)の全てのシロー\(p\)部分群は共役である。
- シロー\(p\)部分群の数\(s\)は $$ s=\frac{\left|G\right|}{\left|{\rm N}_G(H)\right|}\equiv 1\ ({\rm mod}\ p\ ) $$ という条件を満たす。
シローの定理の証明は【代数学の基礎シリーズ】群論編 その27を御覧ください。
シローの定理から、この作用は推移的な作用(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その14)です。
\(\varphi:G\longrightarrow \mathcal{G}_4\)をこの作用による置換表現(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その13)とします。
つまり、\(gK_ig^{-1}=K_{\varphi(g)i}\ (i=1,2,3,4)\)です。
本題
\(K=\left\langle v\right\rangle\)とします。
\(\left|{\rm Aut}(K)\right|=2\)なので、\({\rm Ker}(\varphi)\neq\left\{1\right\}\)です。
故に、\(w\neq1\)であるような\({\rm Ker}(\varphi)\)の要素を取ることができます。
\(\varphi\)の定め方から、\(wvw^{-1}=v\)です。
\(G\)は非可換なので、\(bvb^{-1}=v^2\)となるような\(b\in H\)が存在します。
\(b\not\in\left\langle v\right\rangle\)なので、\(H\cong\left\langle b\right\rangle\times\left\langle w\right\rangle\)です。
\(a=wv\)とすると、\(w\)と\(v\)は可換なので、
$$
a^2=w^2v^2=v^2\neq1,\quad a^3=w^3v^3=w\neq1,\quad a^6=w^6v^6=1
$$
です。
したがって、\(a\)の位数は\(6\)です。
また、\(w\in\left\langle a\right\rangle\)です。
\(\left\langle a,b\right\rangle\supset\left\langle a\right\rangle,H\)なので、\(\left|\left\langle a,b\right\rangle\right|\)は\(6\)でも\(4\)でも割り切れます。
\(\left|G\right|=12\)なので、\(G=\left\langle a,b\right\rangle\)です。
二面体群\(D_6\)は位数\(12\)の群で、2つの要素\(r,t\)で生成され、関係式\(r^6=t^2=1\)、\(trt^{-1}=r^{-1}\)を満たします。
$$
bab^{-1}=bwvb^{-1}=wbvb^{-1}=wv^2=v^2w=a^{-1}
$$
となるので、\(a,b\)が\(D_6\)の生成元と同じ関係式を満たします。
ちなみに、
$$
v^2wa=v^2w^2v=v^3=1
$$
です。
したがって、全射準同型
$$
L=\left\langle x,y\middle|x^6=y^2=1,\ yxy^{-1}=x^{-1}\right\rangle\longrightarrow D_6
$$
が存在します。
ちなみに、左辺は生成元と関係式で定義された群(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その30)です。
故に、\(\left|L\right|\geq12\)です。
しかしながら、\(L\)の任意の要素は関係式により\(y^ix^j\ (i=0,1,\ j=0,\dots,5)\)の形に表されるので、\(\left|L\right|\leq 12\)です。
したがって、\(\left|L\right|=12\)、\(L\cong D_6\)です。
全く同様にして、全射準同型\(L\longrightarrow G\)が存在します。
\(\left|L\right|=\left|G\right|=12\)なので、\(L\cong G\)です。
\(L\cong D_6\)だったわけですので、\(G\cong D_6\)となるわけです。
皆様のコメントを下さい!
数回に渡って、古代ギリシャで生まれた数学(特に幾何学)がデカルトの出現により大きく変化したということについて少々語ります。
前回は、古代ギリシャの数学は代数的な考え方が未発達だったために限界が来てしまった、という趣旨のことを語りました。
数の表現がインドで発明された記数法により著しく簡略化されました。
ヨーロッパでこの記数法が定着するには相当な時間を要したのですが、一旦それに慣れると人間の脳が塑性変形したかのように、10進法が最初からあったかの如く感じられるようになったのです。
数の表現については、その後小数や指数の表現を初めて考案したネーデルランドのステヴィン(Stevin, Simon;約1548-1620)の仕事があります。
現代表記とは異なるものの、その表現を通して数の実体を把握し始めたという意味で大きな意義があります。
数学そのものを記号を用いて表現する方法も、数の場合とまったく同様な効果をもたらしました。
鶴亀算などの問題を文章のみで解くことに慣れていたとしても、一旦数式を使って解く方法を学ぶと、もう後戻りはできないほど脳の構造は変化してしまいます。
同じことが数学の歴史で起こったのです。
記号の導入は、それまで行われていた難渋な文章による表現を簡易化しただけでなく、数学の「思考方法」にも重大な効果を生じ、このことによって数学の発展が大きく加速しました。
その先駆けとなったのがフランスのヴィエタ(Vieta, Franciscus;1540-1603)です。
ヴィエタ
最初法律を学び故郷のフォントネー・ル・コント(Fontenay-le-Comte)で弁護士の職につきましたが、1567年に辞職し、1571年にパリに移って政治家となりました。ユグノー派の新教徒の頭目フォ ンローアンの推挙によって1573年にアンリ3世の顧問官、1580年にパリ大審院付請願部長官、そしてアンリ4世の枢密院顧問官となりました。
政治に携わりながら、その余暇に数学の研究を行い、自費出版で論文を各国の学者に配布しました。
アンリ4世の下で暗号解読にも携わり、敵方のスペインに恐れられたそうです。
ヴィエタは、1591年に出版された『解析術入門』(In artem analyticam isagoge)の中で、既知数を子音文字で、未知数を母音文字で表しました。
現代から見れば煩わしさは残っているものの、代数学をすべて記号を用いて書き表すことは、それまでにはなかった画期的な出来事でした。
その発想の背景にあるのは、「代数を幾何学のように厳密にする」ことです。
当時は幾何学の根底は磐石ですが、代数には曖昧さが残っていると思われていたのです(今日では、実数論を用いて代数的に作られたモデルにより、厳密な幾何学が構成されると考えられています)。
例を挙げれば、現代の数式\(x^3 + 3bx = 2x\)に対するヴィエタによる記号表現は
です。
ヴィエタ以前に、イタリアでルカ・パチオリ(Luca Pacioli;1445-1517)やボンベリ(Bombelli, Rafael;1526-1572)らがある程度の記号化を行っていましたが、完全なものではありませんでした。
プラスとマイナスの記号\(+,−\)は、既にドイツのグラマテウス(Henricus Grammateus;1495-1525) が使用しています(1518)。
平方根の記号\(\sqrt{\cdot}\)は、1525年にドイツのルドルフ(Christoph Rudolff;1499-1545)が導入し、等号(\(=\))については、イギリス(ウェールズ)のレコード(Recorde, Robert;1510頃-1558)が導入しました(1557)。
ヴィエタ以後では、掛け算記号\(\times\)はイギリスのオートレッド(Oughtred, William;1574-1660)が初めて導入しました(1631)。
イギリスのハリオット(Harriot, Thomas;1560-1621)は、記号代数学の進歩をしるす著書『代数方程式を解くための実践解析技術(“Artis analyticae praxis ad aequationes algebraicas resolvendas”)』において、等号のほかに大小を表すのに記号\(<,>\)を用い、ベキについては\(a^2\)を\(aa\)、\(a^3\)を \(aaa\)で表現しました(1631)。
こうしてデカルトの時代になると、現代使われている記号のほとんどが用いられるようになり。数学は質的に変化したのです。
記号表記は、その後ライプニッツによる普遍数学の構想を経て、イギリスのブール(Boole, George; 1815-1864)およびフレーゲにより論理学にまで適用されることになりました。
次回はいよいよデカルトが登場します。
補足情報、感想を是非コメントでお待ちしています!
結
今回は位数が12の群の分類の一部として、二面体群と同型となる場合について解説しました。
位数12の群は位数自体が比較的小さく、そして群論の知識をフル稼働で使うため群論そのものの良い復習となるだけでなく、群論の見通しを良くします。
今回で、証明はおしまいです。
次回は有限アーベル群について解説します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。
もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。
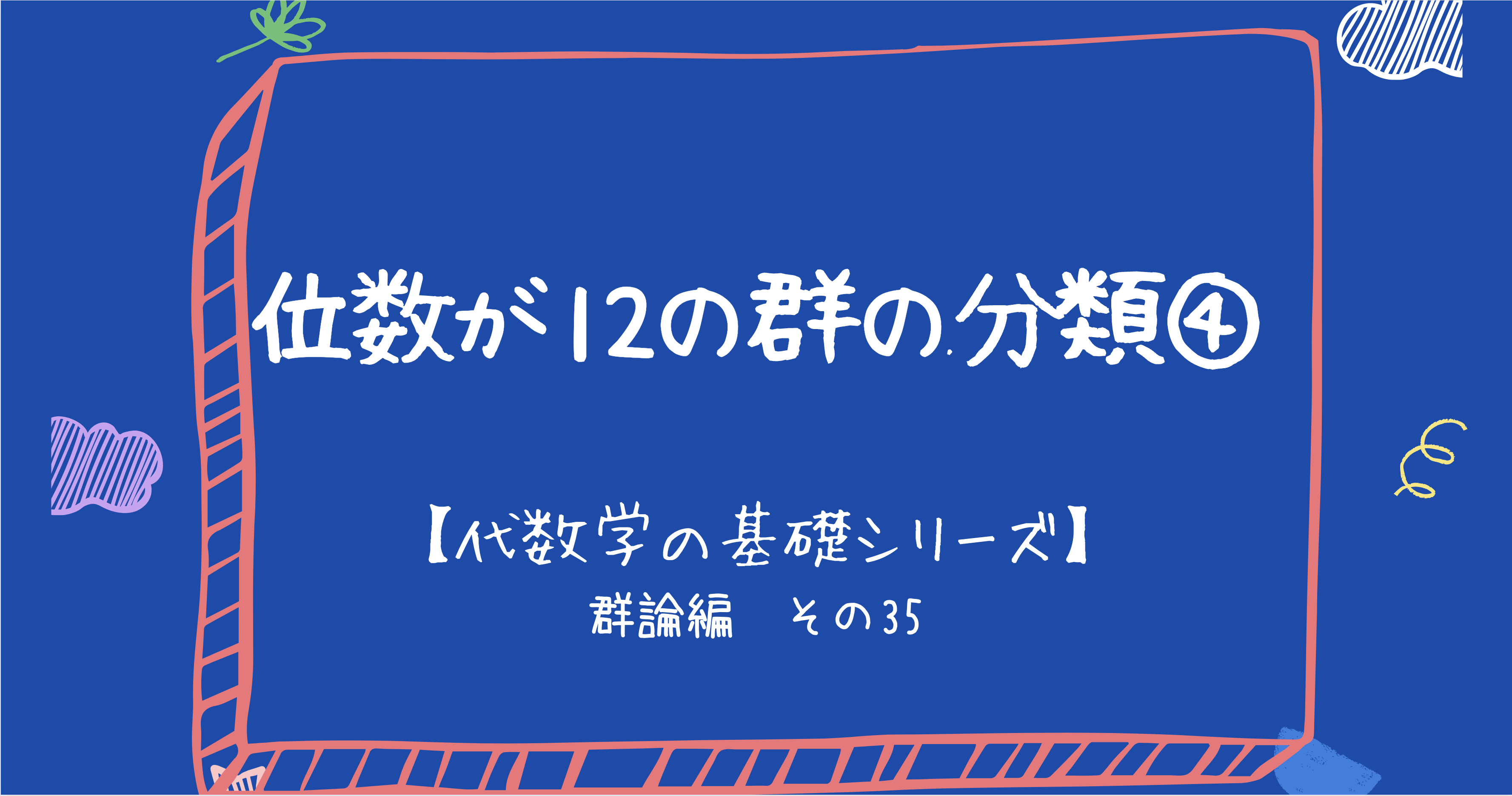
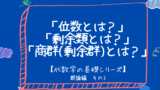


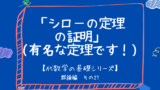


コメントをする