本記事の内容
本記事は不定積分の計算、特に有理関数の不定積分の計算方法を解説する記事です。
本記事を読むにあたり、各種原始関数について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。
↓多項式関数、有理関数、無理関数の原始関数の記事
↓三角関数、指数関数、対数関数の原始関数の記事
初等関数の原始関数は必ずしも初等関数ではありません。
連続な関数の原始関数は、連続関数が可積分であるという以下の2つの事実から存在が保証されています。
定理1.(連続関数の可積分性)
\(\mathbb{R}^n\)の有界閉集合\(I\)上で連続な関数\(\boldsymbol{f}:I\to\mathbb{R}^m\)は、\(I\)上で可積分である。定理1.の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その12を御覧ください。
定理0.(微分積分学の基本定理)
\(I\)を\(\mathbb{R}\)の有界閉区間、\(f\)を\(I\)上の実数値関数、すなわち\(f:I\to\mathbb{R}\)とする。このとき以下の2つが成り立つ。- \(f\)が\(I\)で微分可能で、導関数\(f^\prime\)が\(I\)上で可積分(例えば、連続)ならば、任意の\(a,b\in I\)に対して $$ \int_a^bf^\prime(x)\ dx=f(b)-f(a)\cdots① $$ が成り立つ。
- \(f\)が\(I\)上で可積分で、1点\(x\in I\)で連続ならば、\(f\)の不定積分\(\displaystyle F(x)=\int_a^xf(y)\ dy\)は\(x\)で微分可能で、\(F^\prime(x)=f(x)\)が成り立つ。
定理0.の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その14を御覧ください。
\(\displaystyle\frac{1}{x}\)の原始関数が\(\log x\)であるように、初等関数の原始関数は、より”複雑な”関数となることもあります。
例えば、
\begin{eqnarray}
&&{\rm Li}(x)=\int_2^x\frac{1}{\log t}\ dt,\\
&&{\rm Si}(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{t}\ dt,\\
&&F(k,\varphi)=\int_0^\varphi\frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2t}}\ dt\quad (0<k<1),\\
&&E(k,\varphi)=\int_0^\varphi\sqrt{1-k^2\sin^2t}\ dt\quad (0<k<1)\\
\end{eqnarray}
はそれぞれ、積分対数、積分正弦、第一種および第二種不完全楕円積分と呼ばれる関数で、これらのどれもが初等関数では表されないことが知られています。
要するに、高校数学で習ったような関数では書き表せない、ということです。
何が言いたいかと言うと、原始関数は必ずしも初等関数ではない、ということです。
今回から数回に渡って初等関数の不定積分で、かつ初等関数で表されるものを扱って不定積分を実際に計算します。
今回は有理関数です。
有理関数の原始関数を求める発想
まず最初に重要なのは「有理関数は可積分なんですか?」ということですが、これは定義域で可積分です。
なぜかと言うと、有理関数\(R(x)\)は分母が\(0\)でない点において連続だからです。
どうして連続かというと、\(R(x)\)は多項式関数\(f(x),g(x)\)を用いて
$$
R(x)=\frac{g(x)}{f(x)}\quad(f(x)\neq0)
$$
と書け、多項式関数\(f(x),g(x)\)はそれぞれ定義域で連続ですから、有理関数は\(f(x)\neq0\)を満たす\(x\)で連続です。
故に、\(f(x)\neq0\)を満たす\(x\)で、すなわち\(R(x)\)の定義域で可積分です。
さて、可積分なことは分かりましたが、有理関数の原始関数をどうやって求めるのでしょうか。
これは誠にシンプルな発想です。
結論から言うと、
です。
部分分数分解は高校数学で既に学習していますが、平たく言うと、部分分数分解とは
です。
具体的にどうやって部分分数分解をするかということについては、次節で解説します。
部分分数分解を使って実際に原始関数を計算してみます。
まず、次数に対する注意をします。
\(n\)次の多項式関数
$$
f(x)=\sum_{i=0}^na_ix^i=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0
$$
に対して、\(n\)を\(\deg f\)と書いて、多項式関数\(f\)の次数と呼びます。
有理関数\(\displaystyle R(x)=\frac{g(x)}{f(x)}\)に対して\(\deg f\)と\(\deg g\)の関係は
$$
\deg f>\deg g,\quad \deg f=\deg g,\quad \deg f<\deg g
$$
のいずれか1つが成り立ちます。
\(\deg f=\deg g\)か\(\deg f<\deg g\)の場合、すなわち\(\deg f\leq \deg g\)の場合は\(g\)と\(f\)との割り算をすることで、\(R(x)\)は多項式と真分数式の和として書けます。
要するに、有理関数\(R(x)\)おいて、分母の次数\(\leq\)分子の次数を満たす場合、\(R(x)\)は多項式\(+\)分数式の形で書け、分数式においては分母の次数\(>\)分子の次数となるように変形できます。
したがって、以下では真分数式の場合についてのみの話をします。
例2. \(\displaystyle\int \frac{1}{x^2-a^2}\ dx\)を計算してみます。
実は、以前の記事で、この不定積分は以下だと解説しました。
命題3.
\(\displaystyle f(x)=\frac{1}{x^2-a^2}\ (a\neq0)\)の原始関数\(\displaystyle F(x)=\int f(x)\ dx\)は $$ F(x)=\frac{1}{2a}\log\left|\frac{x-a}{x+a}\right| $$ である。命題3.の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その16を御覧ください。
この\(F\)が部分分数分解によって出現する、ということをこれから計算してみます。
\(\displaystyle\frac{1}{x^2-a^2}\)は
$$
\frac{1}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\left\{\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right\}\quad(a\neq0)
$$
と部分分数分解できます。
従って、
\begin{eqnarray}
\int \frac{1}{x^2-a^2}\ dx&=&\int\frac{1}{2a}\left\{\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right\}\ dx\\
&=&\frac{1}{2a}\left(\int\frac{1}{x-a}\ dx-\int\frac{1}{x+a}\ dx\right)\\
&=&\frac{1}{2a}\left(\log|x-a|+\log|x+a|\right)\\
&=&\frac{1}{2a}\log\left|\frac{x-a}{x+a}\right|\\
\end{eqnarray}
となります。
より具体的な例を計算してみましょう。
例4. \(\displaystyle\int\frac{3x^2-3x-9}{(x+2)(x-1)^2}\ dx\)を計算してみます。
まず、部分分数分解をします。
$$
\frac{3x^2-3x-9}{(x+2)(x-1)^2}=\frac{A}{x+2}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2}
$$
として、\(A,B,C\)を求めます。
\begin{eqnarray}
&&\frac{A}{x+2}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2}\\
&=&\frac{A(x-1)+B(x+2)}{(x+2)(x-1)}+\frac{C}{(x-1)^2}\\
&=&\frac{(Ax-A+Bx+2B)(x-1)+C(x+2)}{(x+2)(x-1)^2}\\
&=&\frac{Ax^2-Ax-Ax+A+Bx^2-Bx+2Bx-2B+Cx+2C}{(x+2)(x-1)^2}\\
&=&\frac{(A+B)x^2+(-2A+B+C)x+(A-2B+2C)}{(x+2)(x-1)^2}\\
\end{eqnarray}
ですので、連立方程式
$$
\begin{cases}
A+B=3\\
-2A+B+C=-3\\
A-2B+2C=-9
\end{cases}
$$
を解くことで\(A,B,C\)が得られます。
これを解けば、
$$
A=1,\quad B=2,\quad C=-3
$$
ですので、
$$
\frac{3x^2-3x-9}{(x+2)(x-1)^2}=\frac{1}{x+2}+\frac{2}{x-1}-\frac{3}{(x-1)^2}
$$
が得られます。
故に
\begin{eqnarray}
\int\frac{3x^2-3x-9}{(x+2)(x-1)^2}\ dx&=&\int\left(\frac{1}{x+2}+\frac{2}{x-1}-\frac{3}{(x-1)^2}\right)\ dx\\
&=&\int\frac{1}{x+2}\ dx+\int\frac{2}{x-1}\ dx-\int\frac{3}{(x-1)^2}\ dx\\
&=&\log|x+2|+2\log|x-1|+\frac{3}{x-1}\\
&=&\log|x+2|+\log(x-1)^2+\frac{3}{x-1}\\
&=&\log\left\{|x+2|(x-1)^2\right\}+\frac{3}{x-1}
\end{eqnarray}
です。
厳密な部分分数分解のお話
一般に、有理関数の部分分数分解はどのようになるか、ということを表す定理を紹介、証明します。
部分分数分解の定理の明示
定理5.
実係数の有理関数\(\displaystyle R(x)\frac{g(x)}{f(x)}\ \)(\(f.g\)は実係数多項式で、\(\deg g<\deg f\))の分母\(f(x)\)の相異なる実根が\(a_j\ (1\leq j\leq k)\)、\(a_j\)の重複度が\(m_j\)、相異なる虚根が\(a_j\pm ib_j\ (k+1\leq j\leq l,\ b_j\neq0)\)で、その重複度を\(m_j\)とするとき、\(R(x)\)は \begin{eqnarray} R(x)=\sum_{j=1}^k\sum_{m=1}^{m_j}\frac{c_{jm}}{(x-a_j)^m}+\sum_{j=k+1}^l\sum_{m=1}^{m_j}\frac{d_{jm}x+e_{jm}}{\left\{(x-a_j)^2+b_j^2\right\}^m}\cdots① \end{eqnarray} と表される。ただし、\(c_{jm},d_{jm},e_{jm}\in\mathbb{R}\)である。「複雑だなあ」と思うかもしれませんが、よく見るとどうってことありません。
先程の例4.を定理5.で確かめてみます。
複雑なので、例4.に適用させてみます。
\(f(x)=(x+2)(x-1)^2\)、\(g(x)=3x^2-3x-9\)とします。
このとき、\(f(x)=0\)を満たす\(x\)は\(x=-2,1\)で、\(x=1\)の重複度が\(2\)です。
これは定理5.において、\(a_1=-2\)、\(m_1=1\)、\(a_2=1\)、\(m_2=2\)、\(k=2\)です。
また、\(f(x)=0\)を満たす\(x\)は全て実数であることにも注意します。
従って、
\begin{eqnarray}
R(x)&=&\sum_{j=1}^k\sum_{m=1}^{m_j}\frac{c_{jm}}{(x-a_j)^m}+\sum_{j=k+1}^l\sum_{m=1}^{m_j}\frac{d_{jm}x+e_{jm}}{\left\{(x-a_j)^2+b_j^2\right\}^m}\\
&=&\sum_{j=1}^2\sum_{m=1}^{m_j}\frac{c_{jm}}{(x-a_j)^m}+0\\
&=&\sum_{m=1}^{m_1}\frac{c_{1m}}{(x-a_1)^m}+\sum_{m=1}^{m_2}\frac{c_{2m}}{(x-a_2)^m}\\
&=&\sum_{m=1}^{1}\frac{c_{1m}}{(x+2)^m}+\sum_{m=1}^{2}\frac{c_{2m}}{(x-1)^m}\\
&=&\frac{c_{11}}{x+2}+\frac{c_{21}}{x-1}+\frac{c_{22}}{(x-1)^2}
\end{eqnarray}
となります。
これはまさに、例4.で見た
$$
\frac{3x^2-3x-9}{(x+2)(x-1)^2}=\frac{A}{x+2}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2}
$$
と同じ形が得られます。
部分分数分解の定理の証明
では、証明しましょう。
定理5.の証明
\(a\in\mathbb{R}\)が\(f(x)=0\)の\(m\)重根のとき、
$$
f(x)=(x-a)^m\varphi(x),\quad \varphi(a)\neq0
$$
となるような多項式\(\varphi(x)\)が存在します。
今、
$$
A=\frac{g(a)}{\varphi(a)}
$$
とすると、\(A\in\mathbb{R}\)で、\(\displaystyle g(x)-A\varphi(x)=g(x)-\frac{g(a)}{\varphi(a)}\varphi(x)\)は\(x=a\)で\(0\)となるから、
$$
g(x)-A\varphi(x)=(x-a)g_1(x)
$$
という多項式\(g_1(x)\)が存在します。
このとき、\(f_{\color{red}{1}}(x)=(x-a)^{m-\color{red}{1}}\varphi(x)\)とおくと(これは単に以下の式を見やすくするために導入した記号です)、
\begin{eqnarray}
R(x)&=&\frac{g(x)}{f(x)}\\
&=&\frac{A\varphi(x)+(x-a)g_1(x)}{(x-a)^m\varphi(x)}\\
&=&\frac{A}{(x-a)^m}+\frac{g_1(x)}{f_1(x)}
\end{eqnarray}
となります。
ここで、
$$
f_{\color{red}{m}}(x)=(x-a)^{m-\color{red}{m}}\varphi(x)=\varphi(x)=\frac{f(x)}{(x-a)^m}
$$
としたとき、
$$
\frac{g(x)}{f(x)}=\sum_{p=1}^m\frac{A_p}{(x-a)^p}+\frac{g_m(x)}{f_m(x)},\quad \deg g_m<\deg f_m
$$
となります。
そこで、\(f_m\)の根について同じことを繰り返せば、①の実根の部分が出現して、残りの分母は\(f\)の虚根のみを根とする多項式になります。
そこで今度は\(\alpha=a+bi\ (b\neq0)\)が\(f\)の\(m\)重根とすれば、\(\overline{\alpha}=a-bi\)もまた\(f\)の\(m\)重根で
$$
f(x)=\left\{(x-a)^2+b^2\right\}^m\psi(x)
$$
と表すことができます。
このとき、\(\psi\left( a\pm bi\right)\neq0\)ですから、
$$
g(\alpha)=\left( B\alpha+C\right)\psi(\alpha),\quad g(\overline{\alpha})=\left( B\overline{\alpha}+C\right)\psi(\overline{\alpha})
$$
によって\(B\)と\(C\)を定めることができます(\(B\)と\(C\)以外は全て定数だから、\(B\)と\(C\)を変数とする連立方程式によって求まります)。
この\(B\)と\(C\)が実数であれば良いわけです。
\(g\)と\(\psi\)は多項式ですので、\(g(\overline{\alpha})=\overline{g(\alpha)}\)、\(\psi(\overline{\alpha})=\overline{\psi(\alpha)}\)です。
また、
\begin{eqnarray}
\overline{g(\alpha)}&=&\overline{\left( B\alpha+C\right)\psi(\alpha)}\\
&=&\overline{B\alpha+C}\cdot\overline{\psi(\alpha)}\\
&=&\left(\overline{B}\overline{\alpha}+\overline{C}\right)\cdot\overline{\psi(\alpha)}\\
&=&\left(\overline{B}\overline{\alpha}+\overline{C}\right)\cdot\psi(\overline{\alpha})\\
\end{eqnarray}
であり、今、\(g(\overline{\alpha})=\overline{g(\alpha)}\)ですので、
\begin{eqnarray}
\overline{B}\overline{\alpha}+\overline{C}\cdot\psi(\overline{\alpha})=\left( B\overline{\alpha}+C\right)\psi(\overline{\alpha})&\Longleftrightarrow&B=\overline{B},\quad C=\overline{C}
\end{eqnarray}
となるから、\(B,C\in\mathbb{R}\)です。
実根のときと同様に、\(g(x)=\left( Bx+C\right)\psi(x)\)は\(x=\alpha,\overline{\alpha}\)で\(0\)となり、\(\alpha\neq\overline{\alpha}\)だから、この多項式は\((x-\alpha)(x-\overline{\alpha})\)で割り切れます。
すなわち、ある多項式\(G_1(x)\)が存在して、
$$
g(x)=\left( Bx+C\right)\psi(x)=\left\{(x-a)^2+b^2\right\}G_1(x)
$$
となります。
そこで、\(F_\color{red}{1}(x)=\left\{(x-a)^2+b^2\right\}^{m-\color{red}{1}}\psi(x)\)と書くことにすれば、
$$
\frac{g(x)}{f(x)}=\frac{Bx+C}{\left\{(x-a)^2+b^2\right\}^m}+\frac{G_1(x)}{F_1(x)}
$$
となります。
そこで、実根の場合と同様にこの操作を繰り返すことで①の虚根の部分が導けます。
この操作の最後に残った有理式を\(h(x)\)とします。
\(h(x)\)の分母は定数(\(\neq0\))であり、\(h(x)\)は多項式です。
実は、この多項式\(h\)は\(0\)です。
なぜなら、仮定\(\deg g<\deg f\)から、\(x\to+\infty\)とするとき、\(R(x)\to0\)であり、また部分分数も\(0\)に収束するから、\(h\neq0\)であれば矛盾するからです。
定理5.の証明終わり
有理関数の不定積分
定理5.から、有理関数の不定積分を求めるには、次の形の不定積分を求めれば良い、ということが分かります。
定理6.
\(n\geq1\)を自然数、\(a,b\in\mathbb{R}\)、\(b\neq0\)のとき、次のことが成り立つ。- \(\displaystyle\int\frac{1}{(x-a)^n}\ dx= \begin{cases} \displaystyle-\frac{1}{n-1}\cdot\frac{1}{(x-a)^{n-1}},&(n>1)\\ \log|x-a|,&(n=1) \end{cases} \)
- \(\displaystyle\int\frac{x}{(x^2+b^2)^n}\ dx= \begin{cases} \displaystyle-\frac{1}{2(n-1)}\cdot\frac{1}{(x^2+b^2)^{n-1}},&(n>1)\\ \displaystyle\frac{1}{2}\log\left(x^2+b^2 \right),&(n=1) \end{cases} \)
- \(\displaystyle I_n=\int\frac{1}{(x^2+b^2)^n}\ dx= \begin{cases} \displaystyle\frac{1}{b^2}\left\{\frac{x}{(2n-2)(x^2+b^2)^{n-1}}+\frac{2n-3}{2n-2}I_{n-1}\right\},&(n>1)\\ \displaystyle\frac{1}{b}\arctan\frac{x}{b},&(n=1) \end{cases} \)
定理6.の証明
(1.の証明)
右辺を微分するだけです。
\(n>1\)のとき、
\begin{eqnarray}
\left( -\frac{1}{n-1}\cdot\frac{1}{(x-a)^{n-1}}\right)^\prime&=&\left( -\frac{1}{n-1}\cdot(x-a)^{-n+1}\right)^\prime\\
&=&\frac{1}{-n+1}\cdot(-n+1)(x-a)^{-n}\\
&=&\frac{1}{(x-a)^n}
\end{eqnarray}
であり、\(n=1\)のときは
$$
\left( \log|x-a|\right)^\prime=\frac{1}{x-a}
$$
となるので、成り立ちます。
(2.の証明)
以下の置換積分法を使います。
定理7.(置換積分)
関数\(f:I=[a,b]\to\mathbb{R}\)、\(\varphi:J=[\alpha,\beta]\to\mathbb{R}\)が次の1.から4.を満たすとする。- \(f\)は\(I\)で連続である。
- \(\varphi\)は\(J\)で微分可能である。
- \(\varphi^\prime\)は\(J\)で有界かつ可積分である(例えば、連続)。
- \(\varphi(J)\subset I,\ \varphi(\alpha)=a,\ \varphi(\beta)=b\)
定理7.の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その18を御覧ください。
\(\displaystyle\int\frac{x}{(x^2+b^2)^n}\ dx\)に対して、\(x^2=t\)という置換をすることで1.の場合に帰着されます。
(3.の証明)
以下の部分積分法を使います。
定理8.(部分積分法)
\(I=[a,b]\)を\(\mathbb{R}\)の閉区間とし、\(f:I\to\mathbb{R}\)、\(f^\prime:I\to\mathbb{R}\)、\(g:I\to\mathbb{R}\)、\(g^\prime:I\to\mathbb{R}\)が\(I\)上で可積分(例えば、連続または単調である)とする。このとき、 $$ \int_a^bg^\prime(x)f(x)\ dx=\left[g(x)f(x) \right]_a^b-\int_a^bg(x)f^\prime(x)\ dx $$ が成り立つ。特に、\(g(x)=x\)のとき、 $$ \int_a^bf(x)\ dx=\left[xf(x) \right]_a^b-\int_a^bxf^\prime(x)\ dx $$ である。
定理8.の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その19を御覧ください。
定理8.により、
\begin{eqnarray}
I_n&=&\color{blue}{\frac{1}{b^2}}\int\frac{\color{red}{x^2}\color{blue}{+b^2}\color{red}{-x^2}}{(x^2+b^2)^n}\ dx\\
&=&\frac{1}{b^2}I_{n-1}-\frac{1}{\color{green}{2}b^2}\int x\frac{\color{green}{2}x}{(x^2+b^2)^n}\ dx\\
&=&\frac{1}{b^2}I_{n-1}-\frac{1}{2b^2}\left\{-\frac{1}{n-1}\cdot\frac{x}{(x^2+b^2)^{n-1}}+\frac{1}{n-1}I_{n-1}\right\}\\
&=&\frac{1}{b^2}\left\{\frac{x}{(2n-2)(x^2+b^2)^{n-1}}+\frac{2n-3}{2n-2}I_{n-1}\right\}
\end{eqnarray}
です。
\(n=1\)の場合は単に微分すれば確かめられます。
定理6.の証明終わり
定理5.と定理6.の主張をまとめると、
定理9.
有理関数の不定積分は、有理関数と対数関数、逆正接関数(\(\arctan\))で表される。ということになります。
実際に計算してみます。
では、最後にまとめとして今回解説したことを使って次の問題を解いてみます。
例10. \(\displaystyle I=\int\frac{1}{x^4+1}\ dx\)を求めてみます。
まずは部分分数分解します。
$$
x^4+1=(x^2+1)^2-2x^2=\left( x^2+\sqrt{2}x+1\right)\left( x^2-\sqrt{2}x+1\right)
$$
により、
$$
\frac{1}{x^4+1}=\frac{Ax+B}{x^2+\sqrt{2}x+1}+\frac{Cx+D}{x^2-\sqrt{2}x+1}
$$
として、\(A,B,C,D\)を求めます。
連立方程式を解くと、
\begin{eqnarray}
&&A=\frac{1}{2\sqrt{2}},\\
&&B=\frac{1}{2},\\
&&C=-\frac{1}{2\sqrt{2}},\\
&&D=\frac{1}{2}
\end{eqnarray}
となるので、定理6.により、
\begin{eqnarray}
\int\frac{1}{x^4+1}\ dx&=&\frac{1}{4\sqrt{2}}\log\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}\\
&&+\frac{1}{2\sqrt{2}}\left\{\arctan\left( \sqrt{2}x+1\right)+\arctan\left( \sqrt{2}x-1\right)\right\}
\end{eqnarray}
となります。
皆様のコメントを下さい!
記事の内容とは一切関係がないのですが、皆様は海外へ行ったことがありますか?
筆者は一回もありません。
博士後期課程では(大学に依ると思いますが)、国際学会で発表をする機会をいただくことがあります。
それに備え、博士後期課程に入院(大学院に入学することを入院といいます。「○年で退院できると良いね」なんてジョークがあります。)した直後に「もしかしたら海外に行かせてもらえるかもしれない!」と思いパスポートを取得しました。
しかし、パスポートを取ったはよかったものの、なかなか渡航の機会はなく、さらにコロナ禍により、研究集会は軒並みオンラインでの実施となりました。
そんな中でも、オンラインではありますが、国際学会での発表機会を頂き、発表させていただきました。
でも、やはり「海外に行ってみたいなあ」と思っています。
筆者はイギリスを初めヨーロッパに行ってみたいです。
ハリー・ポッターシリーズが好きということもあり、イギリスが最も行きたい国です。
しかもイギリスには、かの有名なアイザック・ニュートンが教鞭をとり、万有引力の法則を発見したリンゴの木があるケンブリッジ大学があります。
1回でいいので行ってみたいです。
皆様は渡航経験はありますか?
どんな国に行かれましたか?
また、どの国に行ってみたいですか?
是非コメントで教えて下さい!
結
今回は、有理関数の不定積分の計算方法について解説しました。
有理関数の不定積分の計算の発想は「部分分数分解」です。
次回は、三角関数の不定積分の計算について解説します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。
もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。
この記事の内容をより詳しく知りたい方は以下のリンクの本を参照してください!
ちなみに「解析概論」は日本の歴史的名著らしいので、辞書的にもぜひ1冊持っておくと良いと思います!
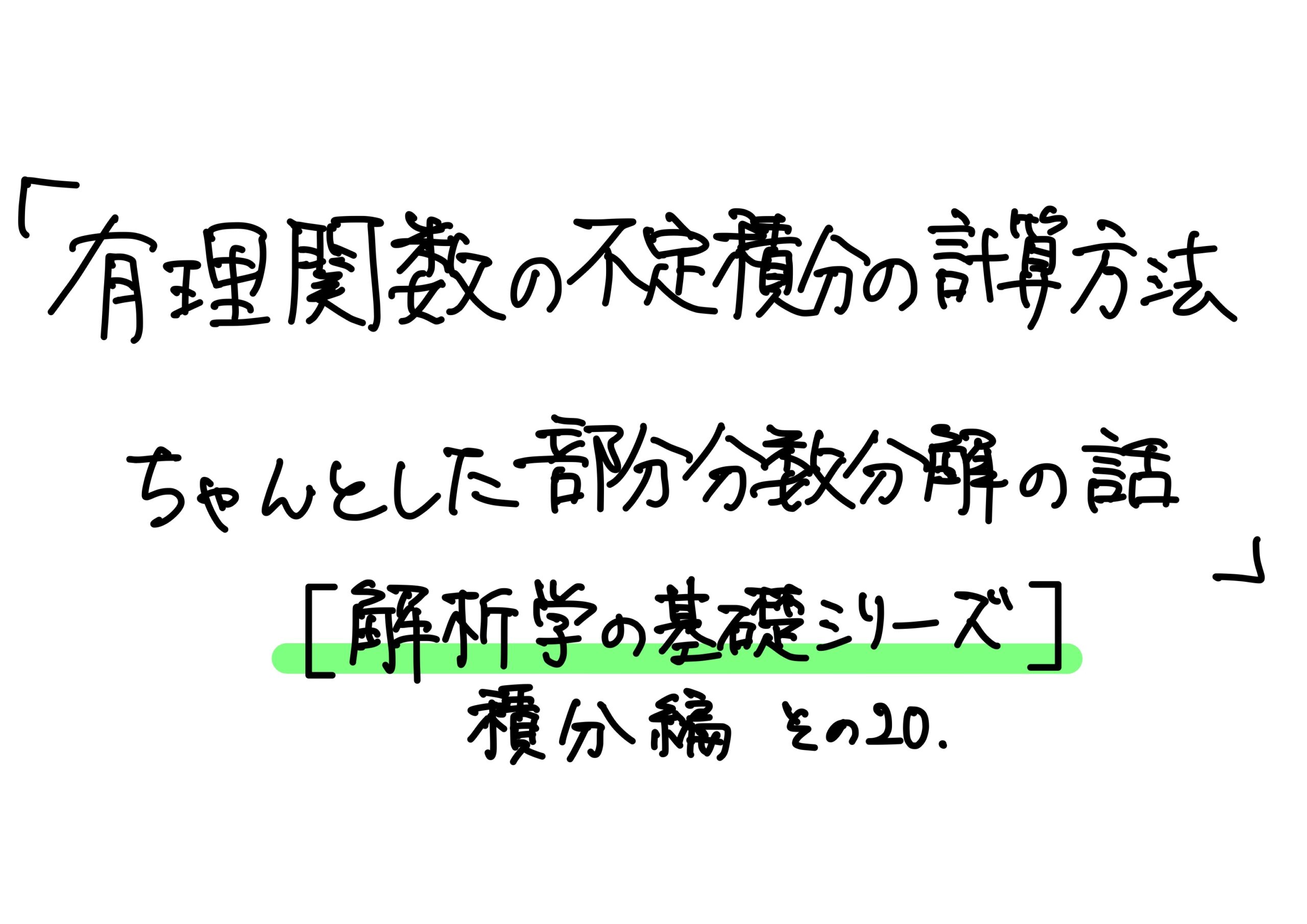
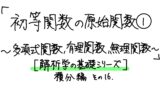
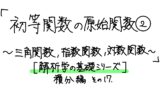
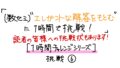

コメントをする