本記事の内容
本記事はロピタルの定理を紹介し、証明する記事です。
本記事を読むにあたり、コーシーの第二平均値定理を知っている必要があるため、以下の記事も合わせて御覧ください。
ロピタルの定理は不定形の極限の計算に有用です。
例えば、次の極限を求めよ、と言われたとします。
例1.\(\displaystyle\lim_{x\to+0}\frac{e^x-1}{x^3}\)
真正直に計算しようとすると、\(\displaystyle\frac{\infty}{\infty}\)となって不定形です。
少し見方を変えて、「\(x\)がデカかったら\(e^x\)は\(x\)よりもデカいから\(\infty\)かな?」と思えるかもしれませんが、あくまで予想です。
勿論、厳密に証明しようとすると\(\epsilon-\delta\)論法で証明するわけですが、骨が折れます。
そこで有用なのが、ロピタルの定理なのです。
要するに、ロピタルの定理というのは、平たく言うと
\(\displaystyle\frac{f}{g}\)の極限が\(\displaystyle\frac{f^\prime}{g^\prime}\)の極限と一致してますよ。
ということです。
ロピタルの定理の明示
ではロピタルの定理を明示します。
と、その前に、ロピタルの定理は大きく分けて2種類存在します。
それは、
- \(x\to a\)のとき
- \(x\to\infty\)のとき
です。
では、明示します。
ある\(a\in\mathbb{R}\)に近づけるとき
ある\(a\in\mathbb{R}\)に近づけるとき、分子分母の極限が\(0\)の場合
\(f\)と\(g\)は\(\mathbb{R}\)の開区間\((a,b)\)で定められていて、微分可能であり、以下の3条件を満たすとする。
- \(\displaystyle\lim_{x\to a+0}f(x)=\lim_{x\to a+0}g(x)=0\)、
- \((\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in (a,a+\delta))\ g(x)\neq 0\land g^\prime(x)\neq0\)、
- \(\displaystyle\lim_{x\to a+0}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A\)
「ん?右極限だけ?」と思われるかもしれません。
大丈夫です。左極限についても同じことが成り立ちます。
すなわち、以下が成り立ちます。
\(f\)と\(g\)は\(\mathbb{R}\)の開区間\((a,b)\)で定められていて、微分可能であり、以下の3条件を満たすとする。
- \(\displaystyle\lim_{x\to a-0}f(x)=\lim_{x\to a-0}g(x)=0\)、
- \((\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in (a-\delta,a))\ g(x)\neq 0\land g^\prime(x)\neq0\)、
- \(\displaystyle\lim_{x\to a-0}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A\)
つまり、上記の2つ(右極限と左極限)が成り立つので、
(この定理3.の証明は【解析学の基礎シリーズ】関数の極限編 その6を御覧ください。)
定理3.から\(\displaystyle\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}\)ですよ、という話です。
ある\(a\in\mathbb{R}\)に近づけるとき、分母の極限が\(\infty\)の場合
\(f\)と\(g\)は\(\mathbb{R}\)の開区間\((a,b)\)で定められていて、微分可能であり、以下の3条件を満たすとする。
- \(\displaystyle\lim_{x\to a+0}g(x)=\infty\)、
- \((\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in (a,a+\delta))\ g(x)\neq 0\land g^\prime(x)\neq0\)、
- \(\displaystyle\lim_{x\to a+0}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A\)
先の場合と同様に、左極限についても同じことが成り立ちます(定理が乱立してしまうので省略)。
無限大に近づけるとき、分日分母の極限が\(0\)である場合
\(f\)と\(g\)は\(\mathbb{R}\)の開区間\((a,\infty)\)で定められていて、微分可能であり、以下の3条件を満たすとする。
- \(\displaystyle\lim_{x\to \infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}g(x)=0\)、
- \((\exists R\in(a,\infty))\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in (R,\infty))\ g(x)\neq 0\land g^\prime(x)\neq0\)、
- \(\displaystyle\lim_{x\to \infty}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A\)
では、証明しましょう!
いざ、証明
定理2.の証明
定理が乱立してしまいますが、もう一度定理2.を明示します。
\(f\)と\(g\)は\(\mathbb{R}\)の開区間\((a,b)\)で定められていて、微分可能であり、以下の3条件を満たすとする。
- \(\displaystyle\lim_{x\to a+0}f(x)=\lim_{x\to a+0}g(x)=0\)、
- \((\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in (a,a+\delta))\ g(x)\neq 0\land g^\prime(x)\neq0\)、
- \(\displaystyle\lim_{x\to a+0}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A\)
左極限の場合、すなわち定理2′.は定理2.(右極限)と同じ方法で証明できるので省略します。
定理2.の証明
定理2.の仮定から、\(f\)と\(g\)は\(x=a\)で値が定められていません。
そこで、以下のようにします。
\begin{eqnarray}
F(x)=
\begin{cases}
f(x) & (x\in(a,b))\\
0 & (x=a)
\end{cases},\quad
G(x)=
\begin{cases}
g(x) & (x\in(a,b))\\
0 & (x=a)
\end{cases}
\end{eqnarray}
このようにすることで、\(F\)と\(G\)は\([a,x]\)で連続です。
さらに、今、\(g(a)=0\)かつ\(g(x)\neq 0\)ですので、\(G(a)\neq G(x)\)です。
また、\(g^\prime(x)\neq0\)ですので、\(F^\prime(x)\)と\(G^\prime(x)\)は同時に0になりません。
故に、コーシーの第二平均値定理の仮定を満たします。
コーシーの第二平均値定理は何だったか、というと、
でした。
コーシーの第二平均値定理の証明は【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その12を御覧ください。
さて、コーシーの第二平均値定理から、ある\(c_x\in(a,x)\)が存在して、
$$
\frac{F(x)}{G(x)}=\frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)}=\frac{F^\prime(c_x)}{G^\prime(c_x)}
$$
\(x>a\)を保ちつつ、\(x\to a\)とすれば、\(c_x>a\)(\(c_x\)は\(x\)と\(a\)の間に存在するから)かつ\(c_x\to a\)となります。
従って、
$$
\lim_{x\to a+0}\frac{F(x)}{G(x)}=\lim_{x\to a+0}\frac{F^\prime(c_x)}{G^\prime(c_x)}=\lim_{x\to a+0}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A
$$
となります。
定理2.の証明終わり
定理4.の証明
定理4.を再掲します。
\(f\)と\(g\)は\(\mathbb{R}\)の開区間\((a,b)\)で定められていて、微分可能であり、以下の3条件を満たすとする。
- \(\displaystyle\lim_{x\to a+0}g(x)=\infty\)、
- \((\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in (a,a+\delta))\ g(x)\neq 0\land g^\prime(x)\neq0\)、
- \(\displaystyle\lim_{x\to a+0}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A\)
先程述べたように、左極限についても同じように証明できるので、省略します。
定理4.の証明
仮定から
$$
\lim_{x\to a+0}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A
$$
ですので、
$$
(\forall \epsilon_0>0)\ (\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ \left((\forall x\in(a,a+\delta])\ \left|\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}-A\right|<\epsilon_0\right)
$$
が成り立っています。
ここで、\(\epsilon_0>0\)は任意ですので、\(0<\epsilon<1\)でも成り立っています。
すなわち、
$$
(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ \left((\forall x\in(a,a+\delta])\ \left|\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}-A\right|<\frac{\epsilon}{3}\right)
$$
が成り立っています。
この\(\delta\)に対して、
$$
\sup_{x\in(a,a+\delta]}\left|\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}\right|\leq |A|+\frac{\epsilon}{3}\leq |A|+1
$$
です。
もし仮に、\(g^\prime(x)=0\)という\(x\in(a,a+\delta]\)が存在したらば、\(\delta\)を新たに小さく取り直して\(g^\prime(x)\neq 0\)とします。
ここで、平均値の定理を使います。
平均値の定理は何だったか、というと、以下です。
平均値の定理の証明は【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その8を御覧ください。
今、\(g^\prime(x)\neq0\)であることと、平均値の定理から、任意の\(x\in(a,a+\delta)\)に対して、\(\displaystyle\frac{g(b)-g(a)}{b-a}=g^\prime(x)\neq0\)です。
すなわち\(g(x)-g(a+\delta)\neq0\)です。
このとき\(\displaystyle\lim_{x\to a+0}g(x)=\infty\)により、\(b^\prime\)を\(a<b^\prime<a+\delta\)かつ\(a\)の十分近くにとれば、
となります。
ここで、各\(x\in (a,b^\prime)\)に対して、コーシーの第二平均値定理から、ある\(\xi_x\in(x,a+\delta)\)が存在して、
$$
\frac{f(x)-f(a+\delta)}{g(x)-g(a+\delta)}=\frac{f^\prime(\xi_x)}{g^\prime(\xi_x)}
$$
が成り立ちます。
これを\(\displaystyle\frac{f(x)}{g(x)}\)を無理やり変形した
$$
\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(a+\delta)}{f(x)-f(a+\delta)}+\frac{f(a+\delta)}{g(x)}-\frac{g(a+\delta)}{g(x)}\cdot \frac{f(x)-f(a+\delta)}{f(x)-f(a+\delta)}
$$
(※右辺を計算してみると左辺と一致することが分かります。)
に代入してみると、
$$
\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f^\prime(\xi_x)}{g^\prime(\xi_x)}+\frac{f(a+\delta)}{g(x)}-\frac{g(a+\delta)}{g(x)}\cdot \frac{f^\prime(\xi_x)}{g^\prime(\xi_x)}
$$
となります。
以上のことから、\(x\in(a,b^\prime)\)に対して、
$$
\left|\frac{f(x)}{g(x)}-A\right|\leq \left|\frac{f^\prime(\xi_x)}{g^\prime(\xi_x)}-A\right|+\left|\frac{f(a+\delta)}{g(x)}\right|+\left|\frac{g(a+\delta)}{g(x)}\right|\cdot\left| \frac{f^\prime(\xi_x)}{g^\prime(\xi_x)}\right|\leq \frac{\epsilon}{3}+\frac{\epsilon}{3}+\frac{\epsilon}{3}=\epsilon
$$
となって、証明完了です。
定理4.の証明終わり
定理5.の証明
定理5.を再掲しておきます。
\(f\)と\(g\)は\(\mathbb{R}\)の開区間\((a,\infty)\)で定められていて、微分可能であり、以下の3条件を満たすとする。
- \(\displaystyle\lim_{x\to \infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}g(x)=0\)、
- \((\exists R\in(a,\infty))\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in (R,\infty))\ g(x)\neq 0\land g^\prime(x)\neq0\)、
- \(\displaystyle\lim_{x\to \infty}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A\)
証明に入ります。
定理5.の証明
一般性を失うことなく、\(a>0\)としてOKです。
なぜかというと、仮に\(a\leq 0\)だったとしても、\((a,\infty)\)の中には必ず正の実数が存在しています。
今、
$$
((\exists R\in(a,\infty))\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in (R,\infty))\ g(x)\neq 0\land g^\prime(x)\neq0)
$$
なわけですので、\(a\leq 0\)だったとしても、\(a<0<b\)という\(b\)に対しても、上記が成り立っています。
従って、\(a>0\)としてOKです。
余談(読み飛ばしてOK)
「一般性を失わない」という文言は数学の論証でたまに目にします。英語ではWithout loss of generalityやら、その頭文字をとってWLOGやらw.l.gやらと略記されたりもします。
筆者は最初にこの文言を見たときに、「なにいってっかわかんねぇ」と思いました。
「一般性ってなんだよ」ということです。
故に、あまり好きな言葉ではありません。
勿論、慣れてくれば段々と意味がわかるのですが。
例えば、こんな感じで使われます。
正直、筆者は好みません。
「全パターンやれよ」と思います。 というちょっとした愚痴でした。
ここで、\(\displaystyle t=\frac{1}{x}\)という変数変換を行います。
すなわち、
$$
F(t)=f\left( \frac{1}{t}\right)、\quad G(t)=g\left( \frac{1}{t}\right)
$$
という新たな関数\(F\)および\(G\)を考えます。
なぜこんな関数を考えるか、というと先程示した定理2.の\(a=0\)の場合を使いたいがためです。
こうすることで、\(\displaystyle t=\frac{1}{x}\)ですから、\(x\to\infty\)のとき\(t\to0\)で、定理2.が使えます。
このとき、\(F\)と\(G\)は\(\displaystyle\left(0,\frac{1}{a} \right)\)で定められた関数で、かつこの区間で微分可能です。
従って、
$$
F^\prime(t)=-\frac{1}{t^2}f^\prime\left( \frac{1}{t}\right)、\quad G^\prime(t)=-\frac{1}{t^2}g^\prime\left( \frac{1}{t}\right)
$$
です。
今、\(g^\prime(x)\neq 0\)であり、かつ\(x\neq 0\)ですので、\(G^\prime(x)\neq0\)です。
加えて、
$$
\lim_{x\to \infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}g(x)=0
$$
ですので、
- \(\displaystyle\lim_{t\to+0}F(t)=\lim_{x\to\infty}f\left( \frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to\infty}f(x)=0\)
- \(\displaystyle\lim_{t\to+0}G(t)=\lim_{x\to\infty}g\left( \frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to\infty}g(x)=0\)
です。
さらに、
$$
(\exists R\in(a,\infty))\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in (R,\infty))\ g(x)\neq 0\land g^\prime(x)\neq0
$$
という仮定から、
$$
(\exists R^\prime\in\left(0,\frac{1}{a}\right))\ {\rm s.t.}\ (\forall t\in (0,R^\prime))\ G(t)\neq 0\land G^\prime(t)\neq0
$$
です。
また、
$$
\lim_{t\to+0}\frac{F^\prime(t)}{G^\prime(t)}=\lim_{t\to+0}\frac{\displaystyle-\frac{1}{t^2}f^\prime\left( \frac{1}{t}\right)}{\displaystyle-\frac{1}{t^2}g^\prime\left( \frac{1}{t}\right)}=\lim_{t\to+0}\frac{\displaystyle f^\prime\left( \frac{1}{t}\right)}{\displaystyle g^\prime\left( \frac{1}{t}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}
$$
であり、
$$
\lim_{x\to\infty}\frac{f^\prime(x)}{g^\prime(x)}=A
$$
ですので、定理2.を使うと、
\begin{eqnarray}
\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}&=&\lim_{t\to+0}\frac{\displaystyle f^\prime\left( \frac{1}{t}\right)}{\displaystyle g^\prime\left( \frac{1}{t}\right)}\\
&=&\lim_{t\to+0}\frac{F(t)}{G(t)}\\
&=&\lim_{t\to+0}\frac{F^\prime(t)}{G^\prime(t)}=A
\end{eqnarray}
により、証明完了です。
例えばこんな使い方
例1.を思い出してみると、
例1.\(\displaystyle\lim_{x\to+0}\frac{e^x-1}{x^3}\)
でした。
今、\(e^x\)も\(x^3\)も\(x\neq0\)で何階でも微分可能です。
さらに、\(x\neq0\)で\(x\to+0\)なわけですので、このとき\(x^3\neq0\)かつ\(3x^2\neq 0\)です。
そこで、
$$
\lim_{x\to+0}\frac{e^x}{3x^2}
$$
を計算してみようとすると、また不定形です。
もう1回微分した極限を考えてみます。
$$
\lim_{x\to+0}\frac{e^x}{6x}
$$
また不定形です。
もう1回やってみます。
$$
\lim_{x\to+0}\frac{e^x}{6}=\infty
$$
求まりました。
従って、定理2.から、
$$
\infty=\lim_{x\to+0}\frac{e^x}{6}=\lim_{x\to+0}\frac{e^x}{3x^2}=\lim_{x\to+0}\frac{e^x-1}{x^3}
$$
となって求まりました。
結
今回はロピタルの定理を解説しました。
ロピタルの定理は解析学の基礎として知らなければならないことではないように思いますが(勿論、知ってたほうがいいわけですが)、コラム的に読んでいただければと思います。
とはいえ、不定形の関数の極限を知るにはかなり手っ取り早い方法だと思います。
これで、解析学は一旦区切りです。
次回から線型代数に入ります。
乞うご期待!質問、コメントなどお待ちしております!
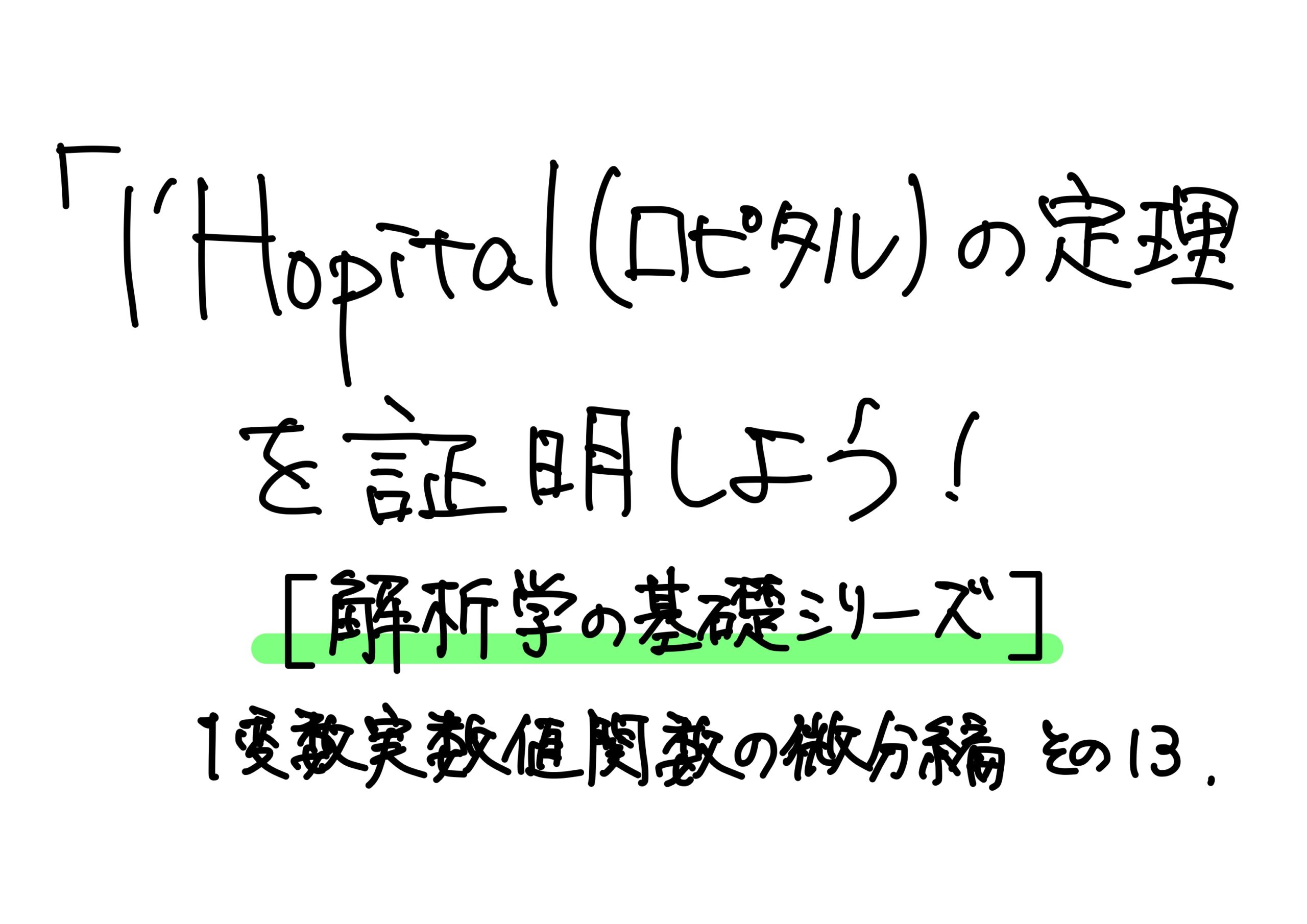
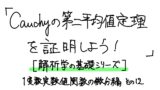
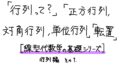
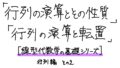
コメントをする