本記事の内容
本記事はテイラーの定理を証明する記事です。
「証明だけ知りたいんだけど?」という方はいざ、証明まで飛んでください。
本記事を読むにあたり、ロルの定理を知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。
テイラーの定理は強力です。
テイラーの定理は非常に強力です。
なぜかというと、
ということだからです。
例えば、\(\sin x\)やら\(\arccos x\)やら\(e^x\)やらという関数を始め、ガンマ関数やらといった複雑な関数ですら多項式で近似できます。
「\(\sin 1\)の値は?」と言われたとしましょう
我々は\(\sin 30^\circ\)やらの値は求めることができますが、\(\sin 1^\circ\)などの値は簡単には求められません。
そんなときにに、\(\sin x\)を多項式関数近似することによって\(\sin 1^\circ\)の近似値を導出することができるということにもなります。
さらに、テイラーの定理から導かれるテイラー展開という事実がありますが、これを使って微分方程式をコンピュータで解くという手法もあります。
テイラーの定理の明示と証明のの発想
テイラーの定理の明示
では、テイラーの定理を明示しましょう。
この定理を少々観察してみましょう。
テイラーの定理が成り立ったとして(まあ、成り立つんですけど(笑))、において、\(k=1\)としてみましょう。
すると
$$
f(x)=f(a)+\frac{f^\prime(c)}{1!}(x-a)
$$
という\(c\)が\(a\)と\(x\)の間に存在する、ということになります。
この式をより見やすい形に変形すると、
$$
f^\prime(c)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}
$$
という\(c\)が\(a\)と\(x\)の間に存在する、ということになります。
これはまさに平均値の定理です。
平均値の定理は何だったか、というと、次です。
平均値の定理の証明は【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の極限編 その8を御覧ください。
故に、
ということです。
一般化という言葉に馴染みがないかもしれませんので、言い換えると「平均値の定理はテイラーの定理に含まれている。」ということです。
テイラーの定理の証明の発想
先程、テイラーの定理は平均値の定理の一般化(平均値の定理はテイラーの定理に含まれている)ということを述べました。
ということは、テイラーの定理も平均値の定理の証明と同様にできるのではないか?ということになります。
では、平均値の定理はどのように証明したかというと、ロルの定理を用いて証明しました。
つまり、ロルの定理が使えるような関数を新たに定めてロルの定理を使って証明しました。
ロルの定理は何だったかというと、次でした。
(テイラーの定理の証明へジャンプ)
ロルの定理の証明は【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その7を御覧ください。
テイラーの定理は平均値の定理の一般化であり、平均値の定理はロルの定理を使って証明したので、テイラーの定理もロルの定理を使って証明できるのだろう、と思えるわけです。
さて、平均値の定理の場合は新たな関数\(g(x)\)を\(I=[a,b])\)に対して
$$
g(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)
$$
とすることによって、
- \(g:[a,b]\to\mathbb{R}\)は連続、
- \(g\)は\((a,b)\)で微分可能、
- \(g(a)=g(b)\)
を満たすため、\(g\)にロルの定理を適用させることで証明しました。
「テイラーの定理は平均値の定理の一般化なのであれば、平均値の定理と同様に\(g\)を定めればよいのだネ?」となるわけですが、同様にといっても一般化なので、全く同じというわけにはいきません。
とはいえ、発想は似たようなものです。
何を示したいか、というと、
$$
f(x)=f(a)+\frac{f^\prime(a)}{1!}(x-a)+\frac{f^{\prime\prime}(a)}{2!}(x-a)^2+\dots+\frac{f^{(k-1)}(a)}{(k-1)!}(x-a)^{k-1}+R_k
$$
と書いたときに、
$$
R_k=\frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-a)^k
$$
となるような\(c\)を見つけたいわけです。
この数式の中で、見つけたい\(c\)が入っているのは\(R_k\)の部分だけです。
さらに言えば、\(f^{(k)}(c)\)の部分だけです。
ということは、
$$
f(x)=\left[ \sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+\frac{(x-a)^k}{k!}\omega \right]
$$
となる\(\omega\)が\(f^{(k)}(c)\)と一致すれば良い、すなわち、一致するような\(c\)を見つけてきなさい、と言い換えることができます。
ここまでくれば、
$$
g(t)=-f(x)+\left[ \sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-t)^j+\frac{(x-t)^k}{k!}\omega \right]
$$
とおけば、いいんじゃないか、となるわけです。
しかしロルの定理を使うためにはまだ確認しなければいけないことがあります。
それは\(g(a)\)と\(g(x)\)が一致していることです。
ここがミソです。
\(g(a)\)と\(g(x)\)が一致するように\(\omega\)を決める、ということにします。
「決められるのかネ?」と思うかもしれませんが、決められます。
\(f\)が多項式のような関数であれば、そもそも形が同じなのだから係数を合わせるだけで済みます。
例えば、\(f(x)=\sin x\)であって、\(x\neq a=\pi\)で、\(k=2\)の場合を考えてみます。
※\(x\neq a\)とした理由はテイラーの定理の証明で解説します。
すると、
$$
\sin x=\sin \pi+(x-\pi)\cos\pi-\frac{\omega}{2}(x-\pi)^2
$$
となります。
このとき、
$$
g(t)=-\sin x+\sin t+(x-t)\cos t-\frac{\omega}{2}(x-t)^2
$$
とします。
このとき、\(g(\pi)=0\)という\(\omega\)は存在するのか、という話ですが、
\(t=\pi\)として方程式を解けばOKです。
ちなみに、
$$
\omega=\frac{-\sin x+\sin \pi+(x-\pi)\cos\pi}{x-\pi}
$$
というように求まります。
「\(x\)が入ってるけど?」と思うかもしれませんが、\(g\)は\(t\)を変数とする関数なので、\(t\)が入っていなければ、すなわち\(\omega\)が\(t\)で表現されていなければOKです。
従って、このような\(\omega\)は存在するわけですので、
$$
g(t)=-f(x)+\left[ \sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-t)^j+\frac{(x-t)^k}{k!}\omega \right]
$$
とすればよさそうだな、となります。
ちなみに、\(g\)は連続かつ微分可能です。
実際、多項式関数は連続かつ微分可能ですので、その和も連続かつ微分可能です。
(詳しくは【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その2および【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その5を御覧ください)
というわけで、\(g(t)\)を先のように定めればロルの定理も使えるということが分かりました。
では、証明しましょう!
いざ、証明
では、証明に入ります。
テイラーの定理を再掲しておきます。
テイラーの定理の証明
仮に、\(a=x\)だったとしたら、
- 左辺 $$f(x)=f(a)$$
- 右辺 \begin{eqnarray}&&f(a)+\frac{f^\prime(a)}{1!}(a-a)+\frac{f^{\prime\prime}(a)}{2!}(a-a)^2+\dots+\frac{f^{(k-1)}(a)}{(k-1)!}(a-a)^{k-1}\\ &=&f(a)+0+0+\dots +0=f(a) \end{eqnarray}
となるので、成り立ちます。
故に、以下は\(a\neq x\)の場合を考えます。
\(t\in I\)に対して、
$$
g(t)=-f(x)+\left[ \sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(t)}{j!}(x-t)^j+\frac{(x-t)^k}{k!}\omega \right]
$$
と置きます。
ただし、定数\(\omega\)は\(g(a)=0\)となるように、すなわち、
$$
f(x)=\sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+\frac{(x-a)^k}{k!}\omega
$$
となるように定めます。
\(g(t)\)において、\(t=x\)のとき、すなわち\(g(x)=0\)ですので、\(g(a)=g(x)\)です。
従って、ロルの定理を適用することができます(ロルの定理へ戻る)。
故に、ロルの定理から\(g^\prime(c)=0\)(ただし、\(c\)は\(a\)と\(x\)の間)を満たす\(c\)が存在します。
ここで、\(g\)の和の記号\(\Sigma\)を書き下してみると、
\begin{eqnarray}
g(t)&=&-f(x)+f^{(0)}(t)+f^\prime(t)(x-t)+\frac{f^{\prime\prime}(a)}{2!}(x-t)^2\\
&&+\dots+\frac{f^{(k-1)}(a)}{(k-1)!}(x-a)^{k-1}+\frac{(x-t)^k}{k!}\omega
\end{eqnarray}
です。
ただし、\(f^{(0)}(t)=f(t)\)です。
気合を入れて\(g^\prime(t)\)を計算すると、
\begin{eqnarray}
g^\prime(t)&=&0+\color{red}{f^{(1)}(t)}+\color{blue}{f^{(2)}(t)(x-t)}\color{red}{-f^{(1)}(t)}+\frac{f^{(3)}(t)}{2!}(x-t)^2\color{blue}{-\frac{f^{(2)}(t)}{2!}\cdot2\cdot(x-t)}\\
&&+\dots+\frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}-\frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!}\omega\\
&=&\frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}-\frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!}\omega\\
&=&\frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!}\left[f^{(k)}(t)-\omega\right]
\end{eqnarray}
ここで、\(g^\prime(c)=0\)だったことと、\(c\)は\(a\)と\(x\)の間にある(\(a<c<x\)または\(x<c<a\))を思い出せば、
$$
g^\prime(c)=\frac{(x-c)^{k-1}}{(k-1)!}\left[f^{(k)}(c)-\omega\right]=0
$$
であり、\(c\neq x\)ですので、\(f^{(k)}(c)-\omega=0\)、すなわち
$$
f^{(k)}(c)=\omega
$$
です。
さて、\(g(a)=0\)だったわけですので(\(g(a)=0\)となるように\(\omega\)を決めたので)、
$$
g(a)=-f(x)+\left[ \sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+\frac{(x-a)^k}{k!}\omega \right]=0
$$
です。
今、\(f^{(k)}(c)=\omega\)だとわかったので、
$$
-f(x)+\left[ \sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+\frac{(x-a)^k}{k!}f^{(k)}(c) \right]=0
$$
です。
従って、
$$
f(x)=\sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+\frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-a)^k
$$
となるため、ロルの定理で見つけてきた\(c\)を採用すれば良いことが分かります。
テイラーの定理の証明終わり
テイラー展開の導入
テイラーの定理の式に注目してみましょう。
$$
f(x)=\sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+R_k
$$
ただし、\(\displaystyle R_k=\frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-a)^k\)です。
※この\(R_k\)を\(k\)次剰余項と呼び、この形で表される剰余項をLagrange(ラグランジュ)剰余項
と呼びます。
もし仮に、\(f\)が何回でも微分可能であり(これを\(C^\infty\)級といいます)、さらに、\(a\)に十分近い\(x\)に対して\(\displaystyle\lim_{k\to\infty}R_k=0\)が成り立てば、両辺に\(k\)に対する極限をとることで、
\begin{eqnarray}
\lim_{k\to\infty}f(x)=f(x)&=&\lim_{k\to\infty}\left(\sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+R_k\right)\\
&=&\sum_{j=0}^{\infty}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+\lim_{k\to\infty}R_k\\
&=&\sum_{j=0}^{\infty}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j
\end{eqnarray}
が成り立ちます。
すなわち、\(a\)に十分近い\(x\)に対して、つまりは\(a\)とある距離よりも小さい\(x\)に対しては(これを収束半径内の\(x\)といいます)、\(f\)は多項式の級数で書き換えることができる、ということになります。
この収束半径というのは関数\(f\)によって異なります。
この
$$
f(x)=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j
$$
を\(f\)の\(a\)を中心とするテイラー展開といいます。
特に、\(a=0\)の場合、すなわち、
$$
f(x)=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{f^{(j)}(0)}{j!}x^j
$$
をマクローリン(マクローリン)展開と言います。
代表的なテイラー展開の例は次回解説します。
結
今回はテイラーの定理をロルの定理から導出しました。
証明の流れとしては平均値の定理の証明とにたようなものですが、ロルの定理を適用させるための新たな関数の定め方がテクニカルでした。
さらに、テイラーの定理は平均値の定理の一般化になっているのでした。
加えて、\(f\)が\(C^\infty\)級(何回でも微分可能)で、Lagrange剰余項\(R_k\)が\(k\to\infty\)で\(0\)に収束する場合は\(f\)は多項式の級数で書き直すことができるため、多項式の級数で書き直した関数をテイラー展開と呼びます。
次回はテイラー展開の代表例を解説します。
乞うご期待!質問、コメントなどお待ちしております!
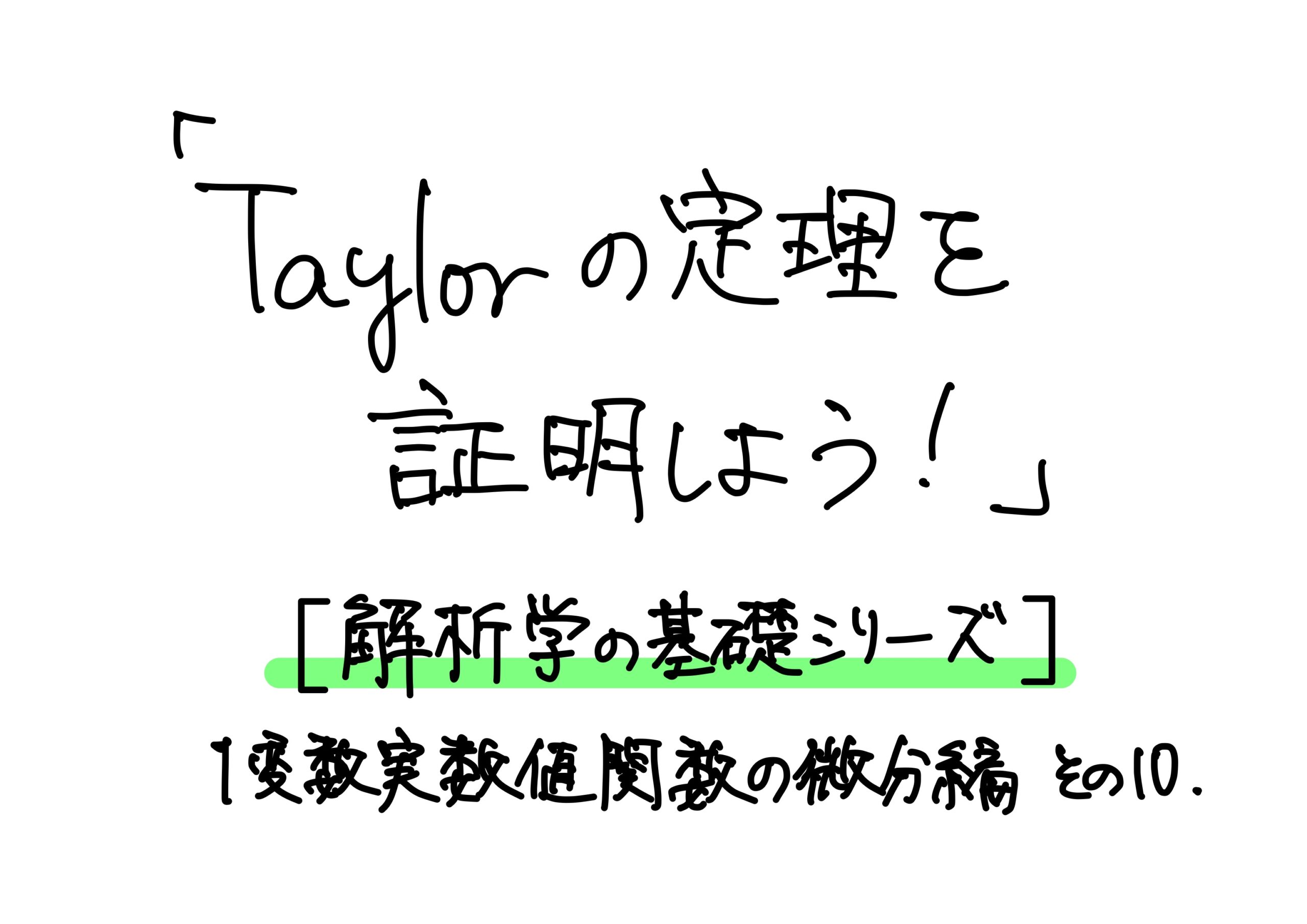
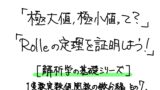
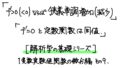
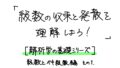
コメントをする
素晴らしい解説をありがとうございます。