本記事の内容
本記事は「交代群\(A_n\)は\(n\geq5\)で単純群である」ということを証明するための準備をする記事です。
本記事を読むに当たり、交代群、単純群、巡回置換について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。
↓交代群の記事
↓単純群の記事
この記事を読む前に…
本記事では単純群やら交代群やらの概念が出現しますが、それらの復習はあとで行います。
今回と次回で証明すること
今回と次回で証明することとその意味を述べます。
主張の明示
定理0.
交代群\(A_n\)は\(n\geq5\)ならば、単純群である。系0.
\(n\geq5\)ならば、対称群\(\mathcal{G}_n\)は可解群でない。証明する主張自体は誠にシンプルです。
系0.は定理0.から導かれます。
何を意味するか?
以前の記事で、群は方程式論と深いつながりがある、ということを述べました。
「5次以上の方程式は解の公式が存在しない」ということを証明するときに出現するのが系0.です。
少し具体的に述べれば、ガロア群と呼ばれる群が\(5\)次以上では可解群でないということを示すときに使います。
要するに、「5次以上の方程式は解の公式が存在しない」という主張を証明するための布石といったところです。
ガロア理論は群論編が一段落したあとに解説します(少々時間が空いてしまうと思いますが…)。
サラッと復習
可解群、ベキ零群
可解群、ベキ零群
\(G\)を群とする。- 可解群 \(G\)の部分群の列\(G=G_0\supset G_1\supset \cdots\supset G_n=\left\{1_G\right\}\)が存在し、\(i=0,\dots,n-1\)に対して、\(G_{i+1}\triangleleft G_i\)で\(G_i/{G_{i+1}}\)が可換群であるとき、\(G\)を可解群という。
- ベキ零群 \(G=G_0\supset G_1\supset \cdots\supset G_n=\left\{1_G\right\}\) \(G\)の部分群の列\(G=G_0\supset G_1\supset \cdots\supset G_n=\left\{1_G\right\}\)が存在し、\(i=0,\dots,n-1\)に対して、\(G_{i+1}\triangleleft G_i\)で\(G_i/{G_{i+1}}\)が\(G/{G_{i+1}}\)の中心に含まれるとき、\(G\)をベキ零群という。
単純群
単純群
群\(G\)が可換群でなく、自明でない正規部分群を持たないならば、\(G\)を単純群という。命題1.
群\(G\)が単純群ならば、可解群ではない。命題1.の証明は【代数学の基礎シリーズ】群論編 その23を御覧ください。
巡回置換
巡回置換
\(m,n\in\mathbb{N}\)が\(m<n\)を満たし、\(M_n=\{1,2,\dots,m,\dots,n\}\)とする。また、 $$ \sigma= \begin{pmatrix} 1&2&\cdots&m&m+1&\cdots&n \\ i_1&i_2&\cdots&i_m&i_{m+1}&\cdots&i_n\\ \end{pmatrix} $$ とする。このとき、置換\(\sigma\)が\(M_n\)の要素のうち、\(i_1,i_2,\dots,i_m\)以外は動かさず\(i_1,i_2,\dots,i_m\)のみを $$ i_1\mapsto i_2,\ i_2\mapsto i_3,\cdots,i_m\mapsto i_1 $$ のように一巡させる置換であるとき、すなわち $$ \sigma= \begin{pmatrix} i_1&i_2&\cdots&i_m&i_{m+1}&\cdots&i_n \\ i_2&i_3&\cdots&i_1&i_{m+1}&\cdots&i_n\\ \end{pmatrix} $$ を巡回置換といい、 $$ \sigma=(i_1\ i_2\ \cdots\ i_m) $$ で表す。共役
共役、共役類
群\(G\)の要素\(x,y\)に対して、ある\(g\in G\)が存在して、\(y=gxg^{-1}\)となるとき、\(x\)と\(y\)は共役であるという。\(x\)と共役である要素の集合を\(x\)の共役類といい、\(C(x)\)と書く。定理0.を証明するための補題
今回は、定理0.を証明するための補題を2つ証明します。
補題2.
\(n\geq3\)ならば、交代群\(A_n\)は長さ\(3\)の巡回置換で生成される。補題2.の証明
任意の置換は互換の積で書くことができます(【線型代数学の基礎シリーズ】行列式編 その1を参照)。
互換の符号は\(-1\)なので、\(A_n\)の要素は偶数個の互換の積です。
逆に、偶数個の互換の積は\(A_n\)の要素です。
ぐすうこの互換の積は\((i\ j)(k\ l)\)という形の要素の有限個の積です。
故に、このような要素が長さ3の巡回置換の有限個の積でであることを示せばOKです。
\(i=k\)、\(j\neq l\)ならば、\((i\ j)(k\ l)=(i\ j\ l)\)です。
\(i=k\)、\(j=l\)であれば、\((i\ j)(k\ l)=1\)です。
\(\left\{i,j\right\}\cap\left\{k,l\right\}=\emptyset\)ならば、\((i\ j)(k\ l)=(i\ j\ k)(j\ k\ l)\)です。
補題2.の証明終わり
補題3.
\(n\geq5\)ならば、長さ3の巡回置換は全て\(A_n\)で共役である。補題3.の証明
\(\sigma=(i\ j\ k)\)、\(\tau=(r\ s\ t)\)を2つの長さ3の巡回置換とします。
このとき、以下の事実を使います。
定理4.
\(\sigma,\tau\in\mathcal{G}_n\)であるとき、\(\sigma,\tau\)が共役であることと、\(\sigma,\tau\)の型が等しいことは同値である。定理4.の証明は【代数学の基礎シリーズ】群論編 その19を御覧ください。
定理4.から、\(\nu\sigma\nu^{-1}=\tau\)となるような\(\nu\in\mathcal{G}_n\)が存在します。
もし、\(\nu\in A_n\)であれば、証明は完了です。
\(\nu\not\in A_n\)ならば、\(\nu\)は奇置換です。
\(n\geq5\)なので、\(i,j,k\)とは異なる\(l,m\leq n\)が存在します。
\(\lambda=(l\ m)\)とすれば、\(\lambda\)は互換なので、奇置換であり、\(\lambda\sigma\lambda^{-1}=\sigma\)です。
故に、\(\nu\lambda\sigma\lambda^{-1}\nu^{-1}=\tau\)となりますが、\(\nu\)も\(\lambda\)も両方とも奇置換なので、\(\nu\lambda\in A_n\)です。
補題3.の証明終わり
皆様のコメントを下さい!
前回の続きで極限の論法、特に微積分学の歴史について少々語ります。
17世紀の終わり近くにニュートンとライプニッツにより独立に切り開かれました。
彼らは、独立に無限小解析(微分積分学)を創造し、一般的な方法により接線の問題(微分学)と求積(quadrature)の問題(積分学)を扱うことに成功したのです。
今回も\(\varepsilon-\delta\)論法以前の極限についてお話します。
当時の数学者が「収束」の厳密な定式化の必要性に思い至らなかった理由は、彼らが扱っていた関数は何らかの「解析的式」で与えられており、前回述べた
という議論が適用できるものだったからです。
しかし、もし望む形に
$$
\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\tag{\ast}
$$
を変形できないときはどうすればよいのでしょうか?
19世紀になるまでこの問いに対する満足すべき答えは与えられなかった数学者がこの問題に立ち向かい、ユードクソスの定式化を再発見したのは、関数の一般的概念が広く受け入れられてから後のことでした。
数学者でさえ「極限概念」の完全な理解には時間を要したのだから、非数学者がそれを理解するのに直面した困難を想像するのは難くありません。
例えば、1870年代に書かれたエンゲルスによる手稿には、微分を理解しようとする涙ぐましい努力と、見当違いな解釈を見出すことができます。
ユードクソスの観点を再発見したのはダランベールが最初と考えられます。
彼は
「無限とは有限なものが限りなく近づくが、決して到達しない1つの極限に過ぎない。例えば\(1+2+4+8+\cdots\)が無限大ということは、項の数を十分にたくさん取って加えると、その結果が任意に与えられた数よりも大きくなることを意味する。」
と言っています。
無限小と無限大の違いはありますが、このような考え方はユードクソスによる無限小の定式化と同じ思想圏に属することは明らかでしょう。
現代で広く知られる\(\varepsilon-\delta\)論法を(不完全ながらも)最初に「開発」したのはコーシーであす(1821年『解析学教程』)。
その後、ワイエルシュトラスによりさらに厳密化されました(1860 年代)。
結
今回は、交代群に焦点を当て、「交代群は次数が5以上であれば単純群である」ことを証明するための準備をしました。
この事実から「対称群は5次以上で可解群でない」ということを証明し、これが「5次以上の方程式は解の公式が存在しない」ということを証明するときに出現します。
次回は「交代群は次数が5以上であれば単純群である」ことと「対称群は5次以上で可解群でない」を証明します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。
もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。
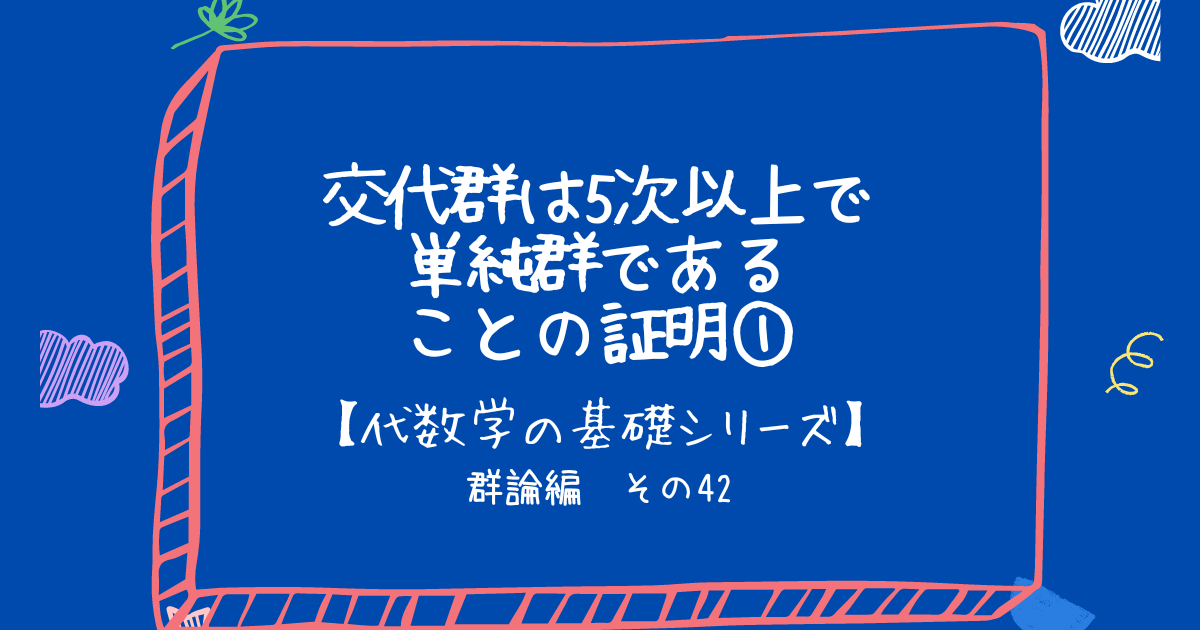




コメントをする
定理4の最後の方、νλσλ^(-1)=τとなってますが、
νλσλ^(-1)ν^(-1)=τの誤植ではないですか?
名無し様
コメントありがとうございます。
>定理4の最後の方、νλσλ^(-1)=τとなってますが、νλσλ^(-1)ν^(-1)=τの誤植ではないですか?
とのお問い合わせですが、おっしゃる通り、誤植でございました。
修正いたしました。ご指摘ありがとうございました。