本記事の内容
本記事は有限アーベル群の基本定理の証明を順を追って解説する記事です。
本記事を読むに当たり、アーベル群、位数、同型、中国式剰余定理について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。
↓アーベル群の記事
↓位数の記事
↓同型の記事
↓中国式剰余定理の記事
数回に渡ってやること
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その36から数回に渡って何をするかというと、結論としては、以下の定理を証明します。
定理0.(有限アーベル群の基本定理)
\(G\)が有限なアーベル群ならば、整数\(e_1,\dots,e_n\geq2\)が存在して、\(i=1,\dots,n-1\)に対して\(e_i|e_{i+1}\)を満たし、 $$ G\cong \mathbb{Z}/{e_1\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{e_n\mathbb{Z}} $$ となる。また、この条件を満たす\(e_1,\dots,e_n\)は一意的に定まる。ただし、\(n=0\)のときは\(G\cong\left\{0\right\}\)と解釈する。有限アーベル群の基本定理は何を言っているのか?
要するに、有限アーベル群の基本定理は何を言っているのか、というと
ということです。
もっと平たく言えば、「有限なアーベル群は”いい具合に”商群の直積に分解することができる」ということです。
証明の流れ
主張を言い換えてみます。
\(e\geq2\)を整数とすれば、相異なる素数\(p_1,\dots,p_t\)により\(e=p_1^{a_1}\cdots p_t^{a_t}\)と素因数分解できます。
ここで、中国式剰余定理を使います。
定理1.(中国式剰余定理)
\(m,n\neq 0\)が互いに素な整数ならば、 $$ \mathbb{Z}/{mn\mathbb{Z}}\cong \mathbb{Z}/{m\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{n\mathbb{Z}} $$ である。定理1.(中国式剰余定理)の証明は【代数学の基礎シリーズ】群論編 その28を御覧ください。
中国式剰余定理を使うことで、
$$
\mathbb{Z}/{e\mathbb{Z}}\cong\mathbb{Z}/{p_1^{a_1}\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{p_t^{a_t}\mathbb{Z}}
$$
です。
したがって、有限アーベル群の基本定理の\(G\)は位数が素数べきの巡回群の積で表されることになります。
そこで、有限アーベル群の基本定理の代わりに、次の定理を証明することにします。
その証明の跡で、有限アーベル群の基本定理が以下の定理から従うことを示します。
定理00.(有限アーベル群の基本定理2)
\(G\)を有限なアーベル群とするとき、次の1.、2.が成り立つ。- 素数\(p_1,\cdots,p_t\)(重複を許す)と正の整数\(a_1,\cdots,a_t\)が存在して $$ \mathbb{Z}/{e\mathbb{Z}}\cong\mathbb{Z}/{p_1^{a_1}\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{p_t^{a_t}\mathbb{Z}} $$ となる。また、\(p_1^{a_1},\cdots,p_t^{a_t}\)は順序を除いて一意的に定まる。
- 素数\(p\)に対して、\(G(p)\)を\(p_i=p\)である\(i\)全てに属する\(\mathbb{Z}/{p_i^{a_i}\mathbb{Z}}\)の直積とすると、\(G\)は全ての\(G(p)\)の直積であり、\(G(p)\)は\(G\)のシロー\(p\)部分群である。
定理00.(有限アーベル群の基本定理2)の証明の流れ
- 同型写像の存在
- \(\left|G\right|\)が\(p\)ベキであることの証明→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その36で証明済み
- \(G\)が巡回群の直積となることの証明→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その37で証明済み
- 同型写像を作る。→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その39で証明済み
- 存在する整数の一意性
- 上の分解が直積因子の順序を除き一意的であることの証明→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その39で証明済み
- 一般の場合の直積因子の一意性の証明→今回
今回は2.-2.を示します。
前回までの証明(ざっくり)
\(G\)の演算は加法的に\(+\)と書き、単位元も\(0\)と書くことにします。
証明(Part.1)
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その36では
$$
H=\left\{x\in G\middle| p^a=0\right\},\quad K=\left\{x\in G\middle|mx=0\right\}
$$
として、\(\left|H\right|\)が\(p\)ベキであることを示し、\(K\)は位数が素数ベキの群の直積となることを証明しました。
証明(Part.2)
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その37では\(G\)が巡回群の直積になることを証明しました。
また、\(G/{H}\)は有限アーベル群で、\(\left|G/{H}\right|<\left|G\right|\)なので、帰納法で正の整数\(a_1,\dots,a_t\)が存在して、
$$
G/{H}\cong K_1\times K_t,\quad K_1\cong\mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}},\cdots,K_t\cong\mathbb{Z}/{p^{a^t}\mathbb{Z}}
$$
となるのでした。
\(K_i\)の生成元(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その2)を\(k_i\)、\(\pi:G\longrightarrow G/{H}\)を自然な準同型(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その4)とするとき、\(\pi(g_i)=k_i\)となる要素\(g_i\in G\)を取ります。
このとき\(g_i\)の位数が\(p^{a_i}\)であるように\(g_i\)を取ることができることを示しました。
証明(Part.3)
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その38では、\(F_i=\left\langle g_i\right\rangle\)、\(F=F_1\times \cdots\times F_t\)としたとき、\(\varphi:F\longrightarrow G\)を
$$
\varphi\left( c_1,\dots,c_t\right)=c_1+\cdots+c_t\quad (c_i\in F_i)
$$
と定めると、\(\varphi\)は準同型写像です。
\(\pi:G\longrightarrow G/{H}\)を自然な準同型(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その4)とするとき、\(\pi\circ \varphi\)は同型写像なので、\(\varphi\)は単射です。
\(L=\varphi(F)\subset G\)とおくと、\(L\)は\(G\)の部分群で\(F\)と同型です。
また、\(\pi\)を\(L\)に制限すれば、\(G/{H}\)への同型写像となります。
\({\rm Ker}(\pi)=H\)なので、\(H\cap L=\left\{0\right\}\)です。
\(\left|H\times L\right|=\left|G\right|\)なので、
$$
G\cong H\times L\cong\mathbb{Z}/{p^c\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{p^{a_t}\mathbb{Z}}
$$
となり、定理00.の同型写像の存在が分かりました。
証明(Part.4)
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その39では、前回まで考察した分解が直積因子の順序をのぞき、一意的であることを、\(G\)が\(p\)群(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その24)の場合に証明しました。
直積因子の順序を変えて
$$
G=\left( \mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}}\right)^{b_1}\times\cdots\times\left( \mathbb{Z}/{p^{a_t}\mathbb{Z}}\right)^{b_t},\quad a_1<a_2<\cdots<a_t
$$
としてOKでした(\(a_i\)は以前のPartの\(a_i\)とは異なります)。
\(p^{a_t}\)は\(G\)により定まる数です。
\(H\)を\(G\)の要素で位数が\(p^{a_t}\)より小さいもの全体の集合とします。
すると、\(H\)は\(G\)により定まる部分群です。
\begin{eqnarray}
H&=&\left( \mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}}\right)^{b_1}\times\cdots\times\left( \mathbb{Z}/{p^{a_{t-1}}\mathbb{Z}}\right)^{b_{t-1}}\times\left( \mathbb{Z}/{p^{a_t}\mathbb{Z}}\right)^{b_t}\\
&\cong&\left( \mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}}\right)^{b_1}\times\cdots\times\left( \mathbb{Z}/{p^{a_{t-1}}\mathbb{Z}}\right)^{b_{t-1}}
\end{eqnarray}
となり、\(H\)の分解の一意性から、\(a_{t-1}<a_t-1\)なら\(a_1,\dots,a_{t-1},b_1,\dots,b_{t-1}\)が定まり、\(a_{t-1}=a_t-1\)なら、\(a_1,\dots,a_{t-2},b_1,\dots,b_{t-2}\)と\(a_{t-1}=a_t-1\)、\(b_{t-1}+b_t\)が定まります。
\(a_t\)と\(b_t\)は定まっているので、\(a_{t-1}\)、\(b_{t-1}\)も定まります。
これで\(G\)が\(p\)群の場合の直積因子の一意性が分かりました。
いざ、証明(Part.5)
一般の直積因子の一意性を考えます。
\(p\)を素数とします。
\(G\)を定理00.の主張の形の直積に分解したとき、\(p_i=p\)であるような全ての\(i\)に関して\(\mathbb{Z}/{p_i^{a_i}\mathbb{Z}}\)の直積を取ったものである\(G(p)\)は、\(G\)のシロー\(p\)部分群(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その27)です。
\(G\)はアーベル群(可換群)でシロー\(p\)部分群は全て共役(シローの定理)なので、シロー\(p\)部分群は一意的に定まります。
\(G(p)\)は\(p\)群(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その24)なので、その直積因子は一意的に定まります。
故に、\(p_i=p\)となるような\(p_i\)のベキ\(a_i\)の集合は\(G\)により定まります。
これで、定理00.の証明はおしまいです。
皆様のコメントを下さい!
前回から極限の論法、特に微積分学の歴史について少々語ります。
17世紀の終わり近くにニュートンとライプニッツにより独立に切り開かれました。
彼らは、独立に無限小解析(微分積分学)を創造し、一般的な方法により接線の問題(微分学)と求積(quadrature)の問題(積分学)を扱うことに成功したのです。
今回はニュートンの方法とライプニッツの方法について少々語ります。
ニュートンの方法「流率法」
ニュートンの方法は「流率法」と呼ばれています。
「流量」は時間とともに変化する量、「流率」とは流量の速さのことであり、「流量」から「流率」を求める問題と、逆に「流率」から「流量」を求める問題が中心となります。
現代的観点から言えば、「微分方程式(differential equation)をたてる」こと、及び「微分方程式を解く」ことに対応します。
このためニュートンは冪級数(power series)を巧みに扱いました。
この研究は1671年に既に行われていましたが、ニュートンの秘密主義のため公になったのはずっと後のことです(1736年)。
ニュートンはさらに力学の問題を無限小解析と関連させ、ケプラーの法則から万有引力の法則を導き出すとともに、その逆が成り立つことも示しましたが、このことが書かれている『プリンキピア』には流率法の着想は表に現れていません。
ライプニッツの方法
一方、ライプニッツは1673年から1676年にかけてハノーバー王室の外交の仕事でパリに滞在中、微分積分学を一部に含む数学理論をほぼ完成させています。
ライプニッツの問題意識も接線問題(微分)と逆接線問題(微分方程式の解法)を目指すものでした。
この期間、ホイヘンスと書簡を交わしたことと、デカルトの『幾何学』などを徹底的に学習したことが大きな力になりました。
ハノーバーに戻る時期の前後は、表現方法の改良に努めて、いわいる“calculus”の構築に精力を注ぎ、これが完成して印刷公表されたのは1684年および1686年です。
微分積分学の誕生に、彼らがほぼ同時期に関わっていたこともあって、ニュートンとライプニッツの間では彼らの弟子も巻き込んで熾烈な先発権論争が起こりました。
しかし、時期の後先はあるものの、二人が独立に微分積分学を発見したことは確かです。
その後、無限小解析はオイラーにより現在ある形に整理され、様々な問題(特に物理学)に応用されるようになりました。
さらに19世紀には、無限小解析の基礎的部分に注意が注がれるようになり、解析学の磐石な基礎が確立されたのです。
ブルバキも言うように、無限小解析は比類のない「道具」であって、ニュートン、ライプニッツの時代から3世紀以上に渡って使われ続けており、その切れ味はまだ完全には鈍っていません。
如何でしたか?
感想など是非コメントで教えて下さい!
結
今回は、有限アーベル群の基本定理の証明の一部を解説しました。
有限アーベル群の基本定理は、「任意の有限アーベル群が巡回群の直積に同型である」という主張の定理です。
今回は、考察している分解が一般の直積因子で一意的であることを証明しました。
次回はいよいよ有限アーベル群の基本定理を証明します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ一週間以内にお答えします。
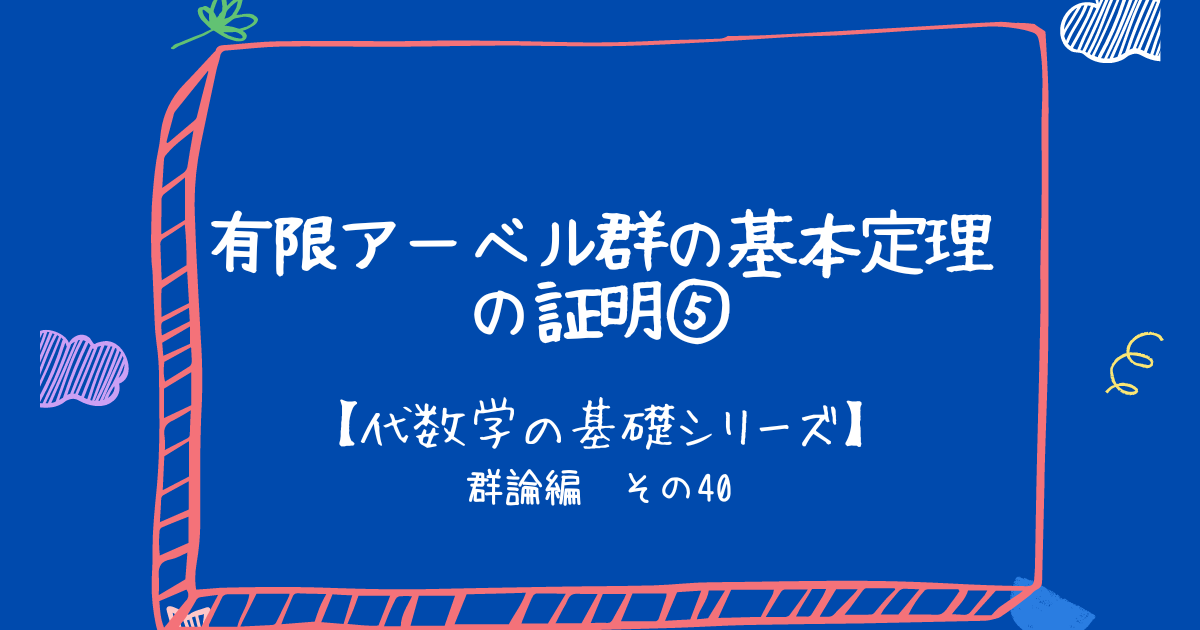

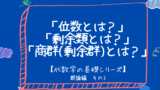
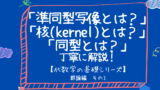
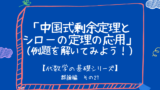


コメントをする