本記事の内容
本記事は有限アーベル群の基本定理の証明を順を追って解説する記事です。
本記事を読むに当たり、アーベル群、位数、同型、中国式剰余定理について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。
↓アーベル群の記事
↓位数の記事
↓同型の記事
↓中国式剰余定理の記事
数回に渡ってやること
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その36から数回に渡って何をするかというと、結論としては、以下の定理を証明します。
定理0.(有限アーベル群の基本定理)
\(G\)が有限なアーベル群ならば、整数\(e_1,\dots,e_n\geq2\)が存在して、\(i=1,\dots,n-1\)に対して\(e_i|e_{i+1}\)を満たし、 $$ G\cong \mathbb{Z}/{e_1\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{e_n\mathbb{Z}} $$ となる。また、この条件を満たす\(e_1,\dots,e_n\)は一意的に定まる。ただし、\(n=0\)のときは\(G\cong\left\{0\right\}\)と解釈する。有限アーベル群の基本定理は何を言っているのか?
要するに、有限アーベル群の基本定理は何を言っているのか、というと
ということです。
もっと平たく言えば、「有限なアーベル群は”いい具合に”商群の直積に分解することができる」ということです。
証明の流れ
主張を言い換えてみます。
\(e\geq2\)を整数とすれば、相異なる素数\(p_1,\dots,p_t\)により\(e=p_1^{a_1}\cdots p_t^{a_t}\)と素因数分解できます。
ここで、中国式剰余定理を使います。
定理1.(中国式剰余定理)
\(m,n\neq 0\)が互いに素な整数ならば、 $$ \mathbb{Z}/{mn\mathbb{Z}}\cong \mathbb{Z}/{m\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{n\mathbb{Z}} $$ である。定理1.(中国式剰余定理)の証明は【代数学の基礎シリーズ】群論編 その28を御覧ください。
中国式剰余定理を使うことで、
$$
\mathbb{Z}/{e\mathbb{Z}}\cong\mathbb{Z}/{p_1^{a_1}\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{p_t^{a_t}\mathbb{Z}}
$$
です。
したがって、有限アーベル群の基本定理の\(G\)は位数が素数べきの巡回群の積で表されることになります。
そこで、有限アーベル群の基本定理の代わりに、次の定理を証明することにします。
その証明の跡で、有限アーベル群の基本定理が以下の定理から従うことを示します。
定理00.(有限アーベル群の基本定理2)
\(G\)を有限なアーベル群とするとき、次の1.、2.が成り立つ。- 素数\(p_1,\cdots,p_t\)(重複を許す)と正の整数\(a_1,\cdots,a_t\)が存在して $$ \mathbb{Z}/{e\mathbb{Z}}\cong\mathbb{Z}/{p_1^{a_1}\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{p_t^{a_t}\mathbb{Z}} $$ となる。また、\(p_1^{a_1},\cdots,p_t^{a_t}\)は順序を除いて一意的に定まる。
- 素数\(p\)に対して、\(G(p)\)を\(p_i=p\)である\(i\)全てに属する\(\mathbb{Z}/{p_i^{a_i}\mathbb{Z}}\)の直積とすると、\(G\)は全ての\(G(p)\)の直積であり、\(G(p)\)は\(G\)のシロー\(p\)部分群である。
定理00.(有限アーベル群の基本定理2)の証明の流れ
- 同型写像の存在
- \(\left|G\right|\)が\(p\)ベキであることの証明→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その36で証明済み
- \(G\)が巡回群の直積となることの証明→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その37で証明済み
- 同型写像を作る。→【代数学の基礎シリーズ】群論編 その39で証明済み
- 存在する整数の一意性
- 上の分解が直積因子の順序を除き一意的であることの証明→今回
- 一般の場合の直積因子の一意性の証明
今回は2.-1.を示します。
前回までの証明
\(G\)の演算は加法的に\(+\)と書き、単位元も\(0\)と書くことにします。
証明(Part.1)
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その36では
$$
H=\left\{x\in G\middle| p^a=0\right\},\quad K=\left\{x\in G\middle|mx=0\right\}
$$
として、\(\left|H\right|\)が\(p\)ベキであることを示し、\(K\)は位数が素数ベキの群の直積となることを証明しました。
証明(Part.2)
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その37では\(G\)が巡回群の直積になることを証明しました。
また、\(G/{H}\)は有限アーベル群で、\(\left|G/{H}\right|<\left|G\right|\)なので、帰納法で正の整数\(a_1,\dots,a_t\)が存在して、
$$
G/{H}\cong K_1\times K_t,\quad K_1\cong\mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}},\cdots,K_t\cong\mathbb{Z}/{p^{a^t}\mathbb{Z}}
$$
となるのでした。
\(K_i\)の生成元(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その2)を\(k_i\)、\(\pi:G\longrightarrow G/{H}\)を自然な準同型(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その4)とするとき、\(\pi(g_i)=k_i\)となる要素\(g_i\in G\)を取ります。
このとき\(g_i\)の位数が\(p^{a_i}\)であるように\(g_i\)を取ることができることを示しました。
証明(Part.3)
【代数学の基礎シリーズ】群論編 その38では、\(F_i=\left\langle g_i\right\rangle\)、\(F=F_1\times \cdots\times F_t\)としたとき、\(\varphi:F\longrightarrow G\)を
$$
\varphi\left( c_1,\dots,c_t\right)=c_1+\cdots+c_t\quad (c_i\in F_i)
$$
と定めると、\(\varphi\)は準同型写像です。
\(\pi:G\longrightarrow G/{H}\)を自然な準同型(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その4)とするとき、\(\pi\circ \varphi\)は同型写像なので、\(\varphi\)は単射です。
\(L=\varphi(F)\subset G\)とおくと、\(L\)は\(G\)の部分群で\(F\)と同型です。
また、\(\pi\)を\(L\)に制限すれば、\(G/{H}\)への同型写像となります。
\({\rm Ker}(\pi)=H\)なので、\(H\cap L=\left\{0\right\}\)です。
\(\left|H\times L\right|=\left|G\right|\)なので、
$$
G\cong H\times L\cong\mathbb{Z}/{p^c\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{p^{a_t}\mathbb{Z}}
$$
となり、定理00.の同型写像の存在が分かりました。
いざ、証明(Part.4)
前回まで考察した分解が直積因子の順序をのぞき、一意的であることを、\(G\)が\(p\)群(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その24)の場合に証明します。
直積因子の順序を変えて、
$$
G=\left( \mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}}\right)^{b_1}\times\cdots\times\left( \mathbb{Z}/{p^{a_t}\mathbb{Z}}\right)^{b_t},\quad a_1<a_2<\cdots<a_t
$$
としてOKです(\(a_i\)は以前のPartの\(a_i\)とは異なります)。
ここで、\(\left( \mathbb{Z}/{p^{a_i}\mathbb{Z}}\right)^{b_i}\)は\(\mathbb{Z}/{p^{a_i}\mathbb{Z}}\)の\(b_i\)個の直積です。
\(p^{a_t}\)は\(G\)の要素の位数の最大値なので、先の分解によらずに、\(G\)により定まる数です。
\(H\)を\(G\)の要素で位数が\(p^{a_t}\)より小さいもの全体の集合とします。
すると、\(H\)も先の分解に依存せず、\(G\)により定まる部分群です。
\(g_i\in\left( \mathbb{Z}/{p^{a_i}\mathbb{Z}}\right)^{b_i}\)、\(g=\left( g_1,\cdots,g_t\right)\in G\)とおきます。
\(g_1,\cdots,t_{t-1}\)の位数が\(p^{a_t}\)より小さいので、\(g\in H\)であることと、\(g_t\)の位数が\(p^{a_t}\)より小さいことは同値です。
\(c_1\dots,c_{b_t}\in\mathbb{Z}\)で、\(bar{c}_1,\dots,\bar{c}_{b_t}\in \left( \mathbb{Z}/{p^{a_i}\mathbb{Z}}\right)^{b_i}\)をその剰余類とするとき、\(\left(bar{c}_1,\dots,\bar{c}_{b_t} \right)\)の位数が\(p^{a_t}\)より小さいことと、\(c_1,\dots,c_{b_t}\)が\(p\)の倍数によれることは同値です。
故に、
\begin{eqnarray}
H&=&\left( \mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}}\right)^{b_1}\times\cdots\times\left( \mathbb{Z}/{p^{a_{t-1}}\mathbb{Z}}\right)^{b_{t-1}}\times\left(p \mathbb{Z}/{p^{a_t}\mathbb{Z}}\right)^{b_t}\\
&\cong&\left( \mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}}\right)^{b_1}\times\cdots\times\left( \mathbb{Z}/{p^{a_{t-1}}\mathbb{Z}}\right)^{b_{t-1}}\times\left( \mathbb{Z}/{p^{a_t-1}\mathbb{Z}}\right)^{b_t}
\end{eqnarray}
となります。
\(G/{H}\cong\left( \mathbb{Z}/{p\mathbb{Z}}\right)^{b_t}\)なので、\(b_t\)は\(G\)により定まります。
\(\left|H\right|<\left|G\right|\)なので、\(H\)の巡回群の直積としての表し方は直積因子の順序を除いて定まります。
\(a_t\)はすでに定まっていますので、\(\mathbb{Z}/{p^{a_t-1}\mathbb{Z}}\)が直積因子として何回現れるかにより\(a_{t-1}=a_t-1\)かどうかが分かります。
\(H\)の分解の一意性から、\(a_{t-1}<a_t-1\)なら\(a_1,\dots,a_{t-1},b_1,\dots,b_{t-1}\)が定まり、\(a_{t-1}=a_t-1\)なら、\(a_1,\dots,a_{t-2},b_1,\dots,b_{t-2}\)と\(a_{t-1}=a_t-1\)、\(b_{t-1}+b_t\)が定まります。
\(a_t\)と\(b_t\)は定まっているので、\(a_{t-1}\)、\(b_{t-1}\)も定まります。
これで\(G\)が\(p\)群の場合の直積因子の一意性が分かりました。
皆様のコメントを下さい!
今回から数回に渡って、極限の論法、特に微積分学の歴史について少々語ろうと思います。
無限小解析(infinitesimal calculus)\(=\)微分積分学((differential and integral) calculus)です。
ニュートンとライプニッツが創始し、オイラー、コーシーらにより整理されました。
その萌芽はユードクソス、アルキメデスの「積尽法」に見られます。
これは長さや面積・体積などの「量」が\(0\)に「近づく」という語義を厳密に扱う論法でした。
しかし古代の幾何学では「量」の演算に対する制限が強く、しかも背理法との技巧的な組み合わせに依存することもあって、取り扱える図形は極めて特殊なものでした。
この制限はデカルトにより取り払われ、数学者は一般の曲線や曲面を扱うことが可能になったのです。
当時の主な関心は、曲線の接線(tangential line)と面積を求めることであり、これはアルキメデスの問題意識を継承しています。
例えば、ケプラーは円錐曲線を回転して得られる回転体の体積を求め、イタリアのカヴァリエリ(Cavalieri, Bonaventura Francesco;1598-1647)は彼の「不可分の原理」を用いて一般の図形の面積・体積を求める方法を開発しています。
しかし、その方法は直観的であり、堅固な一般論にはなりませんでした。
フェルマー、デカルト、バロー(Barrow, Isaac;1630-1677) らによる接線の問題も同様です。
突破口は、17世紀の終わり近くにニュートンとライプニッツにより独立に切り開かれました。
彼らは、独立に無限小解析(微分積分学)を創造し、一般的な方法により接線の問題(微分学)と求積(quadrature)の問題(積分学)を扱うことに成功したのです。
次回はニュートンの方法について語ります。
如何でしたか?
感想など是非コメントで教えて下さい!
結
今回は、有限アーベル群の基本定理の証明の一部を解説しました。
有限アーベル群の基本定理は、「任意の有限アーベル群が巡回群の直積に同型である」という主張の定理です。
今回は、考察している分解が直積因子の順序を除き一意的であることを証明しました。
次回も続きとして、一般の場合の直積因子の一意性の証明を証明します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ一週間以内にお答えします。
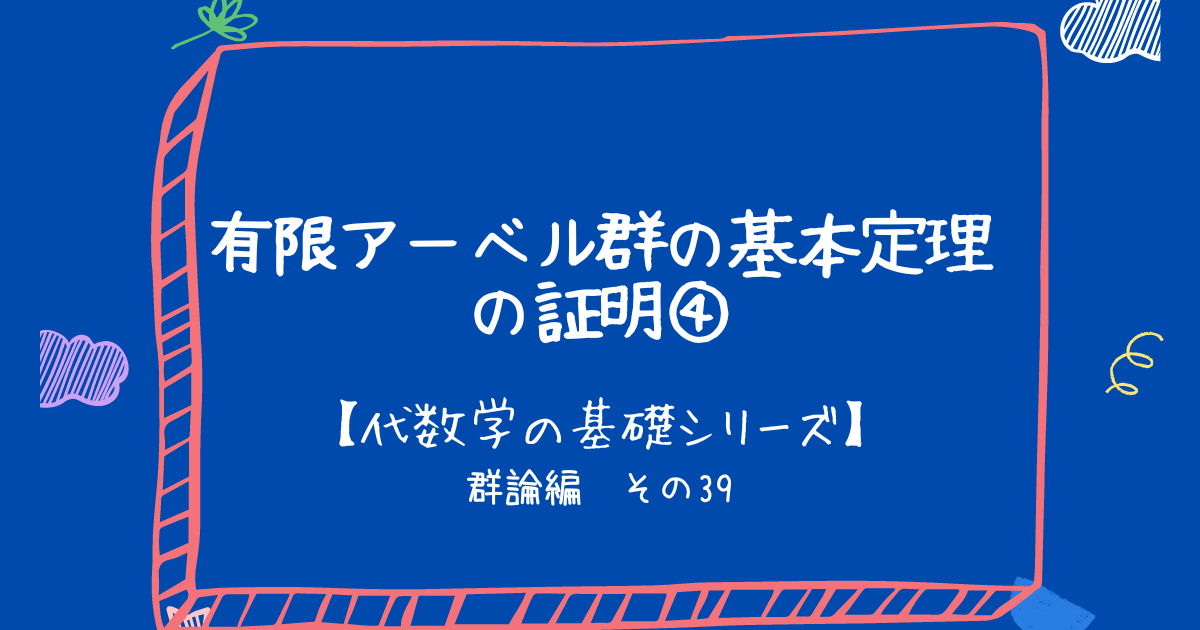

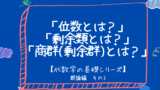
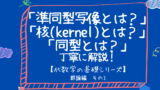
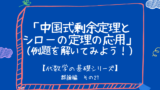


コメントをする
雪江先生の教科書の丸写しのようです。せっかく紙面に制限がないのだから、もっと噛み砕いてせつめいしてほしいです
タカシ様
コメントありがとうごさいます。
また、ご指摘ありがとうございます。
本ブログをより良いものとするため、真摯に受け止めさせて頂き、鋭意精進いたします。
「直積因子の順序を変えて」とは、a_1<a_2…と整列させることを言っていますか。
「p^(a_t)はGの要素の位数の最大値なので、先の分解によらずGにより定まる数です」(①)
元ネタの雪江先生の本には、「h∈GをGの位数最大の元、p^cをその位数とする」(②)とあります。①と②は、最大の位数はp^(a_t)とp^cのどちらかという読みにくい箇所ですが、本サイトでは(そのためか)②に該当する記述が見当たらないようですね。なお、①の「先の分解によらずGにより定まる数です」という箇所について敷衍していただけませんか
naru様
返信が遅れてしまい、申し訳ございません。
>「直積因子の順序を変えて」とは、a_1<a_2…と整列させることを言っていますか。
おっしゃるとおりです。
>「p^(a_t)はGの要素の位数の最大値なので、先の分解によらずGにより定まる数です」(①)
元ネタの雪江先生の本には、「h∈GをGの位数最大の元、p^cをその位数とする」(②)とあります。①と②は、最大の位数はp^(a_t)とp^cのどちらかという読みにくい箇所ですが、本サイトでは(そのためか)②に該当する記述が見当たらないようですね。
②に該当する記述が見当たらないというご指摘ですが、これは書き忘れではありません。
また、本記事では最大の位数は\(p^{a_t}\)です。
「\(h\in G\)は\(G\)の位数最大の要素であり、その位数を\(p^c\)とする」という仮定は、\(G\)が巡回群の直積となることを\(\left|G\right|\)に関する数学的帰納法で証明するとき(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その37)に置いたものです。
本記事とは独立しています(故に本記事では\(h\)という記号は使っておりません)。
強いて【代数学の基礎シリーズ】群論編 その37の\(h\)という記号を踏襲すれば、\(h\)はその37では位数を\(p^c\)と表記し、本記事では位数を\(p^{a_t}\)と表記しているということになります。
平たく言えば、新たに書き直したと捉えることもできます。
>なお、①の「先の分解によらずGにより定まる数です」という箇所について敷衍していただけませんか
一言で言えば、「数を並び替えたとて最大値は変わらない」ということです。
例えば、「\(1,2,3,4,5\)の最大値は?」と聞かれたら、「\(5\)」です。
では、「\(4,1,2,5,3\)の最大値は?」と聞かれたらどうでしょうか。
もちろんこれも「\(5\)」です。
つまり、自然数の最大値は、表示の仕方に依存しないということです。
もう少し今回の例に寄った例を挙げれば、
$$
\left( \mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}\right)^{b_2}\times\left( \mathbb{Z}/{3\mathbb{Z}}\right)^{b_3}\times\left( \mathbb{Z}/{4\mathbb{Z}}\right)^{b_4}
$$
の要素の位数の最大値は\(4\)ですし、直積を並び替えた
$$
\left( \mathbb{Z}/{3\mathbb{Z}}\right)^{b_3}\times\left( \mathbb{Z}/{4\mathbb{Z}}\right)^{b_4}\times\left( \mathbb{Z}/{2\mathbb{Z}}\right)^{b_2}
$$
の要素の位数の最大値も\(4\)です。
したがって、「先の分解によらずGにより定まる数です」というのは、要素の位数が\(G\)の分解(表示の仕方)に依存せず、\(G\)そのものから導ける値だ、という意味になります。
元ネタの雪江先生の本では、Hについての直積で本サイトとは異なっております。一番最後が(pZ/…)^(b_t)と雪江先生の本ではなっています。また同型でも本サイトでは(Z/…)^(b_t)の項が抜け落ちています。何か特別な意味があるのでしょうか
naru様
ご指摘ありがとうございます。
誤植でございます。
訂正いたしました。
至急お願いいたします。雪江代数学2、命題1.7.2で、π:A→A/pを自然な準同型とする、とあります。そして、任意のA/pの0でない元yに対しx∈A/pがあり、π(x)=yとなる、と続きます。x∈A/pではなくx∈Aではないでしょうか。
naru様
申し訳ございませんが、私は雪江先生の代数学2を持ち合わせておりませんので、お答えしかねます。
そうだったのですね。証明方法が酷似しているためお持ちだと思いました。わざわざ動画視聴までしてお答えいただきありがとうございましたm(_ _)m
雪江代数2についてお尋ねします。オノコウスケさまが同書をお持ちであるという前提で、話を進めさせてください。命題3.3.5で、2→1の証明。iはpの倍数なら、f(x)はx^pの多項式になるというのがわかりません。本をお持ちでないのでしたら、YouTubeで「雪江 代数学」と検索していただき、第4回2限目の講座の19:28あたりをご視聴ください。どうかご教示ください。
2→1ではなく2→3の証明でした。
naru様
雪江先生の代数学2を持ち合わせておりませんので、動画を拝聴致しました。
おそらく、
$$
f(X)=\sum_{i}a_{pi}X^{pi}
$$
となる理由がわからない、というお問い合わせだと思いますので、そのつもりで回答させていただきます。
$$
f(X)=\sum_{i=0}^na_iX^i
$$
と書き、標数を\(p\)で書くとします(動画の記法に則れば、\(p:={\rm ch}K\))。
それまでの議論から係数\(a_i\)が\(0\)でないような\(f(X)\)の項については、\(i\mid p\)でなければなりません。
つまり、係数\(a_i\)が\(0\)でないような項については、
$$
\exists j\ {\rm s.t.}\ i=pj
$$
となっていなければなりません。これを踏まえれば簡単です。
以下、\([\cdot]\)はガウス記号を表します。
\begin{eqnarray}
f(X)&=&\sum_{i=0}^na_iX^i=\sum_{\substack{0\leq i\leq n\\ a_i\neq 0}}a_iX^i=\sum_{\substack{i=pj\\ 0\leq pj \leq n}}a_iX^i\\
&=&\sum_{\substack{0\leq pj \leq n}}a_{pj}X^{pj}=\sum_{\substack{0\leq j \leq \left[ \frac{n}{p}\right]}}a_{pj}X^{pj}=\sum_{j=0}^{\left[ \frac{n}{p}\right]}a_{pj}X^{pj}\\
\end{eqnarray}
この\(j\)を新たに\(i\)と書き直す(この\(i\)は今まで出現している\(i\)とは別物)事によって
$$
f(X)=\sum_{j=0}^{\left[ \frac{n}{p}\right]}a_{pj}X^{pj}
$$
となります。
もっと平たく述べれば、\(a_i\neq0\)なる\(i\)はすべて\(p\)の倍数なのだから、\(f(X)\)から\(a_i=0\)なる項を除けば、それ以外の項の添字はすべて\(p\)の倍数となるわけです。
つまり、動くのは\(i=pj\)となるような\(i\)です。
これは\(j\)を\(i\)の指定の範囲に収まるように動かしても、\(i\)の範囲を網羅します。
故に
$$
f(X)=\sum_{i}a_{pi}X^{pi}
$$
となるわけです。
私の勝手な憶測ですが、\(\left[\frac{n}{p}\right]\)を書くとむしろ読みにくくなる、または\(\left[\frac{n}{p}\right]\)と書かずとも後の議論には本質的に影響がない為、動画では\(i\)の範囲を書いていないのだと思います。
ありがとうございます。
〉このjを新たにiと書き直す(このiは今まで出現しているiとは別物)事によって
このiの使用にに引っかかりを感じていたのです。
至急お願いいたします。雪江代数学2、命題1.7.2で、π:A→A/pを自然な準同型とする、とあります。そして、任意のA/pの0でない元yに対しx∈A/pがあり、π(x)=yとなる、と続きます。x∈A/pではなくx∈Aではないでしょうか。
上の質問に対し、雪江2をお持ちでないと答えられましたね。再度、雪江2の内容を転載したものを、ずいぶん前にお送りしております。お答えいただくことを期待しています。
naru様
返信が遅れ、申し訳ございません。
>x∈A/pではなくx∈Aではないでしょうか。
というお問い合わせについてお答えいたします。
以下、\(\left(A,+,\times \right)\)を可換環、\(0\)は\(\left( A,+,\times\right)\)の和における単位元、\(\mathfrak{p}\subsetneq{A}\)が素イデアル、\(\pi:A\longrightarrow A/{\mathfrak{p}}\)を自然な環準同型として話を進めます。
ご指摘の通り、\(x\in A/{\mathfrak{p}}\)は\(x\in A\)の誤植だと思われます。
実際、\(\pi:A\longrightarrow A/{\mathfrak{p}}\)のように\(\pi\)の定義域が\(A\)だからです。
さらにいいえば、その後の文章と合わせて「任意の\(A/{\mathfrak{p}}\)の\(0\)(可換環\(A\)の和における単位元と捉えて)でない元\(y\)に対し\(x\in A\)があり、\(\pi(x)=y\)となる」と読んでも問題がないからです。
ちなみに、\(\pi\)は自然な準同型であるため、\(\pi\)は全射だから、任意の\(y\in A/{\mathfrak{p}}\)に対して\(\pi(x)=y\)なる\(x\in A\)が存在します。