本記事の内容
本記事は、「群とは何か?」とういことを例と共に解説する記事です。
本記事を読むにあたり、同値関係について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。
「群」って何ですか?(直感的なお話)
まず、「群とは何か?」ということを直感的にお話します。
「群」を一言で。
「群」は「ぐん」と読みます。
群を一言で言えば、
です。
ここで、「演算って何ですか?」という話になりますが、それは次節で解説することにして、我々がすでに知っている演算と、群の例から見ていくことにしましょう。
例えばどんなのが群ですか?
例1.(整数の加法)
整数全体の集合\(\mathbb{Z}\)には”たし算(加法)”と呼ばれる演算\(+\)が定まっています。
そして、\(\mathbb{Z}\)のたし算と呼ばれる演算\(+\)は次の性質を満たします。
例えば、\(0,1-,2,3\in\mathbb{Z}\)という整数に対して
- \(\left\{1+\left( -2\right)\right\}+3=(1-2)+3=-1+3=2=1+1=1+\left\{\left(-2 \right)+3\right\}\)、
- \(0+1=1+0=1\)、
\(0+\left( -2\right)=\left( -2\right)+0=-2\)、
\(0+3=3+0=3\)、 - \(1+\left( -1\right)=\left( -1\right)+1=0\)、
\(\left( -2\right)+\left\{-\left( -2\right)\right\}=\left( -2\right)+2=0\)、
\(3+\left( -3\right)=\left( -3\right)+3=0\)
が成り立ちます。
これは、単に\(0,1-,2,3\in\mathbb{Z}\)という整数だけに対して成り立つことではなくて、一般の\(a,b,c\in\mathbb{Z}\)に対して
- \((a+b)+c=a+(b+c)\)、
- \(0+a=a+0=a\)、
- \(a+(-a)=(-a)+a=0\)
が成り立ちます。
これらの性質1.、2.、3.が成り立つような演算が定まっている集合を群といいます(後で厳密に書きます)。
故に、\(\mathbb{Z}\)は整数のたし算(加法)という演算で群です。
もう1つ我々がよく知っている例を挙げることにします。
例2.(実数から\(0\)を除いた集合)
\(\mathbb{R}_{\neq0}=\mathbb{R}\setminus\{0\}\)には”かけ算(乗算)”と呼ばれる演算\(\times\)が定まっています。
そして、\(\mathbb{R}_{\neq0}\)における”かけ算”と呼ばれる演算\(\times\)は、任意の\(a,b,c\in\mathbb{R}_{\neq0}\)に対して、次の性質を満たします。
- \((a\times b)\times c=a\times (b\times c)\)、
- \(1\times a=a \times 1=a\)、
- \(\displaystyle a\times a^{-1}=a\times\frac{1}{a}=\frac{1}{a}\times a=a^{-1}\times a=1\)
故に、例1.と同様にして\(\mathbb{R}_{\neq0}\)は\(\times\)という演算で群です。
「何を当然のことを言ってるんだ?」と思うかもしれません。
それは恐らくすでに我々がたし算やらの演算を無意識に行えるくらい身近に感じているので、改まって”演算”やらと言われてもピンと来ないのだと思います。
そこで、ほんのちょっとだけ複雑な”演算”とその演算で群になる集合を1つ紹介します。
例3.(全単射の集合)
「おお…いきなり複雑になったな…」と思うかもしれませんが、むしろ若干複雑な方が”演算”というモノに対してイメージが湧きやすいと思います。
とします。
要するに、\(\mathcal{S}_X\)は、集合\(X\)から\(X\)への全単射を全て集めてきた集合ということです。
任意の\(f,g\in\mathcal{S}_X\)に対して、\(f\circ g\in\mathcal{S}_X\)です。
実際、\(f:X\longrightarrow X\)かつ\(g:X\longrightarrow X\)ですので、\(f\circ g:X\longrightarrow X\)です。
さらに、全単射な写像の合成写像もまた全単射です。
故に\(f\circ g\in\mathcal{S}_X\)です。
さらに、恒等写像\({\rm id}_X\)も\({\rm id}_X\in\mathcal{S}_X\)であることに注意します。
任意の\(f,g\in\mathcal{S}_X\)に対して、\(f,g\)の合成写像\(f\circ g\)を”演算の結果”と捉えることにしましょう。
(言うなれば「\(f,g\in\mathcal{S}_X\)に対して、\(f\)と\(g\)を合成する。」ということが”演算”です。)
このとき、
- \(h\circ \left( g\circ f\right)=\left(h\circ g \right)\circ f\)が成り立ちます。
実際、任意の\(x\in X\)に対して
\begin{eqnarray}
\left(h\circ \left( g\circ f\right)\right)(x)&=&h\left( (g\circ f)(x)\right)\\
&=&h\left( g(f(x))\right)\\
&=&\left( h\circ g\right)\left(f(x) \right)\\
&=&\left(\left( h\circ g\right)\circ f\right)(x)\\
\end{eqnarray}
が成りたつからです。 - \({\rm id}_X\)であり、任意の\(f\in\mathcal{S}_X\)に対して\({\rm id}_X\circ f=f\circ {\rm id}_X=f\)が成り立ちます。
- 任意の\(f\in\mathcal{S}_X\)に対して、\(f^{-1}\in\mathcal{S}_X\)であり、\(f\circ f^{-1}=f^{-1}\circ f={\rm id}_X\)が成り立ちます。
実際、\(f\in\mathcal{S}_X\)であるので、\(f\)は全単射だから、\(f\)の逆写像\(f^{-1}:X\longrightarrow X\)が存在します。
そして、\(f^{-1}\)もまた全単射だから\(f^{-1}\in\mathcal{S}_X\)です。
さらに、\(f^{-1}\)は\(f\)の逆写像なので\(f\circ f^{-1}=f^{-1}\circ f={\rm id}_X\)が成り立ちます。
が成り立ちます。
故に\(\mathcal{S}_X\)は写像の合成という演算で群です。
「例3.は例1.とも例2.とも毛色が違うから分かりにくい…」と感じるかもしれませんので、次はこれについて述べます。
群の条件を直感的に少し詳しく(特に例3.について)
先程述べた例3.の1.、2.、3.という性質は例1.と例2.の性質1.、2.、3.と本質的には同じです。
どういうことかというと、ある集合\(G\)の任意の要素に対して、\(\ast\)という演算が定まっているとします(\(\ast\)は例1.においては\(+\)(たし算)、例2.においては\(\times\)(かけ算)、例3.においては\(\circ\)(写像の合成)です)。
\(x,y\in G\)に対して、この演算\(\ast\)の結果(つまり演算の結果)を\(x\ast y\)と書くことにしましょう。
このとき、任意の\(x,y,z\in G\)に対して以下の3つが成り立つときに\(G\)は(演算\(\ast\)で)群である、群をなす、といいます。
- 結合律
$$
\left( x\ast y\right)\ast z=x\ast \left( y\ast z\right)
$$
この条件は、最初に\(x\)と\(y\)を”計算”(というより演算)した後に、その演算結果\(x\ast y\)と\(z\)を再度演算したモノと、最初に\(y\)と\(z\)を演算した後に、その演算結果\(y\ast z\)と\(x\)を再度演算したモノが一致している、という条件です。
要するに、何と何を演算するか、ということさえ変わらなければどこから演算しても良い、ということになります。
例えば、実数から\(0\)を取り除いた集合に対して、その掛け算とわり算はどこから計算してもOKですよね。 - 単位元の存在
$$
(\exists e\in G)\ {\rm s.t.}\ \left\{(\forall a\in G)\ \left(a\ast e=e\ast a=a\right)\right\}
$$
これを満たすような\(e\in G\)が存在するとき、その\(e\in G\)を\(G\)の単位元といいます。
この\(e\)は、\(G=\mathbb{Z}\)(つまり例1.の場合)においては\(e=0\)で、\(G=\mathbb{R}_{\neq0}\)(つまり例2.の場合)においては\(e=1\)です。
この「単位元と呼ばれる要素が存在する。」という条件は、「その集合のどんな要素と演算しても、演算の結果が変わらないような特別な要素が存在する。」という条件です。
確かに、整数のたし算に限らず実数のたし算においては、どんな実数に対して\(0\)を足しても結果は変わりませんよね。
さらに、実数のかけ算においては、どんな実数に対して\(1\)をかけても結果は変わりませんよね。 - 逆元の存在
$$
(\forall a\in G)\ (\exists b\in G)\ {\rm s.t.}\ a\ast b=b\ast a=e
$$
ただし、\(e\in G\)は2.で述べた単位元です。
任意の\(a\in G\)に対して、\(a\ast b=b\ast a=e\)を満たすような\(b\in G\)が存在するとき、この\(b\in G\)を\(a\)の逆元と言って、\(b\)を\(a^{-1}\)で表します。
要するに、この「逆元と呼ばれる要素が存在する。」という条件は、「その集合の全ての要素1つ1つに対して、演算すると結果が単位元になるような要素が存在する。」という条件です。
単位元は各演算に対して1つだけだったのに対して、逆元は各要素ごとに存在します。
確かに、実数のたし算において、どんな実数に対しても足すと\(0\)になるような1つだけの特別な要素はありませんよね。
\(\mathbb{R}\)のたし算\(+\)においては、\(2\in\mathbb{R}\)に対して\(-2\in\mathbb{R}\)が逆元であるように、\(a\in\mathbb{R}\)に対して\(-a\in\mathbb{R}\)が\(a\in\mathbb{R}\)の逆元です。
実際、任意の\(a\in\mathbb{R}\)に対して\(-a\in\mathbb{R}\)で、かつ\(a+(-a)=0\)となり、\(0\)は\(\mathbb{R}\)のたし算における単位元だからです。
\(\mathbb{R}_{\neq0}\)のかけ算\(\times\)においては同様にして\(a\in\mathbb{R}_{\neq0}\)に対して\(\displaystyle\frac{1}{a}\in\mathbb{R}_{\neq0}\)が\(a\in\mathbb{R}_{\neq0}\)の逆元です。
実際、\(\displaystyle a\times\frac{1}{a}=1\)となり、\(1\)は\(\mathbb{R}_{\neq0}\)の単位元だからです。
“演算”の正体
次に、”演算”の正体について解説します。
“演算”って何ですか?
演算の正体は写像です。
演算
\(X\)が集合であるとき、写像\(\varphi:X\times X\longrightarrow X\)を集合\(X\)上の演算という。つまり、集合\(X\)に対して「演算が定まっている」とは、「写像\(\varphi:X\times X\longrightarrow X\)が定まっている」ということです。
先程の例1.、例2.、例3.の演算を写像の形で書いてみます。
- 例1.の演算
\(\varphi:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}\)を、任意の\(a,b\in\mathbb{Z}\)に対して
$$
\varphi(a,b)=a+_{\mathbb{Z}}b
$$
で定まる演算です。
ただし、\(+_{\mathbb{Z}}\)と書いたのは、整数におけるたし算であることを明示するためです。 - 例2.の演算
\(\varphi:\mathbb{R}_{\neq0}\times\mathbb{R}_{\neq0}\longrightarrow\mathbb{R}_{\neq0}\)を、任意の\(a,b\in\mathbb{R}_{\neq0}\)に対して
$$
\varphi(a,b)=a\times_{\mathbb{R}_{\neq0}}b
$$
で定まる演算です。
ただし、\(\times_{\mathbb{R}_{\neq0}}\)と書いたのは、\(\mathbb{R}_{\neq0}\)におけるかけ算であることを明示するためです。 - 例3.の演算
\(\varphi:\mathcal{S}_X\times\mathcal{S}_X\longrightarrow\mathcal{S}_X\)を、任意の\(f,g\in\mathcal{S}_X\)に対して
$$
\varphi(f,g)=f\circ g
$$
で定まる演算です。
どうして「〜における演算」と言うのですか?
細かいと言えば細かいことなのですが、演算の見てくれが同じでも、演算として異なる事があるからです。
どういうことか?というと、例えば、先の例1.の演算\(+_{\mathbb{Z}}\)は、演算の規則としては自然数におけるたし算と同じです。
しかしながら、自然数全体の集合\(\mathbb{N}\)は、自然数のたし算\(+_{\mathbb{N}}\)では群になりません。
なぜなら、逆元が存在しないからです。
というのも、\(n\in\mathbb{N}\)に対して、逆元は\(-n\)の形をしているはずですが、\(-n<0\)だから\(-n\not\in\mathbb{N}\)となるからです。
このように、「やってることは同じでしょ?」という演算でも、厳密には異なることがあります。
これは先の演算を写像で捉えるという立場にたてば
- \(+_{\mathbb{Z}}:\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}\)、
- \(+_{\mathbb{N}}:\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{N}\)
というように、定義域と終域が異なります。
「群」ってなんですか?(数学的なお話)
では、数学的に「群とは何か?」ということを明示します。
群
\(G\)を空でない集合とする。\(G\)上の演算\(\varphi:G\times G\longrightarrow G\)が定められていて、次の性質を満たすとき、\(G\)を群(group)という。- 結合律 任意の\(a,b,c\in G\)に対して、\(\varphi\left(\varphi(a,b),c \right)=\varphi\left(a,\varphi(b,c) \right)\)が成り立つ。
- 単位元の存在 ある\(e\in G\)が存在して、任意の\(a\in G\)に対して\(\varphi(a,e)=\varphi(e,a)=a\)が成り立つ。この\(e\in G\)を単位元と呼び、\(1_G\)と書くことがある。
- 逆元の存在 任意の\(a\in G\)に対して、ある\(b\in G\)が存在して、\(\varphi(a,b)=\varphi(b,a)=e\)が成り立つ。この\(b\in G\)を\(a\in G\)の逆元といい、\(a^{-1}\)で表す。
厳密に書くと上記が群です。
上記の3つの条件を群の公理という事もあります。
厳密なのは良いですが、演算を写像のかたちで書くと少々複雑、というか分かりにくい部分があります。
そこで、簡易的な新たな記号を導入します。
とはいえ、すでに出現している記号で、演算\(\varphi:G\times G\longrightarrow G\)に対して
$$
\varphi(a,b)=a\ast b
$$
か、または単に
$$
\varphi(a,b)=ab
$$
と書くことにします。
ただし、
ということに注意して下さい。
この記法にのっとれば、先の群の説明は、以下のように書き換えられます。
群(簡易的な記法を使ったver.)
\(G\)を空でない集合とする。\(G\)上の演算\(\ast\)が定められていて、次の性質を満たすとき、\(G\)を群(group)という。- 結合律 任意の\(a,b,c\in G\)に対して、\(\left(a\ast b \right)\ast c=a\ast \left(b\ast c \right)\)が成り立つ。
- 単位元の存在 ある\(e\in G\)が存在して、任意の\(a\in G\)に対して\(a\ast e=e\ast a=a\)が成り立つ。この\(e\in G\)を単位元と呼び、\(1_G\)と書くことがある。
- 逆元の存在 任意の\(a\in G\)に対して、ある\(b\in G\)が存在して、\(a\ast b=b\ast a=e\)が成り立つ。この\(b\in G\)を\(a\in G\)の逆元といい、\(a^{-1}\)で表す。
こちらのほうがスッキリしていて読みやすいと思います。
どちらで覚えても構いませんが、簡易的な記法を使ったver.で覚える場合は「集合\(X\)上の演算は写像\(\varphi:X\times X\longrightarrow X\)のことだ。」と注意する必要があります。
群の代表例
特別な群は数え切れないほどたくさんありますが、中でも基本的なものを紹介します。
すでに出現していて、「実は群でした。」というものもあります。
例3.(全単射の集合)
は写像の合成を演算として群でした。
この\(\mathcal{S}_X\)は特別な呼び名があり、置換群、または対称群と呼びます。
これは、まさに以前線型代数の記事で解説した置換が、写像の合成でもって群であるということです。
置換とは以下でした。
置換
\(n\in\mathbb{N}\)とする。\(n\)個の文字\(1,2,\dots,n\)からなる集合を $$ M_n=\{1,2,\dots,n\} $$ とする。写像\(\sigma:M_n\to M_n\)が全単射であるとき、\(\sigma\)を\(M_n\)の置換という。置換\(\sigma\)による対応が $$ 1\mapsto i_1,\ 2\mapsto i_2,\dots,n\mapsto i_n $$ であるとする、すなわち、 $$ \sigma(1)=i_1,\ \sigma(2)=i_2,\dots,\ \sigma(n)=i_n $$ とする。このとき\(\sigma\)を $$ \sigma= \begin{pmatrix} 1&2&\cdots&n \\ i_1&i_2&\cdots&i_n\\ \end{pmatrix} $$ と書く。
詳しくは【線型代数学の基礎シリーズ】行列式編 その1を御覧ください。
例4.(線型空間)
実は、線型空間もベクトルの和を演算として群です。
線型空間とは以下でした。
線型空間(ベクトル空間)
集合\(V\)が次の2条件Ⅰ.およびⅡ.を満たすとき、\(V\)を複素線型空間、複素ベクトル空間、\(\mathbb{C}\)上の線型空間(ベクトル空間)という。- 任意の\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V\)に対して、和と呼ばれる第三の\(V\)の要素(これを\(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\in V\)と書く)が定まり、次の法則が成り立つ。
- \((\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})+\boldsymbol{z}=\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})\quad\)(結合則)
- \(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}\quad\)(交換則)
- 零ベクトルと呼ばれる特別な要素(これを\(\boldsymbol{0}\)で表す)がただ1つ存在して、任意の\(\boldsymbol{x}\in V\)に対して\(\boldsymbol{0}+\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}\)が成り立つ。
- 任意の\(\boldsymbol{x}\in V\)に対して、\(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^\prime=\boldsymbol{0}\)となる\(\boldsymbol{x}^\prime\in V\)がただ1つ存在する。これを\(\boldsymbol{x}\)の逆ベクトルといい、\(-\boldsymbol{x}\)で表す。
- 任意の\(x\in V\)と任意の\(c\in\mathbb{C}\)に対して、\(\boldsymbol{x}\)の\(c\)倍と呼ばれるもう1つの\(V\)の要素(これを\(c\boldsymbol{x}\in V\)で表す)が定まり、次の法則が成り立つ、
- 任意の\(c,d\in\mathbb{C}\)に対して\((c+d)\boldsymbol{x}=c\boldsymbol{x}+d\boldsymbol{x}\)
- \(c(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=c\boldsymbol{x}+c\boldsymbol{y}\)
- 任意の\(c,d\in\mathbb{C}\)に対して、\((cd)\boldsymbol{x}=c(d\boldsymbol{x})\)
- \(1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}\)
詳しくは【線型代数学の基礎シリーズ】線型空間編 その1を御覧ください。
上記の線型空間の「線型空間とは何か?」ということを見れば、線型空間はベクトルの和でもって群であることが分かります。
ちなみに、線型空間\(V\)に対して、単位元は零ベクトル\(\boldsymbol{0}\in V\)、\(\boldsymbol{x}\in V\)に対する逆元は\(-\boldsymbol{x}\in V\)です。
ここで、2.(交換則)について言及しておきます。
一般に、\(G\)が演算\(\ast\)で群だとします。
しかし、必ずしも任意の\(a,b\in G\)に対して\(a\ast b=b\ast a\)が成り立つとは限りません(成り立たない例は後述します)。
群を例で挙げた\(\mathbb{Z}\)やら\(\mathbb{R}_{\neq0}\)で連想すると、「え?成り立たないことがあるの?」と思うかもしれませんが、必ずしも成り立ちません。
このように群の公理のほかに、任意の\(a,b\in G\)に対して\(a\ast b=b\ast a\)が成り立つような群を可換群(またはアーベル群)といいます。
可換群(アーベル群)
\(G\)を空でない集合とする。\(G\)上の演算\(\ast\)が定められていて、次の性質を満たすとき、\(G\)を可換群(Abel group)という。- 結合律 任意の\(a,b,c\in G\)に対して、\(\left(a\ast b \right)\ast c=a\ast \left(b\ast c \right)\)が成り立つ。
- 単位元の存在 ある\(e\in G\)が存在して、任意の\(a\in G\)に対して\(a\ast e=e\ast a=a\)が成り立つ。この\(e\in G\)を単位元と呼び、\(1_G\)と書くことがある。
- 逆元の存在 任意の\(a\in G\)に対して、ある\(b\in G\)が存在して、\(a\ast b=b\ast a=e\)が成り立つ。この\(b\in G\)を\(a\in G\)の逆元といい、\(a^{-1}\)で表す。
- 可換性 任意の\(a,b\in G\)に対して、\(a\ast b=b\ast a\)が成り立つ。
とどのつまり、線型空間\(V\)はベクトルの和という演算で可換群です。
例5.(一般線型群)
実数を成分に持つ\((n,n)\)型の正則行列全体の集合を\({\rm GL}_n(\mathbb{R})\)と書きます。
すなわち、
です。
正方行列が正則であることと、その正方行列の行列式が\(0\)でないことは同値ということ(これについては【線型代数学の基礎シリーズ】行列式編 その6を御覧ください)を使い、\((m,n)\)型の実数を成分に持つ行列の集合を\(M_{m,n}(\mathbb{R})\)で書くと、
$$
{\rm GL}_n(\mathbb{R})=\left\{A\in M_{m,n}(\mathbb{R})\middle|\det A\neq0\right\}
$$
と表現することも出来ます。
余談(\({\rm GL}_n(\mathbb{R})\)という記号について)
記号\({\rm GL}_n(\mathbb{R})\)の\({\rm GL}\)は、一般線型群の英語名General Liner Groupが由来です。この集合\({\rm GL}_n(\mathbb{R})\)は、行列の積を演算として群です。
実際、以下が成り立つからです。
- 結合律 行列の積は、結合律を満たします。
- \((AB)C=A(BC)\quad\)(積の結合則)
- \(AI_n=I_mA=A\quad\)(\(I_n\)および\(I_m\)はそれぞれ\(n\)次、\(m\)次単位行列)
- \(AO_n=O_mA=O_{mn}\quad\) ただし、\(O_n\)は\(n\)次正方行列の零行列、\(O_m\)は\(m\)次正方行列の零行列、\(O_{mn}\)は\((m,n)\)型の零行列を指す。
- 単位元の存在 \(I_n\)で\((n,n)\)型の単位行列を表したとすると、\(\det I_n=1\neq0\)により、\(I_n\)は正則なので、\(I_n\in{\rm GL}_n(\mathbb{R})\)です。
- 逆元の存在 任意の\(A\in{\rm GL}_n(\mathbb{R})\)は正則なので、逆行列\(A^{-1}\)が存在します。
実際、
行列の積の性質
\(m,n,r,s\in\mathbb{N}\)とする。\((m,n)\)型行列\(A\)、\((n,r)\)型行列\(B\)、\((r,s)\)型行列\(C\)に対して、以下が成り立つ。行列の積の性質の証明は【線型代数学の基礎シリーズ】行列編 その2を御覧ください。
さらに、任意の\(A\in{\rm GL}_n(\mathbb{R})\)に対して、\(AI_n=I_nA=A\)が成り立つため、\(I_n\)は\({\rm GL}_n(\mathbb{R})\)の単位元です。
このとき、\(AA^{-1}=A^{-1}A=I_n\)が成り立つので、任意の\(A\in {\rm GL}_n(\mathbb{R})\)に対して逆元が存在します。
故に、\({\rm GL}_n(\mathbb{R})\)は、行列の積で群です。
しかしながら、\({\rm GL}_n(\mathbb{R})\)は可換群ではありません。
なぜなら、\((n,n)\)型の行列\(A\)と\(B\)の積\(AB\)は必ずしも\(BA\)とは一致しないからです。
簡単な群の性質
簡単な群の性質を解説します。
命題7.
\(G\)が群で、\(a,b,c\in G\)ならば、次の1.、2.が成り立つ。- \(a\ast b=a\ast c\Longrightarrow b=c\)(簡約法則)
- \(a\ast b=c\Longrightarrow b=a^{-1}\ast c,\ a=c\ast b^{-1}\)
命題7.の証明
(1)の証明
両辺に\(a^{-1}\)を左から演算を施せば、\(b=a^{-1}\ast a\ast b=a^{-1}\ast a\ast c=c\)により、成り立ちます。
(2)の証明
\(a^{-1}\)を左から演算を施すことで\(b=a^{-1}\ast c\)となります。
\(a=c\ast b^{-1}\)も同様です。
命題7.の証明終わり
命題8.
- 群の単位元は唯一つである。
- \(a\in G\)に対して、その逆元は一意的に定まる。
- \(a,b\in G\)ならば、\(\left( a\ast b\right)^{-1}=b^{-1}\ast a^{-1}\)である。
- \(a\in G\)ならば、\(\left( a^{-1}\right)^{-1}=a\)である。
命題8.の証明
\(G\)を\(\ast\)を演算とする群とします。
(1)の証明
\(e,e^\prime\)がともに単位元の性質を満たすとすると、\(e\)が単位元であることから\(e\ast e^\prime=e\)です。
また、\(e\)も単位元であるから、\(ee^\prime=e^\prime\)となり、\(e=e^\prime\)で、単位元の一意性が証明完了です。
(2)の証明
\(b,b^\prime\in G\)がともに\(a\in G\)の逆元だとします。
このとき
$$
b=\left( b^\prime\ast a\right)b=b^\prime\ast \left( a\ast b\right)=b^\prime
$$
となって、逆元も一意的に定まります。
(3)の証明
結合律から
$$
\left( b^{-1}\ast a^{-1}\right)\ast a\ast b=b^{-1}\ast\left( a^{-1}\ast a\right)\ast b=b^{-1}\ast b=e
$$
です。
同様にして、\(a\ast b\left(b^{-1}\ast a^{-1} \right)=e\)です。
従って、\(b^{-1}\ast a^{-1}\)は\(a\ast b\)の逆元です。
(4)の証明
\(a\ast a^{-1}=a^{-1}\ast a=e\)により、\(a\)として新たに\(c^{-1}\)という\(c\in G\)を取れば、
$$
c^{-1}\ast\left(c^{-1} \right)^{-1}=\left( c^{-1}\right)^{-1}\ast c=e
$$
となるので、成り立ちます。
命題8.の証明終わり
皆様のコメントを下さい!
今回は、アーベル群として名前が出現したアーベルを紹介します。
アーベル(Abel, Niel Henrik;1802-1829)はノルウェーの数学者です。
数学教師ホルンボエの導きにより、数学に興味を抱くようになり、19 歳のとき、次数が5以上の代数方程式は代数的に解けない(2次方程式に対する根の公式に類似な公式を持たない)ことを証明しました。
ヤコビとともに楕円関数の一般論を確立し、さらに代数関数論の基礎を築いたほかに、解析学の基礎付けにも大きな功績を残しました。
しかし、貧困の中で、ベルリン大学の教授招聘の便りを受け取る数日前に、26歳の若さで亡くなりました。
アーベルの偉大な業績を記念して、彼の名を冠する賞として、アーベル賞が2001年に創設されました。
アーベル群という用語は、可換群をガロア群として持つ代数方程式の可解性についてのアーベルの研究に由来します。
如何でしたか?
皆様はアーベルについてどう思いますか?
ここに書かれている事以外でアーベルについてご存知のことがあれば是非コメントで教えて下さい!
結
今回は例から「群とは何か?」ということについて解説しました。
群とは、演算が定められていて、結合律、単位元の存在、逆元の存在が保証されている集合のことを指します。
我々が普段何気なく行っている四則演算の一般化です。
次回は部分群、正規部分群について解説します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。
もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。
代数についてより詳しく知りたい方は以下を参考にすると良いと思います!
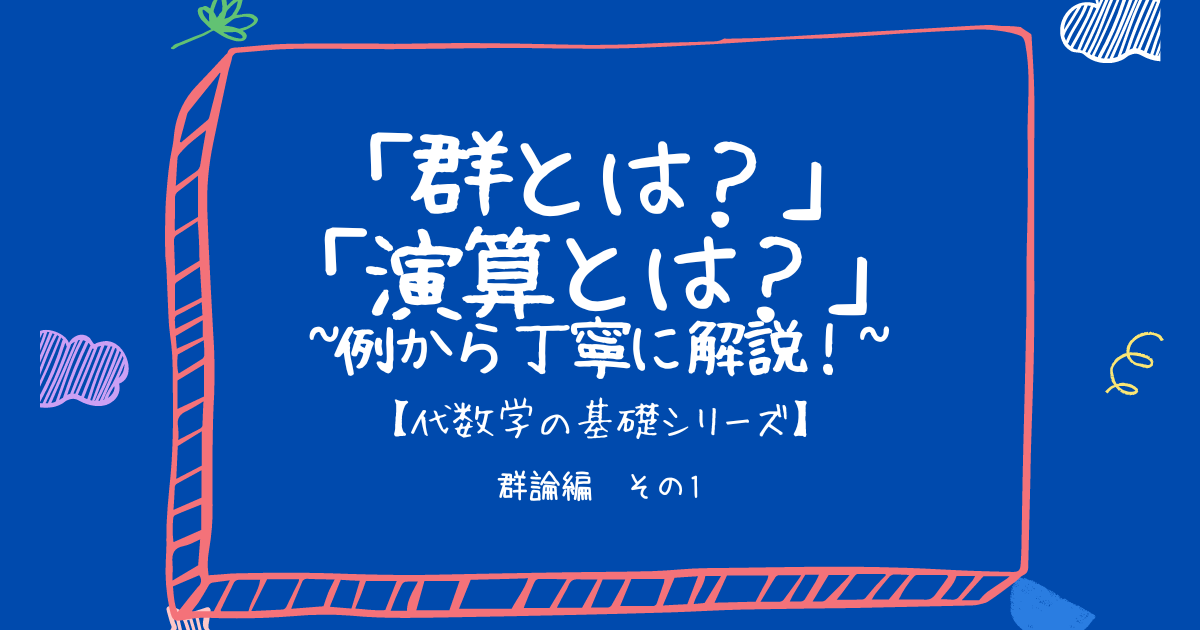



コメントをする