本記事の内容
本記事は多変数ベクトル値関数と実数値関数の商の極限について解説する記事です。
本記事を読むにあたり、多変数ベクトル値関数の極限について知っている必要があるため、その際は以下の記事を参照してください。
多変数ベクトル値関数と実数値関数の商の極限
積と同様に、ベクトル同士では単純な割り算はできません。
従って、ベクトル値関数と実数値関数の商(ベクトルのスカラー倍とも言えます)の極限について考えていきます。
では、早速主張を明示してしまいましょう。
「難しそうだネ」と思うかもしれませんが、紐解いてみるとなんてことありません。
というのも、形式的には既に証明している、とある事実とほとんど同じだからです。
多変数ベクトル値関数と実数値関数の商の極限の証明
まずは、何を示したいのかを明示するために、式変形してみましょう。
\begin{eqnarray}
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}
=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{1}{g(\boldsymbol{x})}
\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{x})\\
f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots\\
f_m(\boldsymbol{x})\\
\end{array}
\right)
=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\frac{f_1(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\displaystyle\frac{f_2(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\vdots\\
\displaystyle\frac{f_m(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\end{array}
\right)
\end{eqnarray}
ここで、次の事実を使います。
すると、
\begin{eqnarray}
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\frac{f_1(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\displaystyle\frac{f_2(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\vdots\\
\displaystyle\frac{f_m(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\end{array}
\right)
=
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{f_1(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{f_2(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\vdots\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{f_m(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\end{array}
\right)
\end{eqnarray}
です。
従って、\(B\neq0\Rightarrow \exists \delta_0>0\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\Omega;0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_0\Rightarrow g(\boldsymbol{x})\neq0)\)のとき、
$$(\forall i\in\mathbb{N};1\leq i\leq m)\ \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}
=\frac{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})}$$
が成り立てば良いことになります。
従って、これを示したいわけです。
ここで、以下の事実を思い出してみます。
この証明は【解析学の基礎シリーズ】多変数関数編 その4で証明しています。
この補題0.において\(g(\boldsymbol{x})\)を\(\displaystyle\frac{1}{g(\boldsymbol{x})}\)に変えてしまえば目標達成です。
そのため、以下を示します。
補題1.の証明
これは既に【解析学の基礎シリーズ】関数の極限編 その3で証明していることとほとんど同じです。
定義域が区間から領域になるだけです。
示したいことは
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall \boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\Rightarrow \left|\frac{1}{g(\boldsymbol{x})}-\frac{1}{B}\right|<\epsilon)$$
です。
結局は\(\delta>0\)を見つけたいので、\(\displaystyle\left|\frac{1}{g(\boldsymbol{x})}-\frac{1}{B}\right|\)を変形してみましょう。
\begin{eqnarray}
\left|\frac{1}{g(\boldsymbol{x})}-\frac{1}{B}\right|&=&\left|\frac{B-g(\boldsymbol{x})}{B\cdot g(\boldsymbol{x})}\right|=\frac{1}{|B|}\cdot\frac{1}{|g(\boldsymbol{x})|}\cdot|B-g(\boldsymbol{x})|
\end{eqnarray}
従って、\(g(\boldsymbol{x})\)がある範囲で下に有界であれば、ある\(L\in\mathbb{R}\)が存在して、\(|g(x)|>L\)ですから、\(\displaystyle\frac{1}{g(\boldsymbol{x})}<\frac{1}{L}\)ですので、あとは\(\epsilon>0\)を帳尻合わせるだけでおしまいです。
故に\(g(\boldsymbol{x})\)がある範囲で下に有界であることを示します。
補題2.の証明
簡単です。
\(\Omega\subset\mathbb{R}^n\)を\(\mathbb{R}^n\)の領域、\(g:\Omega\to\mathbb{R}\)を写像(関数)、\(\boldsymbol{a}\in\bar{\Omega}\)とします。
\(\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}\)のとき\(g(\boldsymbol{x})\)が\(B\in\mathbb{R}\)に収束するとします。
このとき、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall \boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\Rightarrow \left|g(\boldsymbol{x})-B\right|<\epsilon)$$
が成り立っています。
\(\epsilon>0\)は任意ですので、\(\displaystyle\epsilon=\frac{|B|}{2}\)としても成り立ちます。
従って、\(0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\)を満たす任意の\(\boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}\)に対して、
$$|g(\boldsymbol{x})|=|g(\boldsymbol{x})-B+B|\geq|B|-|g(\boldsymbol{x})-B|>|B|-\frac{|B|}{2}=\frac{|B|}{2}>0$$
が成り立ちます。
故に、\(0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\)を満たす任意の\(\boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}\)に対しては\(g(\boldsymbol{x})\)は下に有界です。
補題2.の証明おわり
さて、補題2.により、\(0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\)を満たす任意の\(\boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}\)に対しては\(g(\boldsymbol{x})\)は下に有界です。
すなわち、
$$(\exists L\in\mathbb{R})\ {\rm s.t.}\ \frac{1}{|g(x)|}<\frac{1}{L}$$
です。
従って、
\begin{eqnarray}
\left|\frac{1}{g(\boldsymbol{x})}-\frac{1}{B}\right|&=&\left|\frac{B-g(\boldsymbol{x})}{B\cdot g(\boldsymbol{x})}\right|=\frac{1}{|B|}\cdot\frac{1}{|g(\boldsymbol{x})|}\cdot|B-g(\boldsymbol{x})|<\frac{1}{|B|}\cdot\frac{1}{|L|}\cdot|B-g(\boldsymbol{x})|
\end{eqnarray}
です。
今、\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})=B\)ですから、
$$(\forall \epsilon_g>0)(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall \boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_g\Rightarrow \left|g(\boldsymbol{x})-B\right|<\epsilon_g)$$
です。
\(\epsilon_g>0\)は任意なので、任意の\(\epsilon>0\)を用いて、\(\epsilon_g=|B|\cdot|L|\cdot\epsilon\)としても成り立ちます。
故に、
$$(\forall |B|\cdot|L|\cdot\epsilon>0)(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall \boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_g\Rightarrow \left|g(\boldsymbol{x})-B\right|<|B|\cdot|L|\cdot\epsilon)$$
です。
\(\delta>0\)として、\(\delta_g>0\)を採用すれば、\(0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\)を満たす任意の\(\boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}\)に対して、
$$\frac{1}{|B|}\cdot\frac{1}{|L|}\cdot|B-g(\boldsymbol{x})|<\frac{1}{|B|}\cdot\frac{1}{|L|}\cdot|B|\cdot|L|\cdot\epsilon=\epsilon$$
です。
従って、\(0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\)を満たす任意の\(\boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}\)に対して、
$$\left|\frac{1}{g(\boldsymbol{x})}-\frac{1}{B}\right|<\epsilon$$
です。
以上のことから、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall \boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\Rightarrow \left|\frac{1}{g(\boldsymbol{x})}-\frac{1}{B}\right|<\epsilon)$$
です。
補題1.の証明おわり
補題1.が成り立ったので、
$$
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{f_1(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{f_2(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\vdots\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{f_m(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}\\
\end{array}
\right)=
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\frac{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})}\\
\displaystyle\frac{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})}\\
\vdots\\
\displaystyle\frac{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x})}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})}\\
\end{array}
\right)=
\frac{1}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})}
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x})\\
\end{array}
\right)
$$
です。
再度定理(多変数ベクトル値関数の収束と同値な命題)を用いることで、
$$
\frac{1}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})}
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x})\\
\end{array}
\right)=
\frac{1}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})}
\cdot\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{x})\\
f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots\\
f_m(\boldsymbol{x})\\
\end{array}
\right)
=\frac{1}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})}
\cdot\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})
=\frac{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})}
$$
です。
多変数ベクトル値関数と実数値関数の商の極限の証明おわり
本当に成り立つのかネ?
いつもの通り、簡単ではありますが、例を挙げます。
例.\(\Omega=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x+y\neq 0\}\)、\(\boldsymbol{f}:\Omega\to\mathbb{R}^2\)と\(g:\Omega\to\mathbb{R}\)が
$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\left(
\begin{array}{c}
x \\
y\\
\end{array}\right),\quad
g(\boldsymbol{x})=x+y
$$
で定められているとします。
\(\boldsymbol{x}\to(1,1)\)の極限を考えてみましょう。
このとき、
- \(\displaystyle\frac{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}g(\boldsymbol{x})}=\frac{1}{2}\cdot \left(\begin{array}{c}1\\ 1\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c} \displaystyle\frac{1}{2}\\ \displaystyle\frac{1}{2}\end{array}\right)\)
- \(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\frac{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}=\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\left(\begin{array}{c} \displaystyle\frac{x}{x+y}\\ \displaystyle\frac{y}{x+y}\end{array}\right)
=\left(\begin{array}{c} \displaystyle\frac{1}{2}\\ \displaystyle\frac{1}{2}\end{array}\right)\)
で、たしかに成り立ちます。
結
今回は、多変数ベクトル値関数と多変数実数値関数の商の極限について解説しました。
結局の所、内積やら外積やらのときと同じで、成分ごとの極限と一致するということです。
高校数学的なノリで言うところの「\(\lim\)はカッコの中に入れて計算してOK」ということです。
次回は、多変数ベクトル値関数の連続のイメージについて解説します。
乞うご期待!質問、コメントなどお待ちしております!
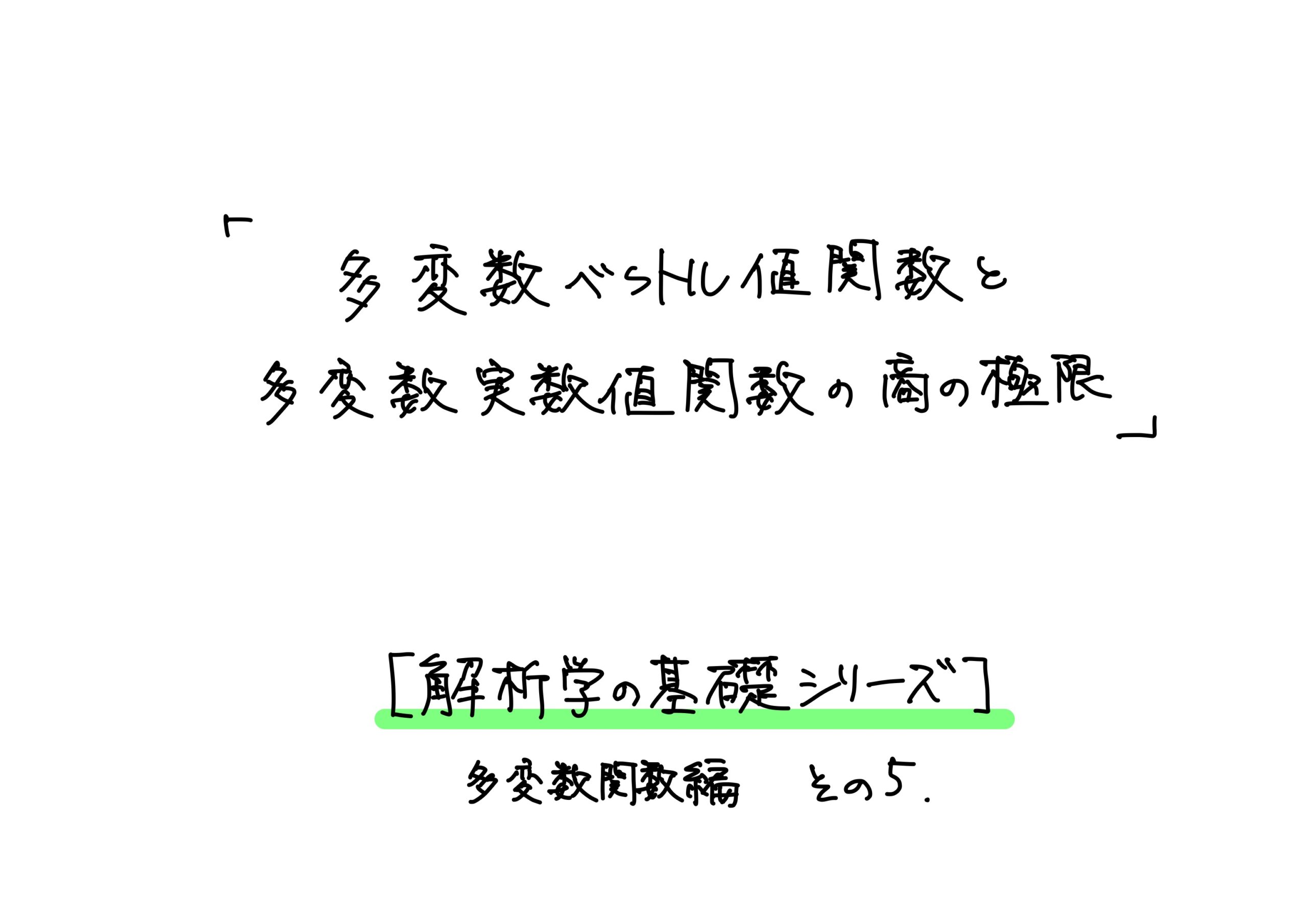



コメントをする