本記事の内容
本記事は多変数ベクトル値関数の和・差の極限が極限の和・差と一致するという事実を説明、証明する記事です。
本記事を読むにあたり、多変数ベクトル値関数とはどういうものか、及び関数の極限について知っている必要があるため、その際は以下の記事を参照してください。
多変数ベクトル値関数の極限の簡単な復習
多変数ベクトル値関数の収束は
でした。
形式的には1変数実数値関数とと何ら変わらないのでした。
ただ、極限への近づき方が
- 1変数実数値関数:関数に沿って近づく。
- 多変数ベクトル値関数:ありとあらゆる方向から近づく。
ということでした。
ただし、ベクトル値関数の極限は、座標に対してベクトルを対応させる写像とも捉えられます。
それ故、ベクトル値関数の極限はどんな座標にも同じベクトルが対応している状態がベクトル値関数の収束です。
さらに、多変数ベクトル値関数の収束と同値な命題がありました。
それが以下です。
この証明は【解析学の基礎シリーズ】多変数関数編 その2を参照してください。
要は、多変数ベクトル値関数の極限は、成分の極限からなるベクトルと一致しますよ、ということでした。
高校数学のノリでいうところの「\(\lim\)はカッコの中に入れてOK」ということです。
すなわち、点列の場合と同様に、多変数ベクトル値関数の場合も極限は1変数関数の極限に帰着できる、というわけです。
多変数ベクトル値関数の極限の和・差
点列のときと同様に、多変数ベクトル値関数の極限にも和・差・積・商を考えることができます。
ただし、積と商については1変数実数値関数のように真正直には考えられません。
点列編で述べたとおり、多変数ベクトル値関数はベクトルだからです。
さて、「何が成り立つのかネ?」ということですが、端的に述べてしまいましょう。
- \(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=A+B\)
- \(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=A+B\)
\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=A+B\)の場合は、\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=A+B\)において\(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})\)を\(-\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})\)とすれば良いので、前者のみを示します。
証明
まずは示したいことを明確にしましょう。
結論は、
$$\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$$
です。
ここで、定理1.を使います。
定理1.により、
$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{x})\pm g_1(\boldsymbol{x})\\
f_2(\boldsymbol{x})\pm g_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots\\
f_m(\boldsymbol{x})\pm g_m(\boldsymbol{x})
\end{array}
\right)=\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(f_1(\boldsymbol{x})+g_1(\boldsymbol{x}))\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(f_2(\boldsymbol{x})+g_2(\boldsymbol{x}))\\
\vdots\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(f_m(\boldsymbol{x})+g_m(\boldsymbol{x}))\end{array}
\right)
$$
です。
従って、
$$(\forall i\in\mathbb{N}:1\leq i\leq m)\ \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(f_i(\boldsymbol{x})+g_i(\boldsymbol{x}))=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_i(\boldsymbol{x})+\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_i(\boldsymbol{x})$$
が成り立てば、証明が終わります。
従って、示したいことは、
$$(\forall i\in\mathbb{N}:1\leq i\leq m)(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\\(\forall x\in\bar{\Omega}:0< |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\Rightarrow |(f_i(\boldsymbol{x})+g_i(\boldsymbol{x}))-(A_i+B_i)|<\epsilon)$$
です。
これは実は1変数実数値関数のときと9割ほど同じです。
いつもの通り、\(\delta>0\)を見つけたいわけですので、\( |(f_i(\boldsymbol{x})+g_i(\boldsymbol{x}))-(A_i+B_i)|\)を変形してみます。
\begin{eqnarray}
|(f_i(\boldsymbol{x})+g_i(\boldsymbol{x}))-(A_i+B_i)|&=&|(f_i(\boldsymbol{x})-A_i)+(B_i-g_i(\boldsymbol{x}))|\\
&\leq&|f_i(\boldsymbol{x})-A_i|+|B_i-g_i(\boldsymbol{x})|
\end{eqnarray}
です。
(※\(f_i(\boldsymbol{x}),\ A_i,\ B_i,\ g_i(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}\))
ここで、\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\)かつ\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{B}\)ですので、再度定理1.を使うことで、
$$(\forall i\in\mathbb{N}:1\leq i\leq m)\ \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_i(\boldsymbol{x})=A_i,\ \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_i(\boldsymbol{x})=B_i$$
が成り立っています。
従って、
$$(\forall \epsilon_f>0)(\exists \delta_f>0)\ {\rm s.t.}(\forall x\in\bar{\Omega}:0< |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_f\Rightarrow |(f_i(\boldsymbol{x})-A_i|<\epsilon_f)\\
(\forall \epsilon_g>0)(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}(\forall x\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_g\Rightarrow |(g_i(\boldsymbol{x})-B_i|<\epsilon_g)
$$
です。
\(\epsilon_f>0\)と\(\epsilon_g>0\)は任意ですので、任意の\(\epsilon>0\)を用いて
$$\epsilon_f=\epsilon_g=\frac{\epsilon}{2}$$
としても成り立ちます。
従って、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta_f>0)\ {\rm s.t.}\left(\forall x\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_f\Rightarrow |(f_i(\boldsymbol{x})-A_i|<\frac{\epsilon}{2}\right)\\
(\forall \epsilon>0)(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}\left(\forall x\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_g\Rightarrow |(g_i(\boldsymbol{x})-B_i|<\frac{\epsilon}{2}\right)
$$
が成り立ちます。
ここで、\(\delta=\min(\delta_f,\delta_g)\)とすれば、\(0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\)を満たす任意の\(\boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}\)に対して、
\begin{eqnarray}
|(f_i(\boldsymbol{x})+g_i(\boldsymbol{x}))-(A_i+B_i)|&\leq&|f_i(\boldsymbol{x})-A_i|+|B_i-g_i(\boldsymbol{x})|\\
&<&\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon
\end{eqnarray}
です。
故に、
$$(\forall i\in\mathbb{N}:1\leq i\leq m)(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\\(\forall x\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\Rightarrow |(f_i(\boldsymbol{x})+g_i(\boldsymbol{x}))-(A_i+B_i)|<\epsilon)$$
です。
以上のことから
$$\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$$
です。
証明終わり
本当に成り立つのかネ?
「本当に成り立つのかネ?」と言われたら「証明したので成り立ちますよ、局長。」と言いたいところですが、例を挙げてみましょう。
例2. \(\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2\)と\(\boldsymbol{g}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2\)が
$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\left(
\begin{array}{c}
x \\
-y\\
\end{array}\right),\quad
\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=\left(
\begin{array}{c}
y \\
x\\
\end{array}\right)
$$
で定められているとします。
このとき、
$$\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=
\left(\begin{array}{c} 2\\ 0\\ \end{array}\right)$$
です。
証明
$$\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=\left(\begin{array}{c} 2\\ 0\\ \end{array}\right)$$
は前回(【解析学の基礎シリーズ】多変数関数編 その2)で証明しています。
従って、
- \(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\left(\begin{array}{c} x\\ -y\\ \end{array}\right)=\left(\begin{array}{c} 1\\ -1\\ \end{array}\right)\),
- \(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\left(\begin{array}{c} y\\ x\\ \end{array}\right)=\left(\begin{array}{c} 1\\ 1\\ \end{array}\right)\)
を示します。
1.について
簡単です。
示したいことは、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\left(\forall x\in\mathbb{R}^2:0< |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_f\Rightarrow \left|\left(\begin{array}{c} x\\ -y\\ \end{array}\right)-\left(\begin{array}{c} 1\\ -1\\ \end{array}\right)\right|<\epsilon\right)$$
です。
\(\delta=\epsilon\)とすれば、
$$
\left|\left(\begin{array}{c} x\\ -y\\ \end{array}\right)-\left(\begin{array}{c} 1\\ -1\\ \end{array}\right)\right|=\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}<\delta=\epsilon
$$
です。
2.について
1.と同じです。
示したいことは、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\left(\forall x\in\mathbb{R}^2:0< |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_f\Rightarrow \left|\left(\begin{array}{c} y\\ x\\ \end{array}\right)-\left(\begin{array}{c} 1\\ 1\\ \end{array}\right)\right|<\epsilon\right)$$
です。
\(\delta=\epsilon\)とすれば、
$$
\left|\left(\begin{array}{c} y\\ x\\ \end{array}\right)-\left(\begin{array}{c} 1\\ 1\\ \end{array}\right)\right|=\sqrt{(y-1)^2+(x-1)^2}<\delta=\epsilon
$$
です。
従って、
$$\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))=\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=
\left(\begin{array}{c} 2\\ 0\\ \end{array}\right)$$
です。
結
今回は多変数ベクトル値関数の和、差の極限が極限の和、差と一致するという定理を証明しました。
1変数実数値関数のときと何ら変わらず証明ができました。
ただ、若干違ったのは、変数が多変数になった部分です。
しかし、多変数になったとしても、成分の極限に帰着できるので、結局は実数値関数のお話に帰着できました。
次回は積と商の極限について解説します。
※4/30,5/1はお休みします。
乞うご期待!質問、コメントなどお待ちしております!
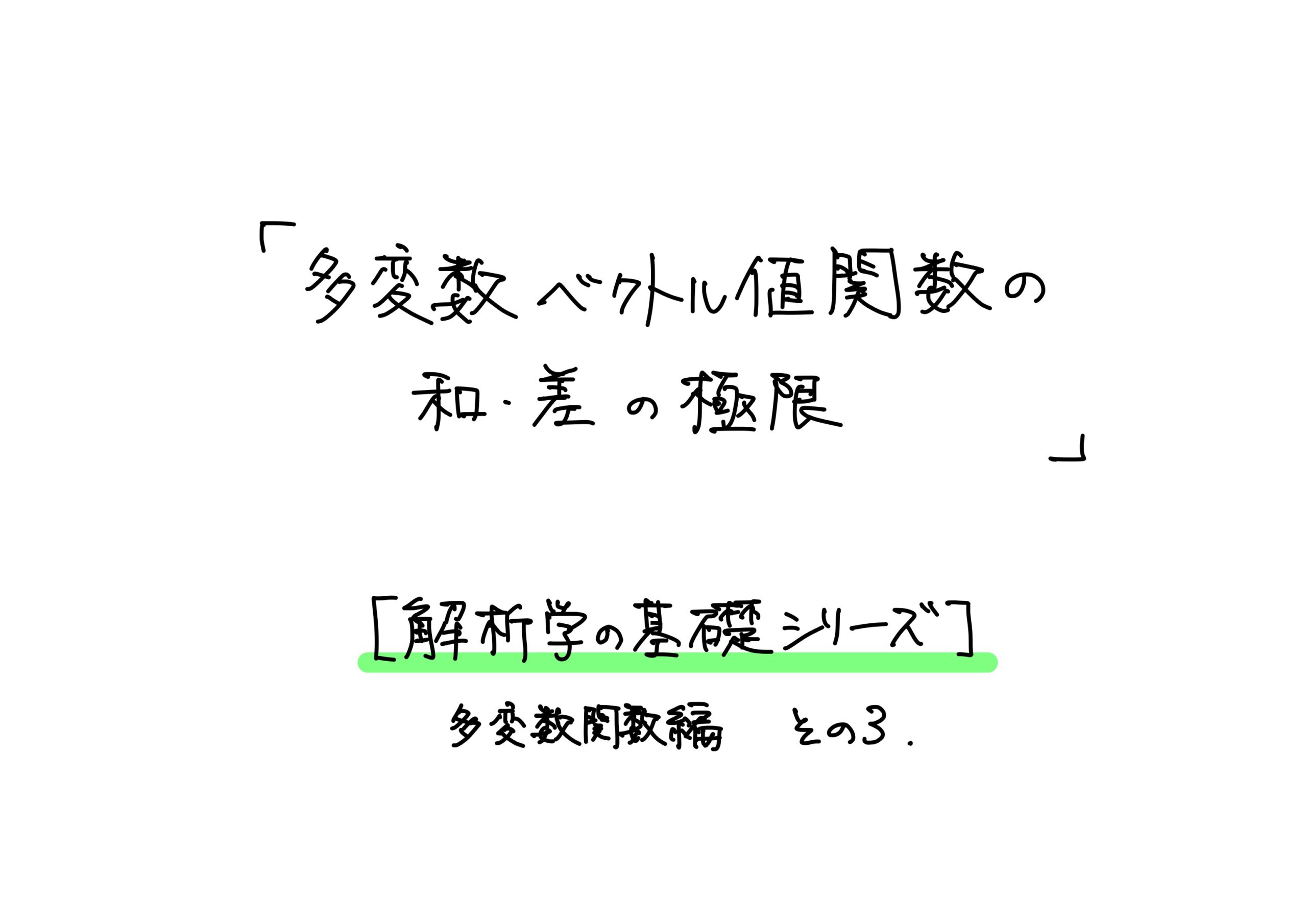




コメントをする