本記事の内容
本記事は逆関数の微分法、および微分の記法についての注意と小咄の記事です。
本記事を読むにあたり、微分係数と導関数と合成関数の微分について知っている必要があるため、その際は以下の記事を参照してください。
逆関数の微分法を考えるのはなぜかネ?
通常、関数というのは\(y=f(x)\)の形をしています。
これについて「\(f^\prime(x)\)を求めなさい」と言われたらば、「はいはい、OKです。」となるわけですが、必ずしもそうはいきません。
つまり、\(x=g(y)\)みたいな形の関数だって出てくるわけです。
「この\(x=g(y)\)を\(x\)について微分しなさい」と言われたらどうしましょうか。
「んなもん、\(y=\)の形に直して微分すりゃいいじゃんか」と思うかもしれません。
確かに、\(x=2y\)みたいな簡単な関数だったらそれでOKです。
しかし、\(x=\sin y\)だっただらどうでしょうか。
「んなもん、\(y=\arcsin x\)に直して…あれ?\(y\)についての微分だったら、高校数学でやったしわかるけど…」となるのではないでしょうか(後の記事で\(\sin x\)の微分についてもちゃんと解説しますので知らなくてもOKです)。
こういうときに逆関数の微分法を使うのです。
\(y=\arcsin x\)の微分については後の記事で解説します。
このように、\(x=g(y)\)で、\(x\)について微分したくても、\(y=\)の形に簡単に直せないような関数に対して逆関数の微分法が有用なのです。
逆関数の微分法の明示
では、早速逆関数の微分法について明示しましょう。
ここで少し言及しておくと、写像\(f\)に逆写像\(f^{-1}\)が存在することと、\(f\)が全単射であることは同値(必要十分条件)でした。
詳しくは、【論理と集合シリーズ】写像編 その8、およびその9を参照してください。
では、証明に行きましょう!
全単射とはどういう写像だったかを思い出せば一瞬です。
証明
\(I,\ J\in\mathbb{R}\)を\(\mathbb{R}\)の開区間、\(\varphi:I\to J\)は全単射、\(\varphi^{-1}:J\to I\)は\(\varphi\)の逆写像とします。
また、\(\varphi,\ \varphi^{-1}\)がそれぞれ\(a\in I\)、\(b=\varphi^{-1}(a)\in J\)で微分可能としましょう。
このとき、\(\varphi^{-1}\)は\(\varphi\)の逆写像ですので、
$$
\varphi^{-1}\left( \varphi(a)\right)=a,\quad \varphi\left( \varphi^{-1}(b)\right)=b
$$
が成り立ちます。
これらの両辺をそれぞれ\(x\)、\(y\)で微分します。
このとき、\(\varphi^{-1}\left( \varphi(a)\right),\ \varphi\left( \varphi^{-1}(b)\right)\)はそれぞれ合成関数であることに注意します。
合成関数の微分は
でした。
詳しくは【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その3を御覧ください。
さて、合成関数の微分法を用いると、
$$
\left( \varphi^{-1}\right)^\prime(y)\cdot \varphi^\prime(x)=1,\quad \varphi^\prime(x)\cdot\left( \varphi^{-1}\right)^\prime(y)=1
$$
です。
\(\left( \varphi^{-1}\right)^\prime(y)\)と\(\varphi^\prime(x)\)は掛け算をして\(1\)なのですから、どちらも\(0\)ではありません。
従って、\(\varphi^\prime(x)\neq0\)ですので、
$$
(\varphi^{-1})^\prime(y)=\left( \varphi^\prime(x)\right)^{-1}\left(=\frac{1}{\varphi^\prime(x)} \right)
$$
です。
証明終わり
本当に成り立つのかネ?
成り立ちます。
例1. \(f:(0,2)\to (0,4)\)が、\(y=f(x)=x^2\)で定められているとします。
また、\(g:(0,4)\to (0,2)\)が、\(g(y)=\sqrt{y}\)で定められているとします。
このとき、\(g\)は\(f\)の逆関数です。
\(\displaystyle g^\prime(y)=\frac{1}{2\sqrt{y}}\)です。
実際、
\begin{eqnarray}
\lim_{h\to0}\frac{g(y+h)-g(y)}{h}&=&\lim_{h\to0}\frac{\sqrt{y+h}-\sqrt{y}}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{\left(\sqrt{y+h}-\sqrt{y}\right)\cdot\left(\sqrt{y+h}+\sqrt{y}\right)}{h\cdot\left(\sqrt{y+h}+\sqrt{y}\right)}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{y+h-y}{h\cdot\left(\sqrt{y+h}+\sqrt{y}\right)}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{h}{h\cdot\left(\sqrt{y+h}+\sqrt{y}\right)}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{1}{\sqrt{y+h}+\sqrt{y}}\\
&=&\frac{1}{2\sqrt{y}}
\end{eqnarray}
です。
ここで、\(y=x^2\)ですので、\(\displaystyle g^\prime(y)=\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{2x}\)です。
一方、\(f^\prime(x)=2x\)ですので、\(\displaystyle\frac{1}{f^\prime(x)}=\frac{1}{2x}\)です。
高階導関数
一言で言ってしまえば、「何回も微分した導関数のこと」です。
「なぜ必要なのかネ?」と思うかもしれませんが、1回だけだと関数の形を知るのには情報量が足りないからです。
微分係数の記事の図のように視覚的にわかるので、それで説明します。
微分係数が正のときは、その点(瞬間)で増加しています。
(実は、これは定理として後にしっかり証明します。ちなみに、証明には平均値の定理という定理を使います。)

しかしながら、あくまでこれは「増加している」ということしかわかりません。
どのように増加してるのかはわからないのです。

微分係数はその瞬間(点)の変化量のことでした。
つまり、微分係数の微分係数はその瞬間の変化量の変化量なので、ある瞬間の接線の傾きの変化量のことを指します。
仮に、一度微分したときの微分係数が正だったとしましょう。
微分係数の微分係数を考えることで、「段々と緩やかになりながらも増えているのか」、それとも「まだまだ急激に増えているのか」という「増え方」がわかるのです。

このように、関数の形をより詳しく知りたいときに何度も微分したりします。
また、拡散方程式などの現象の数理モデルでも出てきます。
以下、機能的に\(f\)の\(k\)階導関数\(f^{(k)}\)が定まる。
例えば、例1.の\(f(x)=x^2\)の微分は\(f^\prime(x)=2x\)で、\(f^{\prime\prime}(x)=2\)で、\(f^{(3)}(x)=0\)です。
結
今回は、逆関数の微分法、高階導関数について解説しました。
逆関数の微分法は、平たく言えば、\(y=f(x)\)の逆関数\(g(y)=x\)を\(y\)について微分して、その逆数をとれば、\(f\)の微分が求まるよ、ということです。
高階導関数については、導関数が微分可能ならばもう一階微分できるよね?
\(k\)階やったらその導関数を\(f^{(k)}\)と書こうぜ、という話です。
次回は、初等関数、特に多項式関数と指数関数と対数関数の微分について解説します。
乞うご期待!
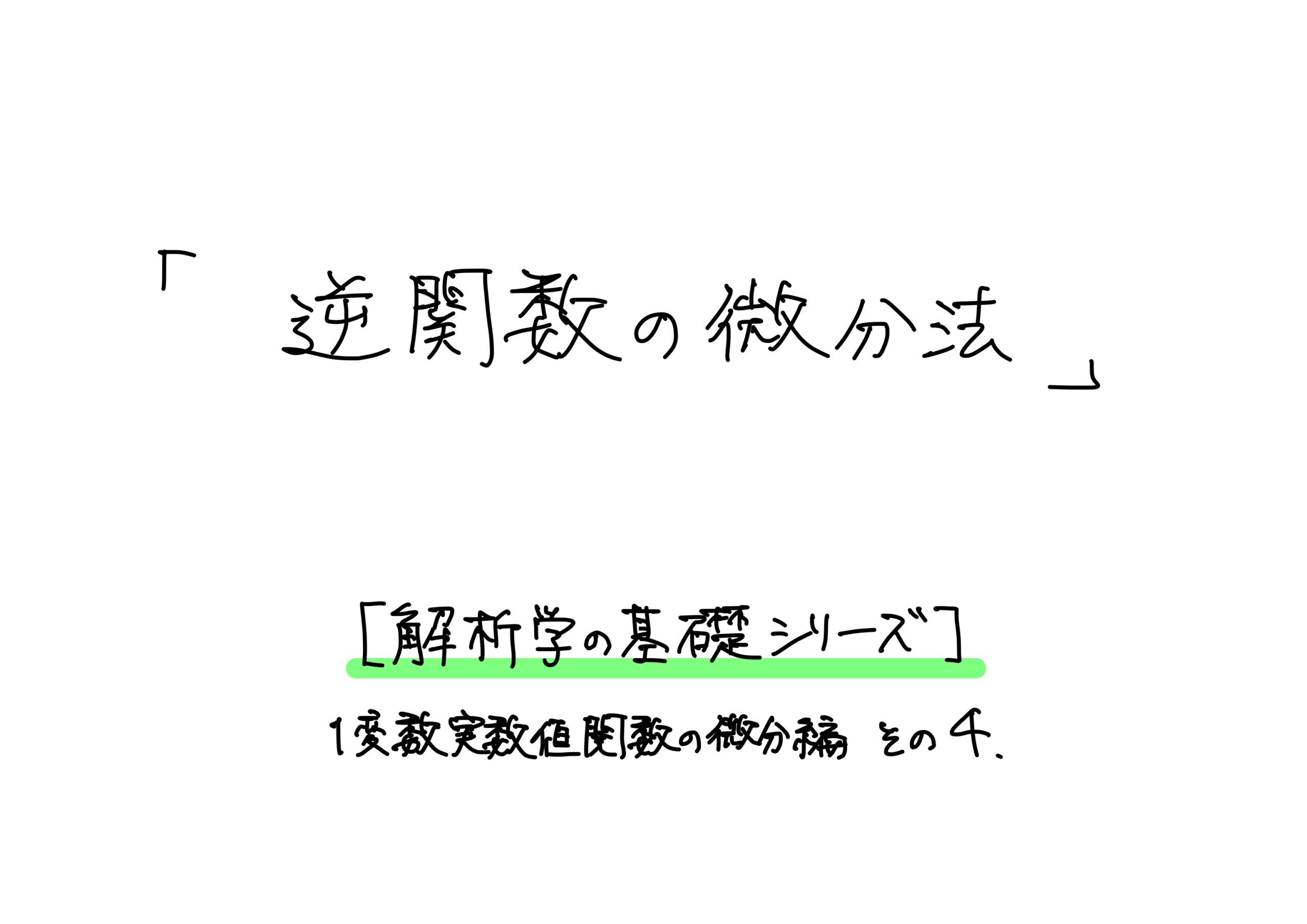



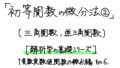
コメントをする