本記事の内容
本記事は多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限、多変数ベクトル値関数同士の内積の極限について解説する記事です。
本記事を読むに当たり、多変数ベクトル値関数の極限について知っている必要があるため、その際は以下の記事を参照してください。
では行きましょう!
多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限
前回(【解析学の基礎シリーズ】多変数関数編 その3)で和、差について解説しました。
今回は積について解説します。
点列のとき同様に、多変数ベクトル値関数の値はベクトルですので、単純に掛け算をすることはできません。
従って、今回は代表的な積、実数値関数とベクトル値関数の積と内積の極限について解説します。
まずは多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限です。
「ベクトルになったら難しいのかな?」と身構えてしまうかもしれませんが、なんてことありません。
というのも、1変数実数値関数の場合とほとんど同じだからです。
早速主張を明示してしまいましょう。
多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限の証明
では、証明に入っていきます。
まずは何を示せばよいのか、ということを明示するために式変形してみましょう。
\begin{eqnarray}
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})
\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{x})\\
f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right)=
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}
\left(
\begin{array}{c}
g(\boldsymbol{x})f_1(\boldsymbol{x})\\
g(\boldsymbol{x})f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
g(\boldsymbol{x})f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right)
\end{eqnarray}
です。
ここで、以下の定理を使います。
この定理の証明は【解析学の基礎シリーズ】多変数関数編 その2を御覧ください。
この定理(多変数ベクトル値関数の収束と同値な命題)を使うと、
$$
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}
\left(
\begin{array}{c}
g(\boldsymbol{x})f_1(\boldsymbol{x})\\
g(\boldsymbol{x})f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
g(\boldsymbol{x})f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right)=
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})f_1(\boldsymbol{x})\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right)
$$
です。
従って、\(1\leq i\leq m\)を満たす任意の\(i\in\mathbb{N}\)に対して、
$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})f_i(\boldsymbol{x})=\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x}) \right)\cdot\left( \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_i(\boldsymbol{x})\right)$$
であれば、再度定理(多変数ベクトル値関数の収束と同値な命題)を使うことによって、
$$
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})f_1(\boldsymbol{x})\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right)=
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})\right)\cdot\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})\right)\\
\displaystyle\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})\right)\cdot\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})\right)\\
\vdots \\
\displaystyle\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})\right)\cdot\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x})\right)\\
\end{array}\right)=
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})\cdot\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}
\left(\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{x})\\
f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right)
$$
となり、多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限が成り立ちます。
従って、\(1\leq i\leq m\)を満たす任意の\(i\in\mathbb{N}\)に対して、
$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})f_i(\boldsymbol{x})=\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x}) \right)\cdot\left( \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_i(\boldsymbol{x})\right)$$
を、すなわち、
$$(\forall i\in\mathbb{N}:1\leq i\leq m)(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\Rightarrow |g(\boldsymbol{x})f_i(\boldsymbol{x})-BA_i|<\epsilon)$$
を示せば良い事になります。
これを示しましょう。
補題1.の証明
これは実は1変数実数値関数の積の極限の証明とほぼ同じです。
(形式的にま全く同じと言ってもいいかもしれません。)
示したいことは、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\Rightarrow |g(\boldsymbol{x})f(\boldsymbol{x})-BA|<\epsilon)$$
です。
いつもの通り、\(\delta>0\)を見つけるために、\( |g(\boldsymbol{x})f(\boldsymbol{x})-BA|\)を変形してみましょう。
\begin{eqnarray}
|g(\boldsymbol{x})f(\boldsymbol{x})-BA|&=&|g(\boldsymbol{x})f(\boldsymbol{x})-BA-g(\boldsymbol{x})A+g(\boldsymbol{x})A|\\
&=&|g(\boldsymbol{x})(f(\boldsymbol{x})-A)+A(g(\boldsymbol{x})-B)|\\
&\leq&|g(\boldsymbol{x})|\cdot|f(\boldsymbol{x})-A|+|A|\cdot|g(\boldsymbol{x})-B|
\end{eqnarray}
です。
今、\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f(\boldsymbol{x})=A\)、\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g(\boldsymbol{x})=B\)が成り立っているので、
- \(\displaystyle(\forall \epsilon_f>0)(\exists \delta_f>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_f\Rightarrow |f(\boldsymbol{x})-A|<\epsilon_f)\)
- \(\displaystyle(\forall \epsilon_g>0)(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_g\Rightarrow |g(\boldsymbol{x})-B|<\epsilon_g)\)
が成り立っています。
従って、\(|g|\)が有界であれば、\(\epsilon_f\)と\(\epsilon_g\)を帳尻合わせるだけれおしまいです。
(1変数実数値関数のときと同じだネ)
この\(|g|\)は有界です。
1変数実数値関数のときと同じように証明できます。
実際、2.が成り立っており、\(\epsilon_g>0\)は任意なので、\(\epsilon_g=1\)としても成り立ちます。
故に、
$$(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_g\Rightarrow |g(\boldsymbol{x})-B|<1)$$
が成り立っています。
ここで、\(|g(\boldsymbol{x})|-|B|\leq|g(\boldsymbol{x})-B|\)ですので、\(|g(\boldsymbol{x})|-|B|<1\)です。
従って、\(0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_g\)を満たす\(x\in\bar{\Omega}\)に対して、\(|g(\boldsymbol{x})|<1+|B|\)です。
さて、そもそも
- \(\displaystyle(\forall \epsilon_f>0)(\exists \delta_f>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_f\Rightarrow |f(\boldsymbol{x})-A|<\epsilon_f)\)
- \(\displaystyle(\forall \epsilon_g>0)(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_g\Rightarrow |g(\boldsymbol{x})-B|<\epsilon_g)\)
が成り立っていたのでした。
\(\epsilon_f>0\)と\(\epsilon_g>0\)は任意でしたので、任意の\(\epsilon>0\)を用いて
$$\epsilon_f=\frac{\epsilon}{2(1+|B|)},\ \epsilon_g=\frac{\epsilon}{2|A|}$$
としても成り立ちます。
ここで、\(\delta=\min(\delta_f,\delta_g)\)とすれば、\(0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\)を満たす任意の\(x\in\bar{\Omega}\)に対して、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ \left(\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta_f\Rightarrow\\|f(\boldsymbol{x})-A|<\frac{\epsilon}{2(1+|B|)}\land |g(\boldsymbol{x})-B|<\frac{\epsilon}{2|A|}\right)$$
が成り立ちます。
以上のことから、\(0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\)を満たす任意の\(x\in\bar{\Omega}\)に対して、
\begin{eqnarray}
|g(\boldsymbol{x})f(\boldsymbol{x})-BA|&=&|g(\boldsymbol{x})f(\boldsymbol{x})-BA-g(\boldsymbol{x})A+g(\boldsymbol{x})A|\\
&=&|g(\boldsymbol{x})(f(\boldsymbol{x})-A)+A(g(\boldsymbol{x})-B)|\\
&\leq&|g(\boldsymbol{x})|\cdot|f(\boldsymbol{x})-A|+|A|\cdot|g(\boldsymbol{x})-B|\\
&<&(1+|B|)\cdot\frac{\epsilon}{2(1+|B|)}+|A|\cdot\frac{\epsilon}{2|A|}=\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon
\end{eqnarray}
が成り立ちます。
従って、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\Rightarrow |g(\boldsymbol{x})f(\boldsymbol{x})-BA|<\epsilon)$$
です。
補題1.の証明おわり
補題1.により、多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限が成り立ちます。
多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限の証明終わり
どういうことかネ?
とどのつまり、多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限は、極限の積と一致する、ということです。
高校数学的なノリで言えば、「\(\lim\)はカッコの中に入れて計算してOK」ということです。
この主張の証明にも定理(多変数ベクトル値関数の収束と同値な命題)を使いました。
この定理は「多変数ベクトル値関数の極限はそのベクトルの成分の極限と等しい」ということで、ベクトル値の関数の極限も結局は実数値関数の極限に帰着できるという定理です。
この定理(多変数ベクトル値関数の収束と同値な命題)は色んな所で出現するという意味では基本的かつ強力な定理だと筆者は思います。
多変数ベクトル値関数の内積の極限
この主張の証明は補題1.と多変数ベクトル値関数の極限の和・差の道中で示したこと(【解析学の基礎シリーズ】多変数関数編 その3)から直ちに分かります。
正直「明らかだし証明しなくてよくね?」と思ってしまいますが、筆者は数学を勉強しているときに、この”明らか”という言葉に非常に悩まされた記憶があるので(余談参照)、ちゃんと証明します。
まずは主張を明示してしまいましょう。
先に述べたとおり、この主張の証明は簡単です。
多変数ベクトル値関数の内積の極限の証明
式変形により証明できます。
\begin{eqnarray}
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))&=&
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\left(
\left(\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{x})\\
f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right),
\left(\begin{array}{c}
g_1(\boldsymbol{x})\\
g_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
g_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right)
\right)\\
&=&\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\left(f_1(\boldsymbol{x})g_1(\boldsymbol{x})+f_2(\boldsymbol{x})g_2(\boldsymbol{x})+\cdots+f_m(\boldsymbol{x})g_m(\boldsymbol{x})\right)
\end{eqnarray}
が成り立ちます。
ここで、前回(【解析学の基礎シリーズ】多変数関数編 その3)で証明した以下の事実を使います。
これを使うと、
$$
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\left(f_1(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x})+f_2(\boldsymbol{x})g_2(\boldsymbol{x})+\cdots+f_m(\boldsymbol{x})g_m(\boldsymbol{x})\right)\\
=\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})g_1(\boldsymbol{x})+\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})g_2(\boldsymbol{x})+\cdots+\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x})g_m(\boldsymbol{x})
$$
を得ます。
さらに、補題1.を用いれば、
$$
\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})g_1(\boldsymbol{x})+\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})g_2(\boldsymbol{x})+\cdots+\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x})g_m(\boldsymbol{x})\\
=\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})\right)\cdot\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_1(\boldsymbol{x})\right)+\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})\right)\cdot\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_2(\boldsymbol{x})\right)+\cdots+\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x})\right)\cdot\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_m(\boldsymbol{x})\right)
$$
です。
これはまさに
$$
\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})\right)\cdot\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_1(\boldsymbol{x})\right)+\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})\right)\cdot\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_2(\boldsymbol{x})\right)+\cdots+\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x})\right)\cdot\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_m(\boldsymbol{x})\right)\\
=\left(
\left(\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right),
\left(\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_1(\boldsymbol{x})\\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots \\
\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}g_m(\boldsymbol{x})
\end{array}\right)
\right)
$$
ですから、証明が完了です。
多変数ベクトル値関数の内積の極限の証明おわり
余談(読み飛ばしてOKです)
先に”明らか”という言葉に苦戦したという話をしました。
正直、筆者の個人的な感想ですが”明らか”という言葉は嫌いです。
なぜかと言うと、「ある主張が”明らか”か否かは個人に依ると思うから」です。
確かに、第一線で活躍されている偉大な数学者の方からすると「明らか」なのかもしれませんが、筆者のような凡人には明らかではありません。
「〇〇入門」というような書籍にも”明らか”という単語が出てきたりしますし、「お前、本当に入門させる気あんのか?」と思っています。
筆者の経験ですが、”明らか”と書かれている部分について「本当に”明らか”なんだな?じゃあ調べてみるぞ?」ということで調べた結果、しっかり複雑で「何が”明らか”だ。嘘つきめが!」と憤慨しかけたこともあります。
勿論、書籍なのですから、ページ数やらの関係で”明らか”で済まざるを得ないのかもしれません。
しかし、親切でないことには変わりないと思っています。
故に、このブログのコンセプトの1つとして、「多少証明が長くなっても”明らか”という言葉で済ますことは極力避ける」を掲げています。(少なくとも筆者はそうです。)
本当に成り立つのかネ?
またもや局長が姿を表しました。
例があったほうが説得力があるのは事実なので、「証明したし良くね?」と思う気持ちは抑えます。
例1.\(\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2\)と\(g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}\)が
$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\left(
\begin{array}{c}
x \\
y\\
\end{array}\right),\quad
g(\boldsymbol{x})=x+y
$$
で定められているとします。
このとき、\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}g(\boldsymbol{x}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\)を考えてみましょう。
示したいことは、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta\Rightarrow |x(x+y)-2|<\epsilon\land |y(x+y)-2|<\epsilon)$$
です。
\begin{eqnarray}
|x(x+y)-2|&=&|x(x+y)-2-(x+y)+(x+y)|\\
&=&|(x+y)(x-1)+(x+y-2)|\\
&\leq&|x+y|\cdot|x-1|+|x+y-2|
\end{eqnarray}
です。
今、\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}f(\boldsymbol{x})=(1,1)\)、\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}g(\boldsymbol{x})=2\)が成り立っているので、
- \(\displaystyle(\forall \epsilon_f>0)(\exists \delta_f>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta_f\Rightarrow |x-1|<\epsilon_f)\)
- \(\displaystyle(\forall \epsilon_g>0)(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta_g\Rightarrow |(x+y)-2|<\epsilon_g)\)
が成り立っています。
ここで、2.が成り立っており、\(\epsilon_g>0\)は任意なので、\(\epsilon_g=1\)としても成り立ちます。
故に、
$$(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta_g\Rightarrow |(x+y)-2|<1)$$
が成り立っています。
ここで、\(|x+y|-|2|\leq|x+y-2|\)ですので、\(|x+y|-|2|<1\)です。
従って、\(0<|\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta_g\)を満たす\(x\in\bar{\Omega}\)に対して、\(|x+y|<3\)です。
さて、そもそも
- \(\displaystyle(\forall \epsilon_f>0)(\exists \delta_f>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta_f\Rightarrow |x-1|<\epsilon_f)\)
- \(\displaystyle(\forall \epsilon_g>0)(\exists \delta_g>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta_g\Rightarrow |(x+y)-2|<\epsilon_g)\)
が成り立っていたのでした。
\(\epsilon_f>0\)と\(\epsilon_g>0\)は任意でしたので、任意の\(\epsilon>0\)を用いて
$$\epsilon_f=\frac{\epsilon}{6},\ \epsilon_g=\frac{\epsilon}{2}$$
としても成り立ちます。
ここで、\(\delta=\min(\delta_f,\delta_g)\)とすれば、\(0<|\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta\)を満たす任意の\(x\in\bar{\Omega}\)に対して、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ \left(\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta_f\Rightarrow\\|x-1|<\frac{\epsilon}{6}\land |x+y-2|<\frac{\epsilon}{2}\right)$$
が成り立ちます。
以上のことから、\(0<|\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta\)を満たす任意の\(x\in\bar{\Omega}\)に対して、
\begin{eqnarray}
|x(x+y)-2|&=&|x(x+y)-2-(x+y)+(x+y)|\\
&=&|(x+y)(x-1)+(x+y-2)|\\
&\leq&|x+y|\cdot|x-1|+|x+y-2|
&<&3\cdot\frac{\epsilon}{6}+\frac{\epsilon}{2}=\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon
\end{eqnarray}
が成り立ちます。
従って、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta\Rightarrow |x(x+y)-2|<\epsilon)$$
です。
同様に、
\(0<|\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta\)を満たす任意の\(x\in\bar{\Omega}\)に対して、
\begin{eqnarray}
|y(x+y)-2|&=&|y(x+y)-2-(x+y)+(x+y)|\\
&=&|(x+y)(y-1)+(x+y-2)|\\
&\leq&|x+y|\cdot|y-1|+|x+y-2|
&<&3\cdot\frac{\epsilon}{6}+\frac{\epsilon}{2}=\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon
\end{eqnarray}
が成り立ちます。
従って、
$$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in\bar{\Omega}:0\leq |\boldsymbol{x}-(1,1)|<\delta\Rightarrow |y(x+y)-2|<\epsilon)$$
です。
ここで、\(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\left(\begin{array}{c}x^2+xy\\ y^2+xy\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}2\\ 2\end{array}\right)\)ですので、確かに多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限が成り立っています。
例2. \(\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2\)と\(\boldsymbol{g}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2\)が
$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\left(
\begin{array}{c}
x \\
y\\
\end{array}\right),\quad
\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=\left(
\begin{array}{c}
y \\
x\\
\end{array}\right)
$$
で定められているとします。
このとき、
- \(\displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\left(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))\right)=\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}2xy=2\),
- \(\displaystyle\left( \lim_{\boldsymbol{x}\to(x)}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}),\lim_{\boldsymbol{x}\to(1,1)}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})\right)=\left( \left(\begin{array}{c}1\\ 1\\\end{array}\right),\left(\begin{array}{c}1\\ 1\\\end{array}\right)\right)=2\)
ですので、たしかに多変数ベクトル値関数の内積の極限が成り立ちます。
結
今回は、多変数ベクトル値関数と実数値関数の積の極限、多変数ベクトル値関数の内積の極限について解説しました。
結局の所、成分で考えればなんてことない話で、高校数学的なノリで言えば、「積についてもカッコの中に\(\lim\)を入れて計算してOK」ということです。
次回は外積の極限について解説します。
乞うご期待!質問、コメントなどお待ちしております!
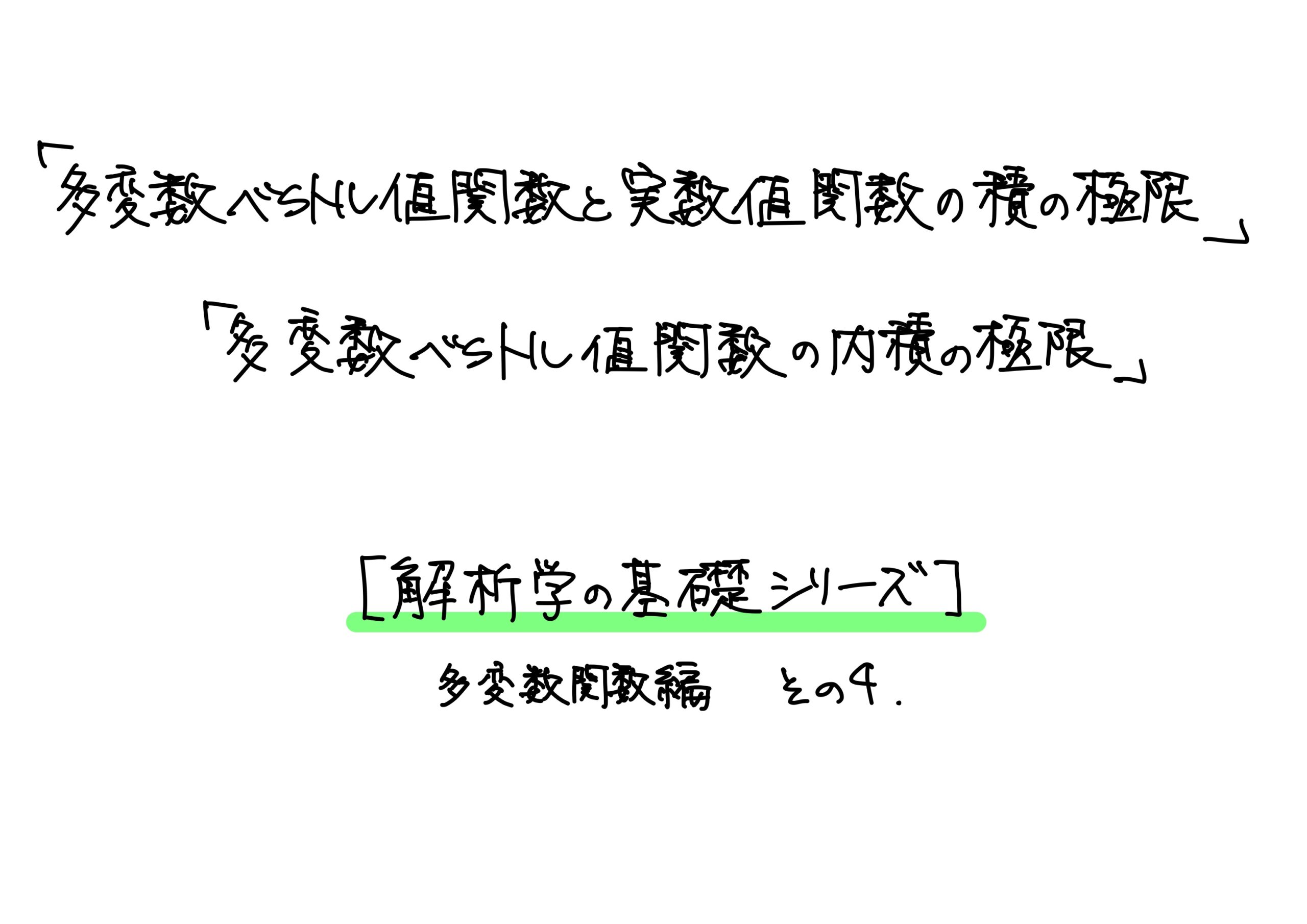



コメントをする