本記事の内容
本記事は1変数の微分積分学の基本定理を解説する記事です。
本記事を読むにあたり、不定積分、原始関数について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。
本記事を書く理由(前回と主旨は同じですので読み飛ばしてOKです)
本記事と前回と次回(厳密には次次回)の目標は「積分について、高校数学で計算方法は習ったけど、なぜその計算方法で良かったのか」ということに回答し、読者の方々に理解していただくことです。
「なぜ高校数学で習った計算方法で良かったのか」ということに一言で回答するなら、
です。
その微分積分学の基本定理を今回は解説、証明します。
さて、「”高校数学で習って、当然のように計算していたこと”って何?」ということの例を挙げます。
例えば、定積分は
$$
\int_0^1x\ dx=\left[ \frac{1}{2}x^2\right]_0^1=\frac{1}{2}(1^2-0^2)=\frac{1}{2}(1-0)=\frac{1}{2}
$$
というように計算することを高校で習ったと思います。
これです。
実は、この計算方法が良いのは微分積分学の基本定理の系(次次回に解説します)が成り立つからですが、大本は微分積分学の基本定理です。
微分積分学の基本定理って何ですか?
では、本題に入っていきます。
微分積分学の基本定理を一言で
前回もサラッと述べましたが、1次元の微分積分学の基本定理を一言でいうと、
ということです。
ものすごく平たく言うと、関数を微分した後に積分すると、元の関数に戻る、ということです。
裏の裏は表、といった具合でしょうか。
その表現を用いれば、微分と積分それぞれ表と裏の関係にある、と言いかえることも出来るでしょう。
微分積分学の基本定理の明示
では、主張を数学的に明示します。
定理0.(微分積分学の基本定理)
\(I\)を\(\mathbb{R}\)の有界閉区間、\(f\)を\(I\)上の実数値関数、すなわち\(f:I\to\mathbb{R}\)とする。このとき以下の2つが成り立つ。- \(f\)が\(I\)で微分可能で、導関数\(f^\prime\)が\(I\)上で可積分(例えば、連続)ならば、任意の\(a,b\in I\)に対して $$ \int_a^bf^\prime(x)\ dx=f(b)-f(a)\cdots① $$ が成り立つ。
- \(f\)が\(I\)上で可積分で、1点\(x\in I\)で連続ならば、\(f\)の不定積分\(\displaystyle F(x)=\int_a^xf(y)\ dy\)は\(x\)で微分可能で、\(F^\prime(x)=f(x)\)が成り立つ。
確かに、
$$
\int_0^1x\ dx=\left[ \frac{1}{2}x^2\right]_0^1=\frac{1}{2}(1^2-0^2)=\frac{1}{2}(1-0)=\frac{1}{2}
$$
という計算方法が正しいと言っている、ということが見て取れると思います(詳しくは次回)。
ちなみに、定理の主張で「(例えば、連続)」というように書いたのは、閉区間で連続ならば可積分だからです(詳しくは【解析学の基礎シリーズ】積分編 その12を御覧ください)。
微分積分学の基本定理の証明
では、いよいよ証明に入ります。
定理0.(微分積分学の基本定理)の証明
\(I=[a,b]\)とします。
(1.の証明)
今、\(a>b\)、\(a=b\)、\(a<b\)の場合について考察する必要がありますが、\(a>b\)と\(a<b\)の場合は\(a\)と\(b\)の役割を交換するだけですので本質的に違いは有りません。
従って、\(a<b\)と\(a=b\)の場合を証明します。
まずは、\(a<b\)の場合を考えます。
\(I\)の任意の分割を
$$
\Delta:a=x_0<x_1<\dots<x_n=b
$$
とします。
ここで、平均値の定理を使います。
定理1.(平均値の定理)
\(f:[a,b]\to\mathbb{R}\)は連続で、\((a,b)\)で微分可能であるとする。このとき、 $$ (\exists c\in(a,b))\ {\rm s.t.}\ \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f^\prime(c) $$ である。定理1.の証明は【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その8を御覧ください。
平均値の定理から、
$$
f(x_k)-f(x_{k-1})=f^\prime(\xi_k)(x_k-x_{k-1})\quad (1\leq k\leq n)
$$
を満たすような\(\xi_k\in(x_{k-1},x_k)\)が存在します。
この\(\xi_k\)を\(I_k=[x_{k-1},x_k]\)の代表点とする\(f^\prime\)のリーマン和は
\begin{eqnarray}
s\left(f^\prime;\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)&=&\sum_{k\in K(\Delta)}f^\prime\left( \xi_k\right)v\left( I_k\right)\\
&=&\sum_{k=1}^nf^\prime(\xi_k)(x_k-x_{k-1})\\
&=&\sum_{k=1}^n\left[f(x_k)-f(x_{k-1}) \right]\\
&=&\left[f(x_1)-f(x_0) \right]+\left[f(x_2)-f(x_1) \right]+\cdots\\
&&\cdots+\left[f(x_{n-1})-f(x_{n-2}) \right]+\left[f(x_n)-f(x_{n-1}) \right]\\
&=&f(x_n)-f(x_0)\\
&=&f(b)-f(a)
\end{eqnarray}
となって、リーマン和は\(\Delta\)に依存しない一定の値\(f(b)-f(a)\)になります。
そこで、上記の式の両辺に\(d(\Delta)\to0\)という極限を考えます。
仮定から\(f^\prime\)が可積分だから、
$$
\lim_{d(\Delta)\to0}s\left(f;\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)=\int_a^bf^\prime(x)\ dx
$$
となり、
$$
\lim_{d(\Delta)\to0}\left(f(b)-f(a)\right)=f(b)-f(a)
$$
となるから、
$$
\int_a^bf^\prime(x)\ dx=f(b)-f(a)
$$
が成り立ちます。
\(a=b\)の場合、リーマン和は
\begin{eqnarray}
s\left(f^\prime;\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)&=&\sum_{k=1}^1f^\prime(\xi_k)(x_k-x_{k-1})\\
&=&f^\prime(a)(a-a)=0
\end{eqnarray}
となって、これもまた\(f^\prime\)が可積分であることから、
$$
\lim_{d(\Delta)\to0}s\left(f^\prime;\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)=\int_a^af(x)\ dx
$$
かつ
$$
\lim_{d(\Delta)\to0}0=0
$$
となって、
$$
\int_a^af^\prime(x)\ dx=0
$$
となります。
(2.の証明)
まず、次の事実を使います。
命題2.
\(\mathbb{R}\)の区間\(I\)で関数\(f\)が可積分であるとき、\(I\)の任意の3点\(a,b,c\in I\)に対して、 $$ \int_a^cf(x)\ dx=\int_a^bf(x)\ dx+\int_b^cf(x)\ dx $$ が成り立つ。命題2.の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その13を御覧ください。
命題2.から
\begin{eqnarray}
F(x)-F(y)&=&\int_a^xf(x)\ dx-\int_a^yf(x)\ dx\\
&=&\int_a^yf(x)\ dx+\int_y^xf(x)\ dx-\int_a^yf(x)\ dx\\
&=&\int_y^xf(x)\ dx\cdots②
\end{eqnarray}
です。
また、三角不等式は
$$
\left|\int_a^bf(x)\ dx\right|\leq\left|\int_a^b\left|f(x)\right|\ dx\right|\cdots③
$$
でした。
②と③により、\(h\neq0\)、\(x+h\in I\)のとき、
\begin{eqnarray}
&&\left|\frac{1}{h}\left( F(x+h)-F(x)\right)-f(x)\right|\\
&=&\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h}f(t)\ dt-f(x)\cdot\frac{1}{h}\int_x^{x+h}\ dt\right|\\
&=&\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h}\left( f(t)-f(x)\right) dt\right|\\
&\leq&\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h}\left| f(t)-f(x)\right| dt\right|\\
\end{eqnarray}
となります。
今、\(f\)は\(x\)で連続なので、任意の\(\varepsilon>0\)に対して、\(\delta>0\)が存在して、
$$
(\forall t\in I)\ |t-x|<\delta\Longrightarrow \left|f(t)-f(x)\right|<\varepsilon
$$
が成り立っています。
そこで、\(0<|h|<\delta\)のとき、
$$
\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h}\left| f(t)-f(x)\right| dt\right|\leq \varepsilon
$$
となります。
これはまさに
$$
\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left( F(x+h)-F(x)\right)=f(x)
$$
が成り立つ、ということを意味しています。
すなわち、\(F\)は\(x\)で微分可能で、\(F^\prime(x)=f(x)\)が成り立つ、というわけです。
定理0.(微分積分学の基本定理)の証明終わり
今証明した微分積分学の基本定理の系を次回解説しますが、その系から高校数学で習った計算方法が正しい計算方法であることが保証されます。
次次回に向けてのお話(読み飛ばしてOK)
次次回(次回は1時間チャレンジなので)に向けてのお話をします。
次次回はどういうお話をするかというと、いよいよ高校数学で習った積分の計算方法が正しい計算方法であることを保証する事実を解説します。
また、前回述べた向きのついた積分
向き付きの積分
\(a,b\in \mathbb{R}\)を両端とする1次元の区間上で可積分な関数\(f\)に対して \begin{eqnarray} \int_a^bf(x)\ dx= \begin{cases} \displaystyle\int_{[a,b]}f(x)\ dx&(a\leq b)\\ \displaystyle-\int_{[b,a]}f(x)\ dx&(a> b)\\ \end{cases} \end{eqnarray} とする。が「本当にこのように定めてもいいの?」という話もします。
これらの話は、結局の所今回解説した微分積分学の基本定理が大元にあって、それから得られる事実です。
皆様のコメントを下さい!
筆者はこのブログを角にあたって、図だったりサムネイルだったりというのはiPadで書いています。
研究をする上でもiPadを使っていて、ノートアプリにお世話になっています。
特に最近は筆者の周りの人もiPadで研究をしている人が多いです。
確かに、iPadって有用なんです。
ペンを買う必要もなければ、書いたものがかさばらないし、iPadだけですべて事足りるわけです。
しかしながら、筆者がiPadに書くのはある程度結果がまとまったときに、まとめノートとして書くことが多いです。
なぜなら結局のところ紙とペンが好きだからです。
要するにiPadと紙の二刀流で使っています。
皆様はiPad派ですか?それとも紙とペン派ですか?
是非コメントで教えて下さい!(できれば理由も教えてくれると嬉しいです)
結
今回は、筆者が微分積分を学ぶ上で最も重要だと思っている微分積分学の基本定理(1次元)について解説しました。
微分積分学の基本定理から得られる系により、高校数学で学んだ積分の計算方法が正しい計算方法として保証されます。
リーマン積分はリーマンの極限で定められていますので、極限の”当たり”をつけて、実際に極限であることを\(\varepsilon-\delta\)論法で証明する、というのが正攻法なのですが、微分積分学の基本定理から実は原始関数さえ分かってしまえば積分の値が直ちに求まる、ということが分かります。
次回は1時間チャレンジです!
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。
もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。
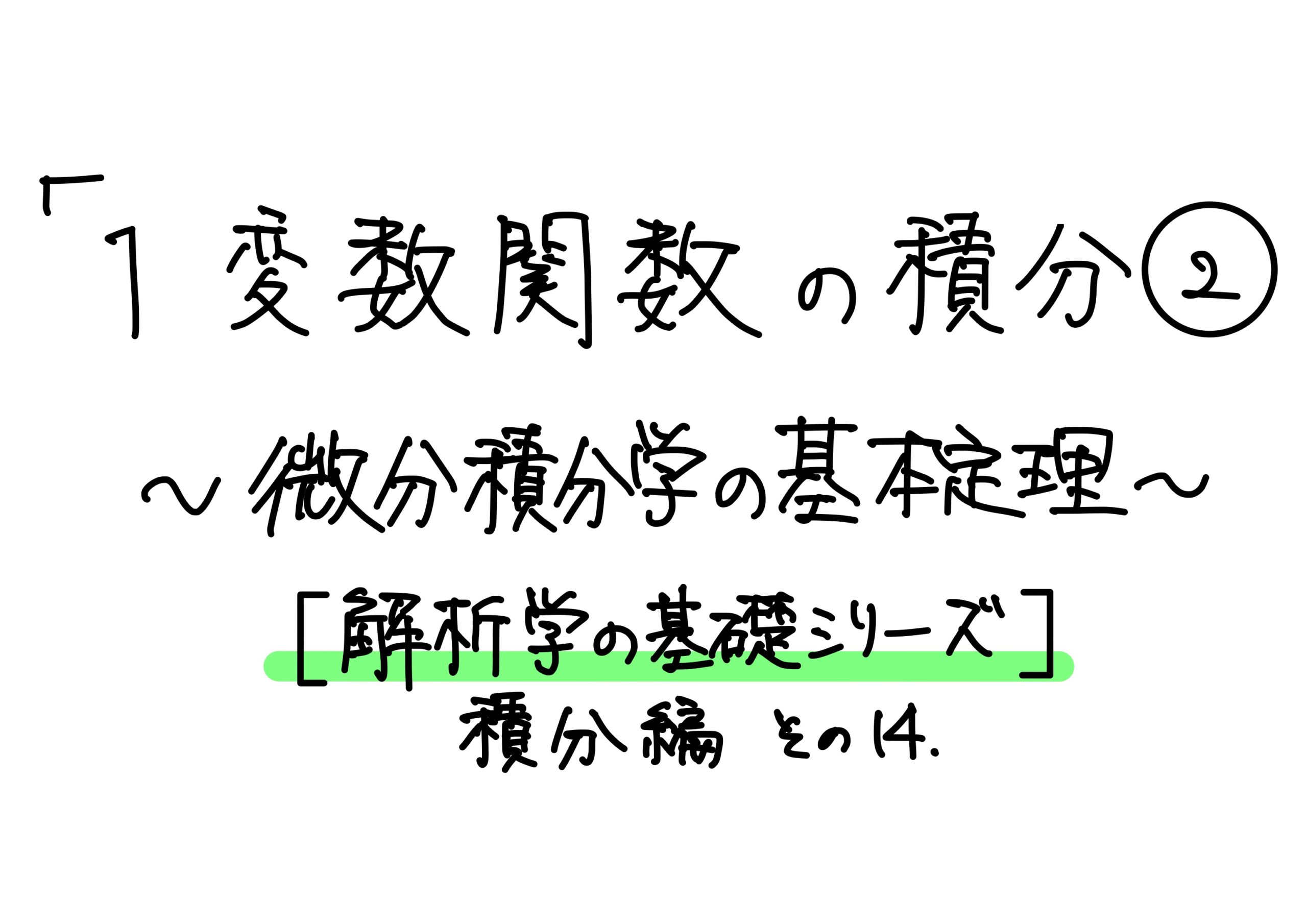
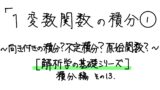


コメントをする