本記事の内容
本記事は、1変数関数の積分について、特に定積分、不定積分、原始関数について解説する記事です。
本記事を読むにあたり、積分について知っている必要があるので、以下の記事も合わせてご覧ください。
本記事を書く理由
「なぜわざわざ1次元の場合に着目するの?」と思われるかもしれません。
確かに、一般の\(n\)次元の閉集合を定義域に持つベクトル値関数について語れば、勿論1次元の場合も含んでいるわけですので、それでOKです。
では、何のためにわざわざ1次元の話をするのか?というと「高校数学で習って、当然のように計算していたことを厳密に証明するため」です。
これをもう少ししっかり言うと
ということです。
さて、「”高校数学で習って、当然のように計算していたこと”って何?」ということの例を挙げます。
例えば、定積分は
$$
\int_0^1x\ dx=\left[ \frac{1}{2}x^2\right]_0^1=\frac{1}{2}(1^2-0^2)=\frac{1}{2}(1-0)=\frac{1}{2}
$$
というように計算することを高校で習ったと思います。
これはなぜなのか?ということです。
また、定積分に対して不定積分
$$
\int x\ dx=\frac{1}{2}x^2+C
$$
(ただし、\(C\)は積分定数)も習ったと思いますが、そもそも不定積分とは何なのか?とういうことは高校数学では厳密な話はされていなかったと思います(筆者の記憶だと)。
さらに、筆者が個人的に微分積分を学ぶにあたって最も重要だと思う微分積分学の基本定理についても、紹介はされていますが厳密な証明は与えられていません。
というのも、そもそも積分は極限で定められていて、極限が高校数学では厳密に語られていないからです。
ちなみに、微分積分学の基本定理を一言でいうと、
という事実です。
これらを解決するために本記事(と次回、次次回)を書きます。
向き付きの積分
“向き付きの積分”といっても、ある種記法のようなもので、大したことはありません。
高校数学で習ったことでもあるので、復習がてら読んでいただければと思います。
ただ、書き方、言い回しは数学的に厳密に書いていますので「高校数学で習ったことを厳密に書くとこうなるのかあ」ということを意識しながら読んでいただけると嬉しいです。
余談
向き付きの積分って何ですか?
向き付きの積分
\(a,b\in \mathbb{R}\)を両端とする1次元の区間上で可積分な関数\(f\)に対して \begin{eqnarray} \int_a^bf(x)\ dx= \begin{cases} \displaystyle\int_{[a,b]}f(x)\ dx&(a\leq b)\\ \displaystyle-\int_{[b,a]}f(x)\ dx&(a> b)\\ \end{cases} \end{eqnarray} とする。これは「このように定める」という話です。
しかし、「”定める”って言ったって、本当にそれでいいの?」となると思います。
良いんです。
なぜなら、次次回に解説する微分積分学の基本定理が成り立つからです。
さて、このことから、
が成り立ちます。
要するに、向き付きの積分を上記のように定めることで、積分する区間を逆にしたらば、積分の値は負になり、1点での積分は\(0\)となる、というわけです。
向き付きの積分に対する注意
向き付きの積分においては、積分の単調性と三角不等式がそのまま成り立つというわけではありません。
積分の単調性についての注意
向き付きの積分については、積分の単調性は一般には成り立ちません。
つまり、\(a>b\)のとき、
$$
f\geq g\Longrightarrow \int_a^bf(x)\ dx\leq \int_a^bg(x)\ dx
$$
が成り立ちます。
ちなみに、積分の単調性とは以下でした。
定理1.(積分の単調性)
\(f,g\)が\(I\)上で可積分で、 $$ (\forall \boldsymbol{x}\in I)\ f(\boldsymbol{x})\geq g(\boldsymbol{x}) $$ が成り立つならば、 $$ \int_If(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\geq \int_Ig(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} $$ が成り立つ。定理1.の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その2を御覧ください。
実際、\(a>b\)であれば、積分の単調性から
\begin{eqnarray}
f\geq g&\Longrightarrow&\int_b^af(x)\ dx\geq \int_b^ag(x)\ dx\\
&\Longleftrightarrow&-\int_a^bf(x)\ dx\geq -\int_a^bg(x)\ dx\\
&\Longleftrightarrow&\int_a^bf(x)\ dx\leq \int_a^bg(x)\ dx\\
\end{eqnarray}
だからです。
積分の三角不等式についての注意
積分の三角不等式についての注意として、絶対値がつきます。
すなわち、
$$
\left|\int_a^bf(x)\ dx\right|\leq\left|\int_a^b\left|f(x)\right|\ dx\right|\cdots②
$$
となります。
\(\displaystyle\int_a^bf(x)\ dx\)という記法が便利なのは、多くの式が\(a,b\)の大小関係に拘らずに同じ形で書けるからです。
その一例が次の命題です。
1次元における積分の加法性
簡単です。
というより、もはや以前解説した積分の区間に関する加法性に対して1次元に着もした、という単にそれだけです。
命題2.
\(\mathbb{R}\)の区間\(I\)で関数\(f\)が可積分であるとき、\(I\)の任意の3点\(a,b,c\in I\)に対して、 $$ \int_a^cf(x)\ dx=\int_a^bf(x)\ dx+\int_b^cf(x)\ dx $$ が成り立つ。命題2.の証明
これはもはやほぼ証明が終わっています。
なぜなら次の積分の区間に関する加法性を既に証明しているからです。
定理3.(区間に関する加法性)
\(\Delta\)を\(\mathbb{R}^n\)の有界閉集合\(I\)の任意の分割とし、\(f\)を\(I\)上の有界な関数とする。\(f\)が\(I\)上で可積分ならば、全ての\(k\in K(\Delta)\)に対し、\(f\)は\(I_k\)上で可積分で $$ \int_If(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}=\sum_{k\in K(\Delta)}\int_{I_k}f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} $$ が成り立つ。逆に、\(f\)が全ての\(I_k\ (k\in K(\Delta))\)上で可積分ならば、\(f\)は\(I\)上で可積分で①が成り立つ。定理3.の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その3を御覧ください。
さて、\(a,b,c\in I\)に対して一致するものがあれば、①に帰着します。
そこで、\(a,b,c\)が全て相異なる場合を考えます。
もし仮に\(a<b<c\)であれば、これは定理3.そのものです。
また、例えば\(a<c<b\)であれば、これも定理3.から
$$
\int_a^bf(x)\ dx=\int_a^cf(x)\ dx+\int_c^bf(x)\ dx
$$
であり、しかも\(\displaystyle\int_c^bf(x)\ dx=-\int_b^cf(x)\ dx\)だから、移項することで
$$
\int_a^cf(x)\ dx=\int_a^bf(x)\ dx+\int_b^cf(x)\ dx
$$
が得られます。
他の場合も全く同じようにできます。
命題2.の証明終わり
つまり、本質的には定理3.が重要、ということです。
不定積分
次に、不定積分について解説します。
不定積分って何ですか?
「不定積分って何ですか?」ということに一言で答えるなら、「関数ですよ。」です。
イメージでいえば、微分で言うところの導関数に対応すると思います。
導関数は名前に”関数”と書いてあるので「関数なんだね」とすぐ分かりますが、不定積分の名前にはその情報が無いため、若干分かりにくいのかもしれません。
形式的には、積分の積分する区間の値を代入する前の状態が不定積分です(厳密ではないけど、イメージはそんなもんです)。
不定積分
\(I\subset\mathbb{R}\)を1次元の区間とする。関数\(f:I\to\mathbb{R}\)が\(I\)上で可積分であるとき、\(a\in I\)を固定して得られる\(I\)上の関数 $$ F(x)=\int_a^xf(x)\ dx $$ を\(f\)の不定積分という。次に、不定積分について少し踏み込んだ話をします(高校数学では学習していませんが)。
リプシッツ連続
リプシッツ連続を一言でいうと、
です。
「ん?どういうこと?」という感じかもしれませんが、一様連続のイメージは「ある\(\delta>0\)が存在して、その\(\delta\)よりも小さい距離にある定義域の要素に対する\(f\)の変化量が全て\(0\)に近づく」ということでした(詳しくは【解析学の基礎シリーズ】積分編 その11を御覧ください)。
すこし復習すると、区間\([a-\delta,a+\delta]\)という区間に対して、\(f(a+\delta)-f(a-\delta)\)が\(0\)に近づく、ということです。
リプシッツ連続は、その「\(f\)の変化量の\(0\)への近づき方に制限を設けている」という状況です。
では、厳密に書きます。
リプシッツ連続
\(A\subset\mathbb{R}^n\)、\(\boldsymbol{f}:A\to\mathbb{R}^m\)とする。このとき、 $$ (\exists L\geq0)\ {\rm s.t.}\ \left[(\forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in I)\left\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})\right\|\leq L\left\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\right\|\right] $$ を満たすならば、\(\boldsymbol{f}\)は\(A\)でリプシッツ連続(Lipschitz continuity)という。直感的には「適当な有限値の実数が存在して、その函数のグラフ上の任意の二点を結ぶ直線の傾きの絶対値はその実数を超えない。」ということです。
さて、どうしてこれが一様連続と関係があるのか、というと以下が成り立つからです。
定理4.
\(A\subset\mathbb{R}^n\)として、\(\boldsymbol{f}:A\to\mathbb{R}^m\)が\(A\)でリプシッツ連続であれば、\(\boldsymbol{f}\)は\(A\)で一様連続である。定理4.の証明
一瞬です。
\(\boldsymbol{f}\)が\(A\)でリプシッツ連続だとします。
つまり、
$$
(\exists L\geq0)\ {\rm s.t.}\ \left[(\forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in I)\left\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})\right\|\leq L\left\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\right\|\right]
$$
だとします。
このとき、示したいのは
$$
(\forall \varepsilon>0)\ (\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall \boldsymbol{x}\in A)\ (\forall \boldsymbol{y}\in A)\ (\left\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\right\|<\delta\Longrightarrow \left\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})\right\|<\varepsilon)
$$
です。
任意の\(\varepsilon>0\)に対して\(\displaystyle\delta=\frac{\varepsilon}{L+1}\)とすると、\(\delta>0\)で、\(\left\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\right\|<\delta\)を満たす任意の\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in I\)に対して
\begin{eqnarray}
\left\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})\right\|&\leq&L\left\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\right\|\\
&\leq&L\cdot \delta\\
&\leq&(L+1)\cdot\delta\\
&=&(L+1)\cdot\frac{\varepsilon}{L+1}=\varepsilon
\end{eqnarray}
となるため、\(\boldsymbol{f}\)は\(A\)で一様連続です。
定理4.の証明終わり
リプシッツ連続な例とリプシッツ連続でない例
例5. \(f:[0,1]\to\mathbb{R}\)を\(f(x)=x\)とすると、\(f\)は\([0,1]\)でリプシッツ連続です。
実際、
$$
\left|f(x)-f(y)\right|=|x-y|\leq1\cdot |x-y|
$$
だからです。
例6. \(I=[0,1]\)、\(g(x)=\sqrt{x}\)とすると、\(g\)は\(I\)でリプシッツ連続ではありません。
実際、仮に、\(g\)がリプシッツ連続だとして、任意の\(n\in\mathbb{N}\)に対して\(\displaystyle a=\frac{1}{n^2},b=0\)とすると、
$$
\left|g(a)-g(b)\right|=\left|\sqrt{\frac{1}{n^2}}-0\right|=\frac{1}{n}
$$
です。
つまり、
$$
\frac{1}{n}\leq L\cdot\frac{1}{n^2}
$$
という\(L\in\mathbb{R}\)が存在することになります。
つまり、\(n\leq L\)という\(L\in\mathbb{R}\)が存在することになりますが、これは\(\mathbb{N}\)が上に有界な集合だ、ということになっていまいますので矛盾です。
余談(リプシッツ連続と微分方程式)
実は、リプシッツ連続は常微分方程式の解の一意性の十分条件です。つまり、「リプシッツ連続ならば常微分方程式の解が一意的に存在する。」という命題が成り立ちます。
不定積分のリプシッツ連続と連続性
不定積分は関数でした。
この不定積分と呼ばれる関数も実は連続である、という意味で結構扱いやすい関数です。
定理7.
\(I\subset\mathbb{R}\)、\(f:I\to\mathbb{R}\)が有界でかつ\(I\)上で可積分であるとする。このとき、\(f\)の不定積分\(F\)は\(I\)上でリプシッツ連続であり、特に\(I\)上で連続である。定理7.の証明
\(f\)は有界なので、
$$
(\exists c\geq0)\ {\rm s.t.}\ (\forall x\in I)\left( \left|f(x)\right|\leq c\right)
$$
です。
命題2.により、任意の\(x,yu\in I\)に対して
\begin{eqnarray}
F(x)-F(y)&=&\int_a^xf(x)\ dx-\int_a^yf(x)\ dx\\
&=&\int_a^yf(x)\ dx+\int_y^xf(x)\ dx-\int_a^yf(x)\ dx\\
&=&\int_y^xf(x)\ dx
\end{eqnarray}
だから、積分の三角不等式②から、
$$
\left|F(x)-F(y)\right|=\left|\int_x^yf(x)\ dx\right|\leq\left|\int_x^y\left|f(x)\right|\ dx\right|\leq c|x-y|
$$
が成り立ちます。
そこで、\(F\)は\(I\)上でリプシッツ連続であり、従って\(I\)上で一様連続です(定理4.)。
従って、また\(f\)は\(I\)上で連続です。
定理7.の証明終わり
原始関数
では本記事の最後として原始関数について解説します。
高校数学では積分を計算するときに「原始関数はこれだから〜」というのは言葉としては意識していないと思いますが(少なくとも筆者はそうでした)、微分積分学の基本定理を語る上では原始関数は重要です。
原始関数
\(I\subset\mathbb{R}\)として、\(f,F\)が\(I\)上で定められた関数とする。\(F\)は\(I\)上で微分可能で $$ (\forall x\in I)\quad F^\prime(x)=f(x) $$ を満たすとき、\(F\)は\(f\)の(\(I\)における)原始関数であるという。さて、\(F\)が\(f\)の\(I\)における原始関数だったとしましょう。
このとき任意の\(C\in\mathbb{R}\)に対して、\(G(x)=F(x)+C\)という関数もまた\(f\)の原始関数です。
実際、「微分が\(0\)であることと定数関数であることは同値」という次の事実が成り立つからです。
定理8.
\(f:[a,b]\to\mathbb{R}\)が連続で、\((a,b)\)で微分可能、任意の\(c\in(a,b)\)に対して\(f^\prime(c)=0\)ならば、\(f\)は定数関数である。逆に、\(f:[a,b]\to\mathbb{R}\)が定数関数であれば、任意の\(c\in(a,b)\)で\(f^\prime(c)=0\)である。さらに、定理8.のおかげで、\(f\)の原始関数は\(F(x)+C\)の形に限る、ということも分かります。
故に、高校では「不定積分では積分定数\(C\)を書かなきゃだめだよ」と習うわけです。
「定数を微分したら\(0\)だから不定積分は積分定数\(C\)を書かないとだめだよ」ということは実は高校ですでに説明がなされていたかもしれません。
しかし、厳密にはその説明では不十分だと思います。
なぜなら、「\(F(x)+C\)以外の形の原始関数が存在しない」ということに言及していないからです。
定理8.は「微分して\(0\)になるのは定数関数だけである。」ことも保証されているので、それではじめて\(f\)の原始関数は\(F(x)+C\)の形に限ることが言えるから、不定積分は\(F(x)+C\)と書かなければならない、という話なのです。
皆様のコメントを下さい!
ツイッターのフォロワーさんと「計算力」についてお話させていただきました。
(偉そうに語ってしまいました…)
私は計算力には単純な計算を早く正確に解く力の他に「眼力」(と勝手に呼んでいます)も含まれると思っています。
どういうことかというと、例えば「1~100までの和を計算しなさい」と言われたときを考えます。
地道に頭から計算することで、答えは得られますし、そのためには正確に和を計算する力が必要だと思います。
しかし、「\(1+99,\ 2+98,\cdots\)」のように計算することで劇的に計算が簡単にかつ正確になります。
これが眼力の例です。
さて、問題は「言われたらそうだけど、思いつかないよ。」ということです。
この眼力はどうやることで鍛えられるのでしょうか。
フォロワーさんは「ある程度の練習と経験則に基づく」とおっしゃっていて、その通りだと思います。
私は「なぜその発想に至ったのかを考えながら問題を解くことで、似たような問題に出会ったときに眼力を発動させることが出来る」と思います。
他にこの「眼力」を鍛える方法があるでしょうか。
皆様のご意見をコメントで教えてくださると嬉しいです。
結
今回は、1変数の積分について注目して解説しました。
特に、向き付きの積分、不定積分、原始関数について解説しました。
どうして積分定数\(C\)を書かなければならないのか、ということについても解説しました。
これらを解説した意図としては微分積分学の基本定理という大定理を示したいがためです。
次回は、いよいよ微分積分学の基本定理を解説します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。
もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。
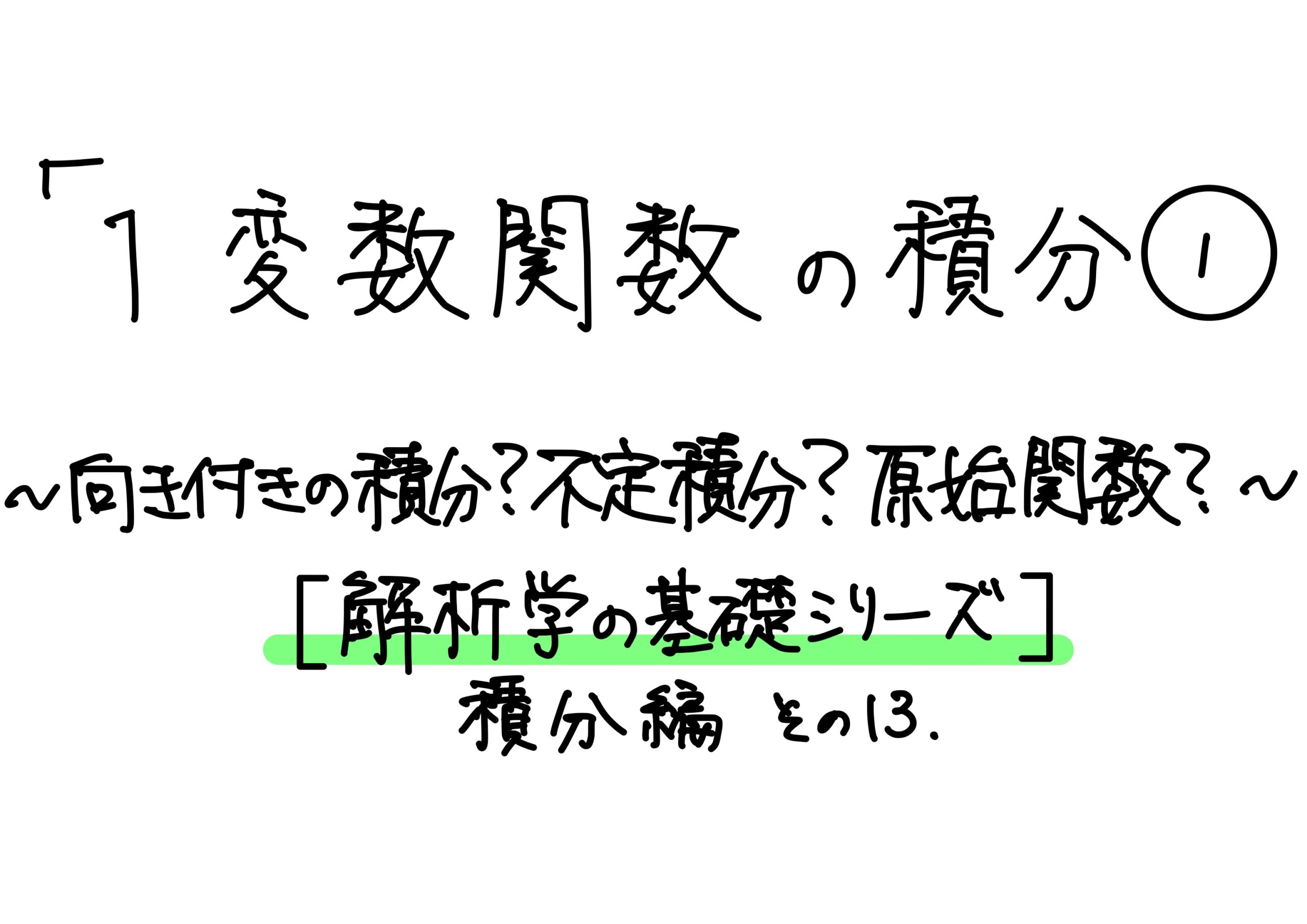
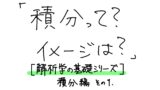
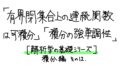
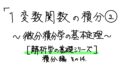
コメントをする