本記事の内容
本記事は、ベクトル値関数の積分について解説する記事です。
本記事を読むにあたり、実数値関数の積分について知っている必要があるため、以下の記事も合わせて御覧ください。
本記事で言いたいこと
ベクトル値関数の積分と言っても、じつは形式的にはなんてことありません。
ベクトル値関数の微分と同じで、ベクトル値関数の積分は成分ごとの積分です。
ということだけ覚えてしまえば、後は基本的に問題はありません。
ベクトル値関数におけるリーマン和
先程、「ベクトル値関数の積分は成分ごとの積分」と述べました。
言いたいことはある種それだけなのですが、形式的に明言しておきます。
形式的なベクトル値関数のリーマン和
ベクトル値関数におけるリーマン和
\(I\subset\mathbb{R}^n\)を有界な閉集合、\(\boldsymbol{f}\)が\(I\)上で定められ、\(\mathbb{R}^m\)の値を取る関数、すなわち\(\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^n\supset I\to \mathbb{R}^m\)としたとき、\(I\)の分割\(\Delta\)に対して、\(\Delta\)により得られる各小区間\(I_k\ (k\in K(\Delta))\)の中から任意に1点\(\boldsymbol{\xi}_k\)(これを\(I_k\)の代表点という)を取って作った和 $$ s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)=\sum_{k\in K(\Delta)}\boldsymbol{f}\left( \boldsymbol{\xi}_k\right)v\left( I_k\right) $$ を\(\boldsymbol{f}\)の\(\Delta\)に関するリーマン和という。これを見ると、「確かに見てくれは実数値関数のときと同じだね」と思っていただけると思いますが、出現する記号にはベクトルと実数が混在しているため、何がベクトルで何が実数なのかが分かりにくいと思います(実数値関数の場合は明快でしたが)。
そこで、先の説明をベクトルの成分の記法を使って、少し書き換えてみます。
ベクトル値関数のリーマン和に出現する各記号について考えてみる
\(I\subset\mathbb{R}^n\)を、\(\mathbb{R}^n\)の有界な閉集合として、\(\boldsymbol{f}:I\to\mathbb{R}^m\)としたとき、任意の\(\boldsymbol{x}\in I\)に対して
$$
\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=
\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{x})\\
f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots\\
f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}
\right)\in \mathbb{R}^m
$$
と書いたとします。
このとき、リーマン和\(s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\)の正体を探ってみます。
\(s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\)の\(\boldsymbol{\xi}\)について
まず、\(s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\)の\(\boldsymbol{\xi}\)は、分割\(\Delta\)により得られる小区間\(I_k\ (k\in K(\Delta))\)の代表点\(\boldsymbol{\xi}_k\)を集めたものです。
厳密には、
$$
\boldsymbol{\xi}=\left( \boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\dots,\boldsymbol{\xi}_k,\dots\right)
$$
です。
ここで、\(\boldsymbol{\xi}_k\in I_k\ (k\in K(\Delta))\)で、かつ\(I_k\subset \mathbb{R}^n\)ですので、\(\boldsymbol{\xi}_k\in \mathbb{R}^n\)だから、\(\boldsymbol{\xi}_k\)は\(n\)次元のベクトルです。
強いて書けば
$$
\boldsymbol{\xi}_k=
\left(
\begin{array}{c}
\xi_{1k}\\
\xi_{2k}\\
\vdots\\
\xi_{nk}\\
\end{array}
\right)\in \mathbb{R}^n
$$
というわけです。
つまり、\(\boldsymbol{\xi}\)はベクトル\(\boldsymbol{\xi}_k\)を集めてきたものなわけですので、\(\boldsymbol{\xi}\)は形式的には行列の風貌をしています。
記号で書けば、
\begin{eqnarray}
\boldsymbol{\xi}&=&\left( \boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\dots,\boldsymbol{\xi}_k,\dots\right)\\
&=&\left(
\left(
\begin{array}{c}
\xi_{11}\\
\xi_{21}\\
\vdots\\
\xi_{n1}\\
\end{array}
\right),
\left(
\begin{array}{c}
\xi_{12}\\
\xi_{22}\\
\vdots\\
\xi_{n2}\\
\end{array}
\right),
\cdots,
\left(
\begin{array}{c}
\xi_{1k}\\
\xi_{2k}\\
\vdots\\
\xi_{nk}\\
\end{array}
\right),
\cdots
\right)
\end{eqnarray}
です(むしろ分かりにくくなってしまったような気もしますが…)。
\(\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}\boldsymbol{f}\left( \boldsymbol{\xi}_k\right)v\left( I_k\right)\)について
次に、\(\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}\boldsymbol{f}\left( \boldsymbol{\xi}_k\right)v\left( I_k\right)\)について見てみます。
この式にはベクトルと実数が混在しています。
まず、この章の最初に述べたように、
$$
\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=
\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{x})\\
f_2(\boldsymbol{x})\\
\vdots\\
f_m(\boldsymbol{x})
\end{array}
\right)\in \mathbb{R}^m
$$
です。
つまり、\(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\)はベクトルです。
そして、\(v(I_k)\)は小区間\(I_k\)の体積ですので、実数です。
すなわち、
$$
\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)=
\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{\xi}_k)\\
f_2(\boldsymbol{\xi}_k)\\
\vdots\\
f_m(\boldsymbol{\xi}_k)
\end{array}
\right)\times v(I_k)
=
v(I_k)\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{\xi}_k)\\
f_2(\boldsymbol{\xi}_k)\\
\vdots\\
f_m(\boldsymbol{\xi}_k)
\end{array}
\right)
=
\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
f_2(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\vdots\\
f_m(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)
\end{array}
\right)\in \mathbb{R}^m
$$
です。
故に、
\begin{eqnarray}
s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)&=&\sum_{k\in K(\Delta)}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
&=&
\sum_{k\in K(\Delta)}
\left(
\begin{array}{c}
f_1(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
f_2(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\vdots\\
f_m(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)
\end{array}
\right)\\
&=&
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}f_1(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}f_2(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\vdots\\
\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}f_m(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)
\end{array}
\right)\\
&=&
\left(
\begin{array}{c}
s\left(f_1;\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\\
s\left(f_2;\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\\
\vdots\\
s\left(f_n;\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\\
\end{array}
\right)
\in \mathbb{R}^m
\end{eqnarray}
となります。
以上のことから、ベクトル値関数のリーマン和はベクトル値です。
少し詳しく言うと、
です。
ベクトル値関数におけるリーマン積分
先程の「ベクトル値関数のリーマン和は、各成分のリーマン和を並べたベクトル」ということから、「ベクトル値関数の積分は成分ごとの積分」が直ちに分かると思います。
ベクトル値関数におけるリーマン積分の明示
ベクトル値関数におけるリーマン積分
\(I\subset\mathbb{R}^n\)を有界な閉集合、\(\boldsymbol{f}\)が\(I\)上で定められ、\(\mathbb{R}^m\)の値を取る関数、すなわち\(\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^n\supset I\to \mathbb{R}^m\)とする。このとき、\(I_k\)の代表点\(\boldsymbol{\xi}_k\)の取り方に依存せず\(\boldsymbol{f}\)の\(\Delta\)に関するリーマン和\(s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\)の極限 $$ \lim_{d(\Delta)\to0}s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)=\boldsymbol{J}\in\mathbb{R}^m $$ が存在するとき、\(\boldsymbol{f}\)は\(I\)上(で)可積分といい、 $$ \boldsymbol{J}=\int_I\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} $$ を\(\boldsymbol{f}\)の\(I\)上の(リーマン)積分という。リーマン和のときと同様に、形式的には実数値関数のときと同じです。
リーマン積分についても記号を観察してみます。
ベクトル値関数のリーマン積分に出現する各記号について考えてみる
リーマン和\(s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\)は
\begin{eqnarray}
s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)=\sum_{k\in K(\Delta)}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)=\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}f_1(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}f_2(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\vdots\\
\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}f_m(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)
\end{array}
\right)
\end{eqnarray}
でした。
このとき極限\(\displaystyle\lim_{d(\Delta)\to0}s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\)が存在すれば、
\begin{eqnarray}
\lim_{d(\Delta)\to0}s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)&=&\lim_{d(\Delta)\to0}\sum_{k\in K(\Delta)}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
&=&
\lim_{d(\Delta)\to0}
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}f_1(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}f_2(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\vdots\\
\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}f_m(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)
\end{array}
\right)\\
&=&
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\lim_{d(\Delta)\to0}\sum_{k\in K(\Delta)}f_1(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\displaystyle\lim_{d(\Delta)\to0}\sum_{k\in K(\Delta)}f_2(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)\\
\vdots\\
\displaystyle\lim_{d(\Delta)\to0}\sum_{k\in K(\Delta)}f_m(\boldsymbol{\xi}_k)v(I_k)
\end{array}
\right)\\
&=&
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\int_If_1(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\displaystyle\int_If_2(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\vdots\\
\displaystyle\int_If_m(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\end{array}
\right)
\end{eqnarray}
となります(ただし、これは以下で復習する定理3.(ベクトル値関数の極限)を使っています)。
すなわち、\(\boldsymbol{J}\)の正体はベクトルだ、ということです。
これはまさに「ベクトル値関数の積分は成分ごとの積分」ということを表しています。
ただし、注意があります。
先程の章で「ベクトル値関数のリーマン和は、各成分のリーマン和を並べたベクトルです。」と述べましたが、リーマン積分はベクトルの極限ではありません。
なぜなら、\(d(\Delta)\)はベクトルではなく、実数だからです。
この章で言いたかったこと
結局の所、言いたかったことは
ということです。
ベクトル値関数の積分は成分ごとの積分なので、実数値関数の積分に帰着できる、というわけです。
有界なベクトル値関数の可積分条件
では、ベクトル値関数が可積分であることの必要十分条件を解説します。
とはいっても、もう既に述べているようなものですが…
有界なベクトル値関数の可積分条件の明示
定理1.(有界なベクトル値関数の可積分条件)
\(I\subset\mathbb{R}^n\)を有界な閉集合とする。このとき有界なベクトル値関数\(\boldsymbol{f}:I\to\mathbb{R}^m\)が\(I\)上で可積分であるための必要十分条件は、\(\boldsymbol{f}\)の成分である実数値関数\(f_i:I\to\mathbb{R}\ (i=1,2,\dots,m)\)が全て\(I\)上で可積分であることである。そしてこのとき、 $$ \int_I\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}= \left( \begin{array}{c} \displaystyle\int_If_1(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\ \displaystyle\int_If_2(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\ \vdots\\ \displaystyle\int_If_m(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\ \end{array} \right) $$ である。ちなみに、
$$
\int_I\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}=
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\int_If_1(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\displaystyle\int_If_2(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\vdots\\
\displaystyle\int_If_m(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\end{array}
\right)
$$
というように、列ベクトルとして捉えましたが、
$$
\int_I\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}=\left(\int_If_1(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}, \int_If_2(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x},\dots,\int_If_m(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\right)
$$
というように、行ベクトルとして捉えることもあります。
定理1.の系(複素数値関数の可積分条件)
定理1.の系として複素数値関数の可積分条件があります。
系2.(複素数値関数の可積分条件)
\(I\in\mathbb{R}^n\)を有界な閉集合、\(f_1:I\to\mathbb{R}\)、\(f_2:I\to\mathbb{R}\)とする。このとき、複素数値関数\(f:I\to\mathbb{C}\)が\(f(\boldsymbol{x})=f_1(\boldsymbol{x})+if_2(\boldsymbol{x})\)(\(i\)は虚数単位)で与えられるならば、\(f\)が\(I\)上で可積分であるための必要十分条件は、\(f_1\)と\(f_2\)の双方が\(I\)上で可積分であることである。またこのとき、 $$ \int_If(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}=\int_If_1(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}+i\int_If_2(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} $$ である。定理1.を認めてしまえば、系2.が成り立つことが直ちに分かります。
なぜなら、一般に、複素数\(z\in\mathbb{C}\)は\(z=x+iy\)と書けるため、\(z\in\mathbb{C}\)は実数の対\((x,y)\in\mathbb{R}^2\)として捉えることができるから、定理1.において、\(m=2\)の場合にほかならないからです。
ちなみに、複素数を実数の対として捉えて座標と対応させたのが複素数平面です。
有界なベクトル値関数の可積分条件の証明
では、定理1.の証明ですが、もうほぼ証明しています。
なぜなら、以下の事実を既に証明しているからです。
定理3.(多変数ベクトル値関数の収束と同値な命題)
\(\Omega\subset\mathbb{R}^n\)を\(\mathbb{R}^n\)の領域、\(\boldsymbol{f}:\Omega\to\mathbb{R}^m\)を写像(関数)、\(\boldsymbol{a}\in\bar{\Omega}\)、\(\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^m\)とする。\(\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}\)のとき\(f(\boldsymbol{x})\)が\(\boldsymbol{A}\)に収束するとする。 すなわち、 $$(\forall \epsilon>0)(\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ (\forall \boldsymbol{x}\in\bar{\Omega}:0<|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|<\delta\Rightarrow |\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{A}|<\epsilon)$$ が成り立っているとする。 $$ \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\left( \begin{array}{c} f_1(\boldsymbol{x})\\ f_2(\boldsymbol{x})\\ \vdots\\ f_m(\boldsymbol{x}) \end{array} \right),\quad \boldsymbol{A}=\left( \begin{array}{c} A_1\\ A_2\\ \vdots\\ A_m \end{array} \right),\quad $$ と書いたとき、 $$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\Leftrightarrow \ (\forall i\in\mathbb{N}:1\leq i\leq m)\ \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_i(\boldsymbol{x})=A_i$$ が成り立つ。 言い換えれば、 $$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})= \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\left( \begin{array}{c} f_1(\boldsymbol{x})\\ f_2(\boldsymbol{x})\\ \vdots\\ f_m(\boldsymbol{x}) \end{array} \right)= \left( \begin{array}{c} \displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_1(\boldsymbol{x})\\ \displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_2(\boldsymbol{x})\\ \vdots\\ \displaystyle\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f_m(\boldsymbol{x}) \end{array} \right) $$ が成り立つ。定理3.の証明は【解析学の基礎シリーズ】多変数関数編 その2を御覧ください。
リーマン和\(s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\)を\(d(\Delta)\)を変数とする関数と捉えて、定理3.の\(n=1\)の場合を適用させることで証明完了です。
定理1.の証明
リーマン和\(s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\)を\(d(\Delta)\)を変数とする関数と捉えます。
今、\(\boldsymbol{f}:I\to\mathbb{R}^m\)が可積分だとします。
すると、\(I_k\)の代表点\(\boldsymbol{\xi}_k\)の取り方に依存せず\(\boldsymbol{f}\)の\(\Delta\)に関するリーマン和\(s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)\)の極限
$$
\lim_{d(\Delta)\to0}s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)=\boldsymbol{J}
$$
が存在します。
このとき、定理3.と\(\displaystyle\sum_{k\in K(\Delta)}\boldsymbol{f}\left( \boldsymbol{\xi}_k\right)v\left( I_k\right)\)についてでの考察から
\begin{eqnarray}
\lim_{d(\Delta)\to0}s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)
=
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\int_If_1(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\displaystyle\int_If_2(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\vdots\\
\displaystyle\int_If_m(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\end{array}
\right)
\end{eqnarray}
が成り立つので、\(\boldsymbol{f}\)の各成分が可積分です。
逆に、\(\boldsymbol{f}\)の各成分が可積分であれば、
\begin{eqnarray}
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\int_If_1(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\displaystyle\int_If_2(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\vdots\\
\displaystyle\int_If_m(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\\
\end{array}
\right)
=
\lim_{d(\Delta)\to0}s\left(\boldsymbol{f};\Delta;\boldsymbol{\xi} \right)
\end{eqnarray}
が導けるので、\(\boldsymbol{f}\)は可積分です。
定理1.の証明終わり
今まで学習したことはベクトル値関数でも成り立ちます。
「今まで学習したことは全てベクトル値関数でも成り立ちます」というと語弊がありますが、ベクトル置換数に対して意味のあるものはベクトル値関数に対しても成り立ちます。
なぜなら、(くどいようですが)ベクトル値関数の積分は実数値関数の積分に帰着できるからです。
ここでは、実数値関数で成り立ったことの内、ベクトル値関数でも成り立つ事実を列挙します。
ただし、ベクトル値関数の積分は実数値関数の積分に帰着できることから証明は省略します。
(※実数値関数における証明に「任意の\(f_i\ (i=1,2,\dots,m)\)に対して」という文言を入れるだけだからです。)
積分の線型性
定理4.(ベクトル値関数の積分の線型性)
\(\mathbb{R}^n\)の有界閉区間\(I\)上で可積分な\(\mathbb{R}^m\)のベクトル値関数全体の集合\(\mathcal{R}_m(I)\)は実線型空間であり、\(I\)上の積分は\(\mathcal{R}_m(I)\)から\(\mathbb{R}\)への線型写像である。すなわち、\(\forall \boldsymbol{f},\boldsymbol{g}\in\mathcal{R}_m(I)\)、\(\forall c\in\mathbb{R}\)に対して、\(\boldsymbol{f}+\boldsymbol{g},\ c\boldsymbol{f}\in\mathcal{R}(I)\)であり、かつ- \(\displaystyle\int_I(\boldsymbol{f}+\boldsymbol{g})(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}=\int_{I}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}+\int_{I}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\)
- \(\displaystyle\int_I\left( c\boldsymbol{f}\right)(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}=c\int_I\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\)
実数値関数の場合の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その2を御覧ください。
ダルブーの定理と可積分条件
実数値関数\(f\)の不足和\(s_\Delta=s_\Delta(\boldsymbol{f})\)等は大小関係を用いて定められていますが、ベクトル値関数\(\boldsymbol{f}\)に対して
$$
\boldsymbol{s}_\Delta(\boldsymbol{f})=\left(s_\Delta(\boldsymbol{f}_1),\dots, s_\Delta(\boldsymbol{f}_m)\right)
$$
として定めて、これと同様にして過剰和\(\boldsymbol{S}_\Delta\)、上積分\(\displaystyle\boldsymbol{S}=\sup_{\Delta\in\mathcal{D}}\boldsymbol{S}_\Delta\)、下積分\(\displaystyle\boldsymbol{s}=\inf_{\Delta\in\mathcal{D}}\boldsymbol{s}_\Delta\)を定めることでダルブーの定理と可積分条件が成り立ちます。
定理5.(ベクトル値関数におけるダルブーの定理)
\(I\)を\(\mathbb{R}^n\)の閉区間とする。このとき、任意の有界なベクトル値関数\(f:I\to\mathbb{R}^m\)に対して常に $$ \lim_{d(\Delta)\to0}\boldsymbol{s}_\Delta=\boldsymbol{s},\quad \lim_{d(\Delta)\to0}\boldsymbol{S}_\Delta=\boldsymbol{S} $$ が成り立つ。実数値関数の場合の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その3を御覧ください。
定理6.(ベクトル値関数の可積分条件)
\(I\)を\(\mathbb{R}^n\)の有界閉集合とするとき、\(I\)上の有界なベクトル値関数\(f:I\to \mathbb{R}^m\)に対して、次の1.~5.は同値である。- \(\boldsymbol{f}\)は\(I\)上で(リーマン)可積分である。
- \(\displaystyle\lim_{d(\Delta)\to0}\left( \boldsymbol{S}_\Delta-\boldsymbol{s}_\Delta\right)=\boldsymbol{0}\)
- リーマンの可積分条件 小区間\(I_k\ (k\in K(\Delta))\)上の\(\boldsymbol{f}\)の振幅\(a(\boldsymbol{f},I_k)=\boldsymbol{M}_k-\boldsymbol{m}_k\)に対して、 $$ \lim_{d(\Delta)\to0}\sum_{k\in K(\Delta)}a(\boldsymbol{f},I_k)v(I_k)=\boldsymbol{0} $$ である。
- ダルブーの可積分条件 \(\boldsymbol{S}=\boldsymbol{s}\)、すなわち、 $$ \underline{\int_I} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}=\overline{\int_I}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} $$ である。
- 任意の\(\varepsilon>0\)に対して、\(\left\|\boldsymbol{S}_\Delta-\boldsymbol{s}_\Delta\right\|<\varepsilon\)となる\(I\)の分割\(\Delta\)が存在する。
実数値関数の場合の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その4および【解析学の基礎シリーズ】積分編 その5を御覧ください。
積の可積分性
これについては、ベクトル値関数\(\boldsymbol{f}\)と実数値関数\(g\)の積に対して成り立ちます。
定理7.
\(I\subset\mathbb{R}^n\)とする。2つの有界な関数\(\boldsymbol{f}:I\to\mathbb{R}^m\)、\(g:I\to\mathbb{R}\)が\(I\)上で可積分であれば、積\(g\boldsymbol{f}\)も\(I\)上で可積分である。実数値関数の場合の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その8を御覧ください。
ベクトルには割り算が存在しませんので、ベクトル値関数の逆数の積分は成り立ちません。
ちょっとだけベクトル値関数の積分を計算してみます。
まだ代表的な初等関数の可積分性について述べていないので、またまた簡単な例になってしまいますが、1つ例を挙げます。
例8. \(\boldsymbol{f}:[1,2]\to\mathbb{R}^2\)を\(\displaystyle\boldsymbol{f}(x)=
\left(
\begin{array}{c}
f_1(x)\\
f_2(x)
\end{array}
\right)=
\left(
\begin{array}{c}
x\\
\log x
\end{array}
\right)
\)とします。
\(f_1\)も\(f_2\)も\(I=[1,2]\)で可積分です(\(f_2\)の可積分性については、\(\log x\)は\([1,2]\)で単調な関数だからです)ので定理1.から\(\boldsymbol{f}\)も可積分で、
\begin{eqnarray}
\int_I\boldsymbol{f}(x)\ dx&=&
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\int_If_1(x)\ dx\\
\displaystyle\int_If_2(x)\ dx\\
\end{array}
\right)\\
&=&
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\int_{[1,2]}x\ dx\\
\displaystyle\int_{[1,2]}\log x\ dx\\
\end{array}
\right)\\
&=&
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\left[ \frac{1}{2}x^2\right]_1^2\\
\displaystyle\left[ \frac{1}{x}\right]_1^2
\end{array}
\right)\\
&=&
\left(
\begin{array}{c}
\displaystyle\frac{3}{2}\\
\displaystyle-\frac{1}{2}
\end{array}
\right)
\end{eqnarray}
となります。
ただし、
$$
\int_I\log x\ dx=\left[ \frac{1}{x}\right]_1^2
$$
であることは、高校数学の知識ということで一旦認めています(後の記事で証明します)。
皆様のコメントを下さい!
以前の記事でも数学者のヤバい話を少し紹介しましたが、個人的に最もヤバいのはエヴァリスト・ガロアだと思っています。
ガロアはフランスの数学者で、ガロア理論という理論を構築した大数学者です。
ガロア理論のおかげで「5時以上の方程式には代数的な一般解は存在しない」というアーベルの定理の証明を大幅に簡略化しました。
定理だけでなく、理論そのものに名を残す大数学者でしたが、その人生は短く、なんと20歳で亡くなっています。
その死因がヤバいのです。
なんと決闘の傷による腹膜炎で亡くなったそうです。
なぜ決闘になったかというと、女性を取り合った、ということらしいです。
「なんじゃそれ?」という感じで、ヤバいな、と思いました。
個人的には最もヤバい数学者のエピソードだと思っていますが、これを超える数学者のヤバい話をご存じの方は是非コメントで教えて下さい!
結
今回は、ベクトル値関数の積分について解説しました。
微分法のときと同様に、多少の条件はあれど、ベクトル値関数の積分はベクトルの各成分の積分です。
つまり、ベクトル値関数の積分は実数値関数の積分に帰着できます。
そして、実数値関数で成り立ったことのうち、ベクトルとしても意味があるものについては成り立ちます。
次回は一様連続とハイネの定理について解説します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。
もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。
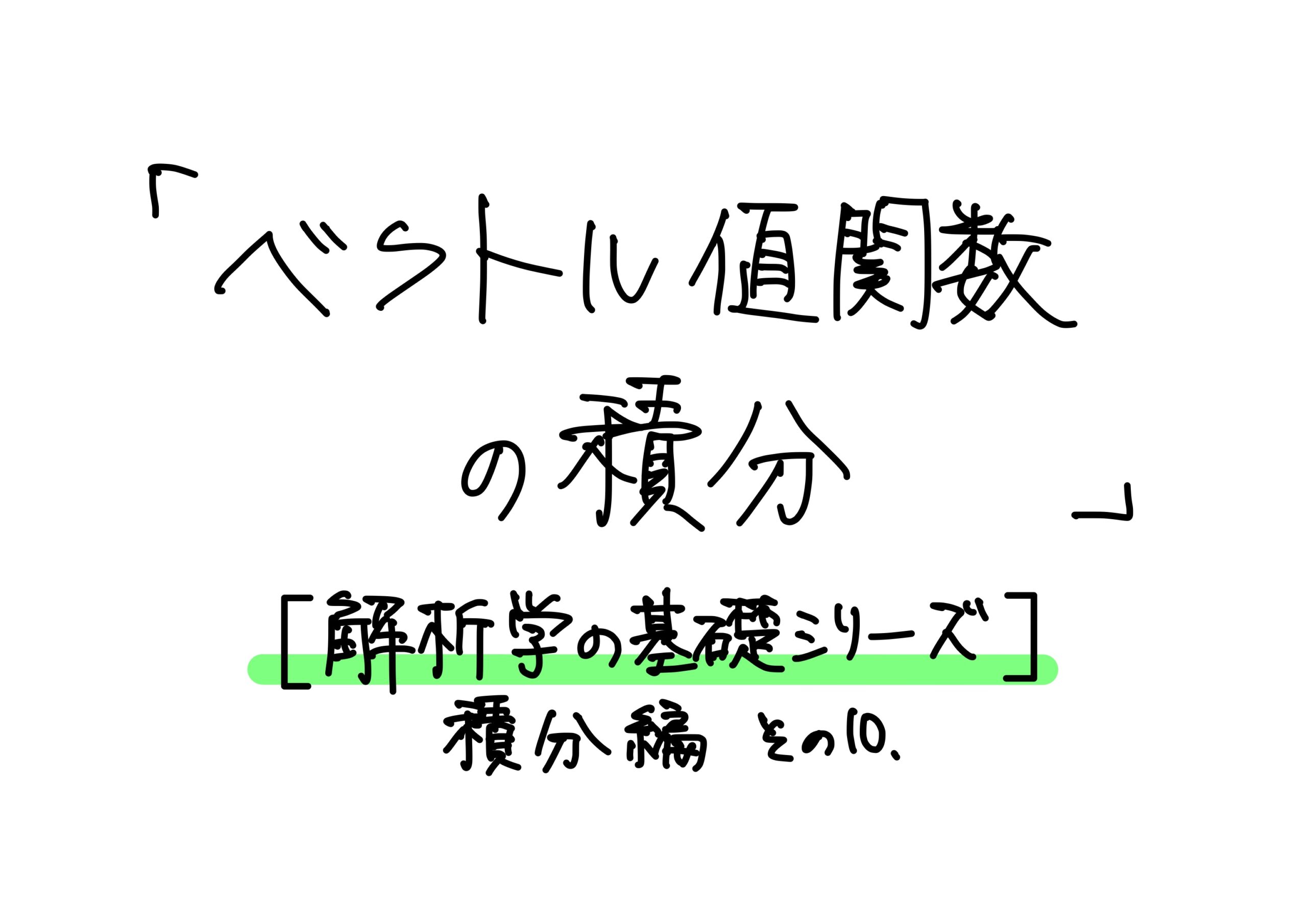
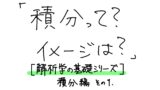
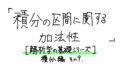
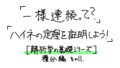
コメントをする