本記事の内容
本記事は積分の三角不等式について解説する記事です。
本記事を読むにあたり、可積分条件について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。
絶対値がついた関数の積分と、積分の絶対値の関係
例えば、次の積分を考えてみましょう。
例1. \(f:[1,2]\to\mathbb{R}\)、\(f(x)=|x|\)は\(I\)上で可積分で、かつ\(\left|f(x) \right|\)も可積分で、積分は高校数学の知識を使って
$$
\int_{[1,2]} \left|f(x) \right|\ dx=\int_{[1,2]} x\ dx=\left[ \frac{1}{2}x^2\right]_1^2=\frac{1}{2}(4-1)=\frac{3}{2}
$$
です。
2つ目の\(=\)が成り立つのは、\([1,2]\)で\(f\)が常に正の値を取るからです。
この場合は特に計算上、問題はありません。
では、高校数学の知識を使って次の積分を計算してみます。
例2. \(g:[-1,1]\to\mathbb{R}\)、\(g(x)=x\)は\(I\)上で可積分で、その積分は
\begin{eqnarray}
\int_{[-1,1]} \left|g(x) \right|\ dx&=&\int_{[-1,0]} -x\ dx+\int_{[0,1]} x\ dx\\
&=&\left[ -\frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^0+\left[ -\frac{1}{2}x^2\right]_0^1\\
&=&-\frac{1}{2}(0-1)+\frac{1}{2}(1-0)\\
&=&\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1
\end{eqnarray}
です。
一方で、
\begin{eqnarray}
\left|\int_{[-1,1]} g(x) \ dx\right|&=&\left|\int_{[-1,1]} x\ dx\right|\\
&=&\left|\left[ \frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^1\right|\\
&=&\left|\frac{1}{2}(1-1)\right|
&=&0
\end{eqnarray}
です。
従って、一般に\(|f|\)の積分と、\(f\)の積分の絶対値は一致しません。
(※そもそも積分する関数が異なるので必ずしも一致するわけはないのですが…)
積分の三角不等式
では、今回解説する主張を明示します。
積分の三角不等式の明示とその証明
定理3.(積分の三角不等式)
\(f\)が\(I\subset\mathbb{R}^n\)上の有界かつ可積分な実数値関数であれば、\(\left|f\right|\)も可積分で、 $$ \left|\int_I f\ d\boldsymbol{x}\right|\leq \int_I\left|f(\boldsymbol{x})\right|\ d\boldsymbol{x} $$ が成り立つ。「え?これが三角不等式?」となったかもしれませんが(筆者はなりました)、それについては後述します。
定理3.の証明
任意の\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in I\)に対して
$$
\left|\left|f(\boldsymbol{x})\right|-\left|f(\boldsymbol{y})\right|\right|\leq \left|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{y})\right|
$$
ですから、任意の\(k\in K(\Delta)\)に対して、
$$
0\leq a\left( \left|f\right|,I_k\right)\leq a\left( f,I_k\right)
$$
です。
実際、
\begin{eqnarray}
0&\leq& a\left( \left|f\right|,I_k\right)\\
&=&\sum_{k\in K(\Delta)}\left|f(\boldsymbol{\xi}_k)\right|v(I_k)-\sum_{k\in K(\Delta)}\left|f(\boldsymbol{\xi}_{k-1})\right|v(I_k)\\
&=&\sum_{k\in K(\Delta)}\left(\left|f(\boldsymbol{\xi}_k)\right|-\left|f(\boldsymbol{\xi}_{k-1})\right|\right) v(I_k)\\
&\leq&\sum_{k\in K(\Delta)}\left(f(\boldsymbol{\xi}_k)-f(\boldsymbol{\xi}_{k-1})\right) v(I_k)\\
&=&a\left( f,I_k\right)
\end{eqnarray}
です。
今、\(f\)が\(I\)上で可積分だとします。
ここで、以下の定理を使います。
定理0.(可積分条件)
\(I\)を\(\mathbb{R}^n\)の有界閉集合とするとき、\(I\)上の有界な実数値関数\(f:I\to \mathbb{R}\)に対して、次の1.~5.は同値である。- \(f\)は\(I\)上で(リーマン)可積分である。
- \(\displaystyle\lim_{d(\Delta)\to0}\left( S_\Delta-s_\Delta\right)=0\)
- リーマンの可積分条件 小区間\(I_k\ (k\in K(\Delta))\)上の\(f\)の振幅\(a(f,I_k)=M_k-m_k\)に対して、 $$ \lim_{d(\Delta)\to0}\sum_{k\in K(\Delta)}a(f,I_k)v(I_k)=0 $$ である。
- ダルブーの可積分条件 \(S=s\)、すなわち、 $$ \underline{\int_I} f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}=\overline{\int_I}f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} $$ である。
- 任意の\(\varepsilon>0\)に対して、\(S_\Delta-s_\Delta<\varepsilon\)となる\(I\)の分割\(\Delta\)が存在する。
定理0.の証明は【解析学の基礎シリーズ】積分編 その4および【解析学の基礎シリーズ】積分編 その5を御覧ください。
今、\(f\)が定理0.の3.を満たしているので、\(|f|\)も定理0.の3.を満たします。
従って、\(|f|\)も可積分です。
任意の分割\(\Delta\)と代表点\(\boldsymbol{\xi}\)に対して、実数の和に関する三角不等式で
$$
\left|s\left( f;\Delta;\boldsymbol{\xi}\right)\right|\leq s\left( |f|;\Delta;\boldsymbol{\xi}\right)
$$
が成り立つので、\(d(\Delta)\to0\)とすることで、
$$
\left|\int_I f\ d\boldsymbol{x}\right|\leq \int_I\left|f(\boldsymbol{x})\right|\ d\boldsymbol{x}
$$
を得ます。
定理3.の証明終わり
どうして”三角不等式”と呼ぶのですか?
どうも積分の三角不等式は”三角不等式感”がありません。
ではなぜ”三角不等式”と呼ばれるか、というと、ベクトルに関する三角不等式に由来しているからだと思います。
我々が知っている三角不等式は
\begin{eqnarray}
\left|a+b\right|&\leq&\left|a\right|+\left|b\right|\\
\left\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\right\|&\leq&\left\|\boldsymbol{a}\right\|+\left\|\boldsymbol{b}\right\|
\end{eqnarray}
です。
この\left|\right|に関する三角不等式を繰り返して用いると、
\begin{eqnarray}
\left|\sum_{i=1}^na_i\right|&\leq&\sum_{i=1}^n|a_i|\\
\left|\sum_{i=1}^\infty a_i\right|&\leq&\sum_{i=1}^\infty|a_i|
\end{eqnarray}
となります。
この不等式において\(\displaystyle\sum\)を\(\displaystyle\int\)に、\(a_i\)を\(f(\boldsymbol{x})\)に置き換えると
$$
\left|\int_If(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}\right|\leq \int_I\left|f(\boldsymbol{x})\right|\ d\boldsymbol{x}
$$
となります。
これが由来だと思われます(断言できなくてごめんなさい)。
\(\left|f\right|\)が可積分だったとしても、\(f\)は可積分とは限りません。
定理3.から\(f\)が可積分であれば、\(\left|f\right|\)も可積分であるということが分かりました。
しかしその逆は成り立ちません。
すなわち、\(\left|f\right|\)が可積分だったとしても、\(f\)は可積分とは限りません。
なぜか、ということを例を上げることで示します(誠に恣意的ですが…)。
例4. \(f:[0,1]\to\mathbb{R}\)を任意の\(x\in I\)に対して\(\displaystyle
f(x)=
\begin{cases}
1&(x\in\mathbb{Q})\\
-1&(x\not\in\mathbb{Q} )\\
\end{cases}
\)として定めます。
このとき、\(\left|f(x)\right|=1\)ですので、定数関数だから\(I\)で可積分です。
しかしながら一方で、\(f\)は可積分ではありません。
実際、\(I\)の任意の分割\(\Delta\)に対して、各小区間\(I_k\ (k\in I_k)\)は有理数\(\xi_k\)も無理数\(\eta_k\)も双方を含みます。
従って、
$$
s\left( f;\Delta;\xi\right)=1\quad s\left( f;\Delta;\eta\right)=-1
$$
となるので、\(d(\Delta)\to 0\)としたときにリーマン和は一定の実数に収束しません。
故に可積分ではありません。
読者の皆様のコメントを下さい!
数学にセンスは必要だと思いますか?
まず、”センス”とは何でしょうか。
これは筆者の中で未だはっきりとした答えは出ていませんが、「センス\(\fallingdotseq\)経験」だと思います。
筆者が「あの人、数学のセンスがあるなあ」と思う人は「〜が存在する。」という主張の証明をサラッとする人です。
こういう方に出会ったときに「頭いいなあ。これがセンスなのかなあ。」と思いました。
しかし、考え方を変えてみると、”センス”がある方はありとあらゆる数学に触れて1つ1つ自分で例を挙げつつ理解しようと勉強している方だと思いました。
皆様はどう思いますか?ご意見を是非コメントで教えて下さい!
結
今回は、積分の三角不等式について解説しました。
最も大事なのは、可積分関数の絶対値は可積分だけれども、その逆は成り立たない、ということです。
次回は可積分な関数の積の可積分性と、可積分な関数の逆数も可積分である、ということを解説します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。
もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。
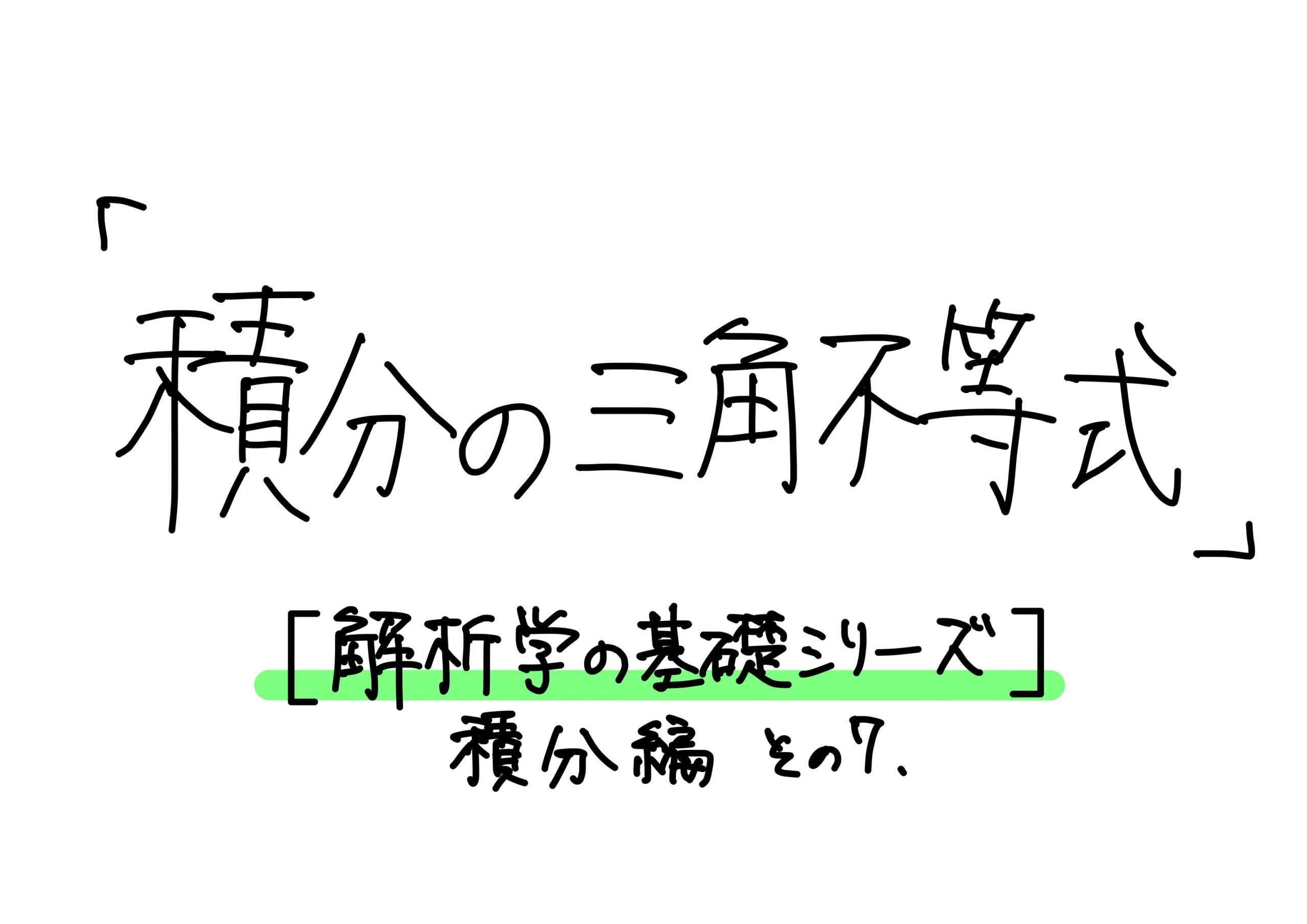
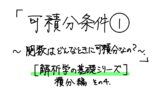
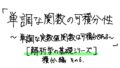

コメントをする