本記事の内容
本記事は陰関数定理から逆関数定理を証明してみる記事です。
本記事を読むにあたり、逆関数定理、陰関数定理について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。
↓逆関数定理の記事
↓陰関数定理の記事
実は、陰関数定理から逆関数定理を導くことができます。
以前の陰関数定理の記事では、逆関数定理を証明して、その逆関数定理から陰関数定理を証明しました。
実は、その逆、陰関数定理を認めれば逆関数定理が成り立つということを証明することもできます。
今回は、陰関数定理を認めた上で、逆関数定理を証明します。
ちなみに、本ブログでは紹介しませんが、陰関数定理は逆関数定理を使わずとも証明が可能です(数学的帰納法で証明します)。
陰関数定理と逆関数定理を軽く復習します。
復習といってもほぼ明示するだけなのですが…
陰関数定理
定理1.(陰関数定理、implicit function theorem)
\(\Omega\)は\(\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^n\)の開集合、\(\boldsymbol{F}:\Omega\ni(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\mapsto \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\in\mathbb{R}^n\)は\(C^1\)級、\((\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\in\Omega\)、\(\boldsymbol{F}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}\)、\(\displaystyle\det\left( \frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{y}}\right)(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\neq\boldsymbol{0}\)が成り立つとする。このとき、\(\boldsymbol{a}\)を含む\(\mathbb{R}^m\)の開集合\(U\)、\(\boldsymbol{b}\)を含む\(\mathbb{R}^n\)の開集合\(V\)、\(C^1\)級の関数\(\boldsymbol{\varphi}:U\to V\)で、以下の1.,2.,3.,4.を満たすものが存在する。- \(U\times V\subset \Omega\).
- \(\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{a})=\boldsymbol{b}\).
- \(\forall (\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\in U\times V\)に対して、\(\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}\ \Longleftrightarrow\ \boldsymbol{y}=\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x})\).
- \(\forall \boldsymbol{x}\in U\)に対して、\(\displaystyle\boldsymbol{\varphi}^\prime(\boldsymbol{x})=-\left( \frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{y}}\left( \boldsymbol{x},\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x})\right)\right)^{-1}\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{x}}\left( \boldsymbol{x},\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x})\right)\)
陰関数定理の証明(逆関数定理から陰関数定理を導く証明)は【解析学の基礎シリーズ】偏微分編 その13を御覧ください。
陰関数定理は、とどのつまり、「ある点の近くで(局所的に)陰関数が存在しますよ」という主張をしている定理です。
逆関数定理
定理2.(逆関数定理)
\(\Omega\)は\(\mathbb{R}^n\)の開集合、\(\boldsymbol{f}:\Omega\to\mathbb{R}^n\)は\(C^1\)級、\(\boldsymbol{a}\in\Omega\)、\(\det\left( \boldsymbol{f}^\prime(\boldsymbol{a})\right)\neq0\)とするとき、以下が成り立つ。\({\rm s.t.}\ \left(\tilde{\boldsymbol{f}}=\left.\boldsymbol{f}\right|_{U}:U\ni \boldsymbol{x}\mapsto \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\in V\right.\)は全単射で、逆関数\(\left.\tilde{\boldsymbol{f}}^{-1}:V\to U\right.\)も\(C^1\)級である。\(\Large)\)
逆関数定理の証明は【解析学の基礎シリーズ】偏微分編 その12を御覧ください。
逆関数定理はとどのつまり、「ある条件下では\(C^1\)級の逆関数が存在しますよ」という主張をしています。
陰関数定理から逆関数定理を証明しましょう。
では、いきます。
既に逆関数定理の証明を読んで頂いた方は「え…あんな長い証明をもう一回するの…?」と思われるかもしれませんが、実は陰関数定理を認めてしまえば、逆関数定理の証明はそこまで長くないです。
陰関数定理から逆関数定理の証明
\(\boldsymbol{\varphi}:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to \mathbb{R}^n\)を
$$
\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{y}
$$
で定めます。
このとき、\(\boldsymbol{b}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})\)により、\(\boldsymbol{F}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}\)です。
従って、陰関数定理から、\(\boldsymbol{a}\)の開近傍\(W\subset \mathbb{R}^n\)と\(C^1\)級の写像\(\boldsymbol{\varphi}:W\to\mathbb{R}^n\)が存在して、
\begin{eqnarray}
&&\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\varphi(\boldsymbol{x}))=\boldsymbol{0}\quad(\boldsymbol{x}\in W),\\
&&\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{a})=\boldsymbol{b},\\
&&\frac{\partial \boldsymbol{\varphi}}{\partial \boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x})=\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{x}}\left( \boldsymbol{x},\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x})\right)\quad (\boldsymbol{x}\in W)
\end{eqnarray}
です。
一方で、
$$
\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\frac{\partial \boldsymbol{\varphi}}{\partial \boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x})\quad ((\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\in \mathbb{R}^{n+n})
$$
により、
$$
\det\left(\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{x}}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\right)=\det\left( \frac{\partial \boldsymbol{\varphi}}{\partial \boldsymbol{x}}(\boldsymbol{a})\right)\neq0
$$
だから、再度陰関数定理により、\(\boldsymbol{y}\)の開近傍\(W^\prime\in\mathbb{R}^n\)と\(C^1\)級の写像\(\boldsymbol{\psi}:W^\prime\to\mathbb{R}^n\)が存在して、
\begin{eqnarray}
&&\boldsymbol{F}(\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y}),\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}\quad(\boldsymbol{y}\in W^\prime),\\
&&\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a},\\
&&\frac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial \boldsymbol{y}}(\boldsymbol{y})=\left( \frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{x}}\left( \boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y}),\boldsymbol{y}\right)\right)^{-1}\quad (\boldsymbol{y}\in W^\prime)
\end{eqnarray}
です。
すなわち、\(\left(\boldsymbol{\varphi}\circ\boldsymbol{\psi}\right)(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}\)です。
実際、\(\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x})\right)=\boldsymbol{0}\)かつ\(\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y}),\boldsymbol{y}\right)=\boldsymbol{0}\)なので、\(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x})\)、\(\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y})\right)=\boldsymbol{y}\)だから、
$$
\boldsymbol{f}\left( \boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{\varphi}\left( \boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y})\right)\right)=\left( \boldsymbol{\varphi}\circ\boldsymbol{\psi}\right)(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}
$$
となるためです。
従って、\(\boldsymbol{\varphi}\circ\boldsymbol{\psi}={\rm id}_{W^\prime}\)です。
ここで、\(\boldsymbol{b}\)の開近傍\(V\)を
$$
V\subset W^\prime,\quad \boldsymbol{\psi}(V)\subset W
$$
となるように取ります。
このとき、\(\left( \boldsymbol{\varphi}\circ\boldsymbol{\psi}\right)(V)=V\)です。
そこで、\(U=\boldsymbol{\psi}(V)\)としましょう。
すると、
$$
(\forall \boldsymbol{x}\in U)\ (\exists \boldsymbol{y}\in V)\ {\rm s.t.}\ \boldsymbol{x}=\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y})
$$
を満たします(\(\boldsymbol{\psi}\)を\(V\)に制限すると全射となるため)。
故に、
\begin{eqnarray}
\left( \boldsymbol{\psi}\circ\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x})\right)&=&\left( \boldsymbol{\psi}\circ\boldsymbol{\varphi}\circ\boldsymbol{\psi}\right)(\boldsymbol{y})\\
&=&\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y})\\
&=&\boldsymbol{x}
\end{eqnarray}
となります。
これはすなわち、
$$
\left.\left(\boldsymbol{\psi}\circ\boldsymbol{\varphi}\right)\right|_V={\rm id}_V
$$
を意味しています。
さて、\(\boldsymbol{\varphi}\)と\(\boldsymbol{\psi}\)の定義域を改めて\(U\)、\(V\)に制限すると、
\begin{eqnarray}
&&\boldsymbol{\varphi}:U\to\boldsymbol{\varphi}(U)=V,\\
&&\boldsymbol{\psi}:V\to\boldsymbol{\psi}(V)=U
\end{eqnarray}
で、\(\boldsymbol{\varphi}^{-1}(V)=U\)は開集合です。
従って、今\(\boldsymbol{\varphi}\circ\boldsymbol{\psi}={\rm id}_{W^\prime}\)かつ\(\left.\left(\boldsymbol{\psi}\circ\boldsymbol{\varphi}\right)\right|_V={\rm id}_V\)が導けたので、\(\boldsymbol{\varphi}\)と\(\boldsymbol{\psi}\)は互いに逆写像の関係だから全単射です。
以上により、逆関数定理が成り立ちます。
陰関数定理から逆関数定理の証明終わり
ちなみに、多様体の分野では、全単射で逆写像が微分可能であるような写像を微分同相写像(diffeomorphism)といいます。
読者の皆様のコメントを下さい!
今回は少し毛色を変えてクイズを出題したいと思います。
よくある問題なのですが、「5Lの水が入る容器と3Lの水が入る容器があって、この2つを使って4Lをためて下さい」というものです。
これに「なるべく少ない工程で」という条件をつけてみます。
何回の操作で4Lの水を貯めることができるでしょうか。
筆者が初めてこの問題に出会ったときに「え?簡単じゃん?2回(厳密には3回かな?)の工程でおしまいじゃん。」と思いました(反則技かもしれませんが…)。
その回答は皆様がコメントを頂いた後に紹介するつもりですが、皆様の思いついた工程とその数をコメントで教えて下さい!
結
今回は陰関数定理から逆関数定理を導く、ということを解説しました。
本ブログでは逆関数定理を証明して、それを用いて陰関数定理を証明しました。
実は、その逆、陰関数定理を認めれば逆関数定理を導くことができます。
さらに陰関数定理は逆関数定理を用いずとも証明が可能です。(数学的帰納法で証明します)
故に、陰関数定理と逆関数定理は密接につながっています。
次回は陰関数定理の応用である条件付き極値問題、ラグランジュの未定乗数法について解説します。
乞うご期待!
質問、コメントなどお待ちしております!
どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!
お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。
もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。
Twitterでもリプ、DM問わず質問、コメントを大募集しております!

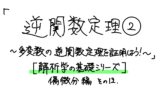


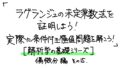
コメントをする