本記事の内容
本記事は初等関数の微分、特に多項式関数、指数関数、対数関数の微分について解説し、証明します。
本記事を読むにあたり、微分係数について知っている必要があるため、その際は以下の記事を参照してください。
この記事の地図
最も基本的な関数の微分として、\(f(x)=ax^n\)の微分が挙げられると思います。
\(n\in\mathbb{Q}\)の場合は、多少の予備知識が必要ですが、おおよそ基本的な難易度で証明が可能です。
しかし、\(n\in\mathbb{R}\)の場合は対数関数の微分の知識が必要になってきます。
従って、\(f(x)=ax^n\)は一筋縄では行きません。
少々カッコよく言えば、\(f(x)=ax^n\)の微分は基本にして応用だ、ということです(あまり意味がある言葉では有りませんのでスルーしてください)。
地図としては
です。
長丁場ですが、頑張っていきましょう!
必要な予備知識
まずは、必要な予備知識を説明します。
その中で最も基本的な概念がネイピア数\(e\)です。
ネイピア数
定理1.の証明
数列ですので、示したいことは
$$(\forall \epsilon>0)\ (\exists N\in\mathbb{N})\ {\rm s.t.}\ (\forall n\in\mathbb{N}:n\geq N\Rightarrow |a_n-A|<\epsilon)$$
ですが、「\(A\)ってなんだよ?」という話です。
地道に証明することも、もしかしたらできるのかもしれませんが、\(A\)の正体がわからない以上、あまりいい手法ではなさそうです。
従って、以下の事実を使います。
これは既に証明しています。
詳しくは【解析学の基礎シリーズ】実数の連続性編 その9を御覧ください。
さて、つまりは、\(a_n\)が有界かつ単調であることが言えれば良いわけです。
実際、\(a_n\)は単調増加数列です。
補題3.の証明
示したいことは、
$$
\left(1+\frac{1}{n+1} \right)^{n+1}\geq\left(1+\frac{1}{n} \right)^{n}
$$
です。
相加相乗平均を使えば、なんとも簡単に証明ができます。
相加相乗平均において、\(\displaystyle a_1=a_2=\cdot=a_n=\frac{n+1}{n}\)、\(a_{n+1}=1\)とします。
すると、
$$
\frac{\frac{n+1}{n}\cdot n+1}{n+1}\geq \sqrt[n+1]{\left( \frac{n+1}{n}\right)^n}
$$
が成り立ちます。
故に、
$$
\left(1+\frac{1}{n+1} \right)^{n+1}\geq\left(1+\frac{1}{n} \right)^{n}
$$
です。
補題3.の証明終わり
次に有界性について示します。
補題4.の証明
二項定理から直ちに分かります。
二項定理により、
\begin{eqnarray}
a_n&=&\left(1+\frac{1}{n} \right)^{n}\\
&=&\sum_{k=0}^n{}_nC_k\frac{1}{n^k}\\
&=&\sum_{k=0}^n\frac{1}{k!}\cdot 1\cdot \left( 1-\frac{1}{n}\right)\cdot \left( 1-\frac{2}{n}\right)\cdots \cdot \left( 1-\frac{k-1}{n}\right)\\
&\leq &\sum_{k=0}^n\frac{1}{k!}\\
&\leq &1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdot\\
&\leq&1+\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=3
\end{eqnarray}
故に有界です。
補題4.の証明終わり
従って、補題3.および補題4.から\(a_n\)が収束します。
定理1.の証明おわり
さて、\(\displaystyle\left(1+\frac{1}{n} \right)^{n}\)が収束するので、その収束先を\(e\)と書いてネイピア数と呼びます。
\(e^x\)および\(\log x\)に関わる極限
次の2つの極限が必要なので、それについて解説します。
補題6.の証明(というか計算)
一瞬です。
$$
\lim_{x\to0}\frac{\log(1+x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\log(1+x)=\lim_{x\to0}\log(1+x)^{\frac{1}{x}}=\log e=1
$$
ただし、\((1+x)^\frac{1}{x}\)は\(x>0\)で連続であるという事実から、\(\displaystyle\lim_{x\to0}\log(1+x)^{\frac{1}{x}}=\log e\)が成り立ちます。
補題6.の証明(というか計算)終わり
補題7.の証明(というか計算)
これも一瞬です。
\(t=e^x-1\)とすると、\(e^x=t+1\)ですので、\(x=\log(t+1)\)です。
また、\(x\to0\)のとき、\(t\to 0\)です。
故に、
$$
\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{t\to0}\frac{t}{\log(t+1)}=\lim_{t\to0}\frac{1}{\log(t+1)^\frac{1}{t}}=1
$$
です。
これも補題6.と同様に\((1+x)^\frac{1}{x}\)は\(x>0\)で連続であるという事実から、\(\displaystyle\lim_{x\to0}\log(1+x)^{\frac{1}{x}}=\log e\)です。
補題7.の証明(というか計算)おわり
さて、いよいよ指数関数の微分について話します。
指数関数の微分
主張を明示してしまいましょう。
定理8.の証明
真面目に証明してみましょう。
\begin{eqnarray}
\left( a^x\right)^\prime&=&\lim_{h\to0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{a^x(a^h-1)}{h}\\
&=&a^x\cdot\lim_{h\to0}\frac{a^h-1}{h}\\
\end{eqnarray}
ここで、\(a^h=e^{\log a^h}\)です(両辺の対数を取ってみれば簡単に分かります)。
故に、収束する関数の積の極限は極限の積と等しい(【解析学の基礎シリーズ】関数の極限編 その3)ので、
\begin{eqnarray}
a^x\cdot\lim_{h\to0}\frac{a^h-1}{h}&=&a^x\cdot\lim_{h\to0}\left(\frac{e^{\log a^h}-1}{\log a^h}\cdot \frac{\log a^h}{h}\right)\\
&=&a^x\cdot\lim_{h\to0}\frac{e^{\log a^h}-1}{\log a^h}\cdot \lim_{h\to0}\frac{\log a^h}{h}\\
&=&a^x\cdot\lim_{h\to0}\frac{e^{\log a^h}-1}{\log a^h}\cdot \lim_{h\to0}\log a\\
&=&a^x\cdot\lim_{h\to0}\frac{e^{\log a^h}-1}{\log a^h}\cdot \log a\\
\end{eqnarray}
です。
従って、
$$\lim_{h\to0}\frac{e^{\log a^h}-1}{\log a^h}=1$$
であれば良いです。
実はこれはほぼ証明が完了しています。
というのも補題7.を証明しているからです。
ここで、\(t=\log a^h\)とします。
\(h\to 0\)のとき、\(t\to 0\)です。
故に、
\begin{eqnarray}
a^x\cdot\lim_{h\to0}\frac{e^{\log a^h}-1}{\log a^h}\cdot \log a&=&a^x\cdot\lim_{t\to0}\frac{e^{t}-1}{t}\cdot \log a=a^x\log a
\end{eqnarray}
です。
特に\(a=e\)(ネイピア数)であれば、\(\log e=1\)により、\(\left( e^x\right)^\prime=e^x\)です。
定理8.の証明終わり
では、次に対数関数の微分について解説します。
対数関数の微分
主張を明示してしまいましょう。
定理8.の証明
真数条件から\(x>0\)ということに注意します。
※高校数学では真数条件と言っていましたが、一般に\(\log\)の定義域が\((0,\infty)\)です。
\begin{eqnarray}
\left( \log_ax\right)^\prime&=&\lim_{h\to0}\frac{\log_a(x+h)-\log_ax}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\log_a\frac{x+h}{x}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)\\
&=&\lim_{h\to0}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}}\\
\end{eqnarray}
ここで、\(\displaystyle t=\frac{h}{x}\)とすれば、\(h\to0\)で\(t\to0\)です。
また、\(\displaystyle\frac{1}{tx}=\frac{1}{h}\)です。
従って、
\begin{eqnarray}
\lim_{h\to0}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}}&=&\lim_{t\to0}\log_a(1+t)^\frac{1}{tx}\\
&=&\frac{1}{x}\cdot\lim_{t\to0}\log_a(1+t)^\frac{1}{t}\\
&=&\frac{1}{x}\cdot\log_ae\\
&=&\frac{1}{x}\cdot\frac{\log e}{\log a}=\frac{1}{x\log a}
\end{eqnarray}
です。
ここでも、\((1+x)^\frac{1}{x}\)は\(x>0\)で連続であるという事実から、\(\displaystyle\lim_{x\to0}\log(1+x)^{\frac{1}{x}}=\log e\)です。
また、対数関数の底の変換公式(定理)も使っています。
特に、\(a=e\)であれば、\(\log a=\log e=1\)ですので、\(\displaystyle\left( \log x\right)^\prime=\frac{1}{x}\)です。
定理8.の証明終わり
では最後に、\(f(x)=ax^n\)の微分を説明します。
\(f(x)=ax^n\)の微分
本来、最も基本的な関数の微分として、\(f(x)=ax^n\)の微分が挙げられると思います。
しかしながら、実はしっかり考えようとすると、そうも行きません。
\(n\in\mathbb{Q}\)の場合は、おおよそ基本的な難易度で証明が可能です。
しかし、\(n\in\mathbb{R}\)の場合は対数関数の微分の知識が必要になってきます。
従って、\(f(x)=ax^n\)は一筋縄では行きません。
故に、本記事では\(f(x)=ax^n\)の微分を最後に持ってきました。
結論から先に述べてしまいましょう。
定理9.の証明
複数の段階に分けて証明します。
0. \(n=0\)のとき
\(n=0\)ならば、\(ax^n=a\)です。
故に、
$$
\lim_{h\to0}\frac{a-a}{h}=0
$$
です。
また、\(anx^{n-1}=a\cdot 0\cdot x^0=0\)ですので、\(n=0\)のときは成り立ちます。
①\(n\in\mathbb{N}\)のとき
この証明の方法はいくつかあります。
特に二項定理を使った証明(よく見る方法)がよく見られると思います。
一方で、積の微分法を用いて数学的帰納法で示す方法もあります。
二項定理を用いた証明はいくらでも見つかるので、今回は後者で示します。
①-1. \(n=1\)のとき
\(x^n=x\)です。
このとき、
$$\lim_{h\to0}\frac{x+h-x}{h}=\lim_{h\to0}\frac{x+h-x}{h}=\cdot\lim_{h\to0}1=1=x^{1-1}$$
により、\(n=1\)のときは成り立ちます。
①-2. \(n=k\)まで成り立っているとします。
すなわち、\(\left( x^k\right)^\prime=kx^{k-1}\)が成り立っているとします。
このとき、積の微分法を使います。
詳しくは【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その2を御覧ください。
により、
\begin{eqnarray}
\left( ax^{k+1}\right)^\prime&=&\left( x^k\cdot x\right)^\prime\\
&=& \left( x^k\right)^\prime\cdot x+x^k\cdot 1\\
&=&kx^{k-1}\cdot x+x^k\\
&=&(k+1)x^{k}\\
&=&(k+1)x^{k+1-1}
\end{eqnarray}
以上から、\(n\in\mathbb{N}\)のときには成り立ちます。
②\(n\in\mathbb{Z}\)、特に\(n\)が負の整数のとき
\(n\in\mathbb{Z}\)で\(n=0\)であれば、0.の場合で、\(n>0\)であれば、①の場合です。
従って、ここでは\(n<0\)を満たす\(n\in\mathbb{Z}\)の場合を考えます。
とはいえ、①の場合に商の微分法を適用させるだけです。
商の微分法は、
でした。
詳しくは、【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その2を御覧ください。
さて、\(n\)は負の整数なので、\(n\)は\(m\in\mathbb{N}\)を用いて、\(n=-m\)と書けます。
従って、\(\displaystyle x^n=x^{-m}=\frac{1}{x^m}\)と書けます。
故に、商の微分法を使うことで、
\begin{eqnarray}
\left(\frac{1}{x^m}\right)^\prime&=&\frac{0\cdot x^m-mx^{m-1}}{\left(x^m\right)^2}\\
&=&\frac{-mx^{m-1}}{x^{2m}}\\
&=&-mx^{m-1}\cdot x^{-2m}\\
&=&-mx^{m-1-2m}\\
&=&-mx^{-m-1}\\
\end{eqnarray}
ここで、\(n=-m\)でしたので、\(-mx^{-m-1}=-(-n)\cdot x^{-(-n)-1}=nx^{n-1}\)となり、\(n\in\mathbb{Z}\)のときも成り立ちます。
③\(n\in\mathbb{Q}\)のとき、特に\(n\)が分数のとき
\(n\in\mathbb{Q}\)は\(p\in\mathbb{N}\)、\(q\in\mathbb{Z}\)を用いて\(\displaystyle n=\frac{q}{p}\)と書けます。
まずは、\(\displaystyle\left( x^\frac{1}{p}\right)^\prime\)について考えます。
これは逆関数の微分を用いて証明できます。
詳しくは、【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その4を御覧ください。
\(y=x^\frac{1}{p}\)は\(y=x^p\)の逆関数です。
従って、\(p\in\mathbb{N}\)ですので、\(y=x^\frac{1}{p}\)と書くと、
\begin{eqnarray}
\left(x^\frac{1}{p}\right)^\prime=\frac{1}{py^{p-1}}=\frac{1}{px^{\frac{p-1}{p}}}=\frac{1}{p}x^{-\frac{p-1}{p}}=\frac{1}{p}x^{\frac{1}{p}-1}
\end{eqnarray}
となります。
従って、\(\displaystyle n=\frac{1}{p}\)であれば、成り立ちます。
では、\(x^\frac{q}{p}\)について考えます。
これは合成関数の微分法を使うことで証明できます。
詳しくは【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その3を御覧ください。
\(x^\frac{q}{p}\)は\(x^q\)と\(x^\frac{1}{p}\)の合成関数です。
従って、
$$
\left(x^\frac{q}{p}\right)^\prime=\left(\left(x^\frac{1}{p}\right)^q\right)^\prime=q\left(x^\frac{1}{p}\right)^{q-1}\cdot \frac{1}{p}x^{\frac{1}{p}-1}=\frac{q}{p}x^{\frac{q-1}{p}+\frac{1}{p}-1}=\frac{q}{p}x^{\frac{q}{p}-1}
$$
ですので、\(\displaystyle n=\frac{q}{p}\)のときも成り立ちます。
④\(n\in\mathbb{R}\)のとき、特に\(n\)が無理数のとき
最後に\(n\in\mathbb{R}\)の場合について考えます。
これは少し特殊な対数微分法という証明方法を使います。
\(y=x^n\)の両辺に自然対数をとり、それを微分することで証明します。
\(\log y=\log x^n\)として、両辺を微分すると、
$$
\left( \log y\right)^\prime=\left( \log x^n\right)^\prime
$$
です。
従って、
\begin{eqnarray}
\frac{y^\prime}{y}=\frac{n}{x}&\Leftrightarrow& y^\prime=\frac{n}{x}\cdot y=\frac{n}{x}\cdot x^n=nx^{n-1}
\end{eqnarray}
です。
従って、\(n\in\mathbb{R}\)でも成り立つことが分かりました。
定理9.の証明終わり
※初等関数の微分を考える意味は次回述べます。
結
今回は、\(ax^n,\ a^x,\ \log_ax\)の微分について解説しました。
高校数学で学習しましたが、しっかり証明しようと思うと骨が折れます。
とはいえ、今までと毛色がすこし違って、比較的高校数学の範囲からあまり出ない証明だったかと思います。
とはいえ、形式的には成り立つけど、本気で考えようとするとしっかり大学数学の範囲になっています。
次回は三角関数、逆三角関数の微分法について解説します。
乞うご期待!
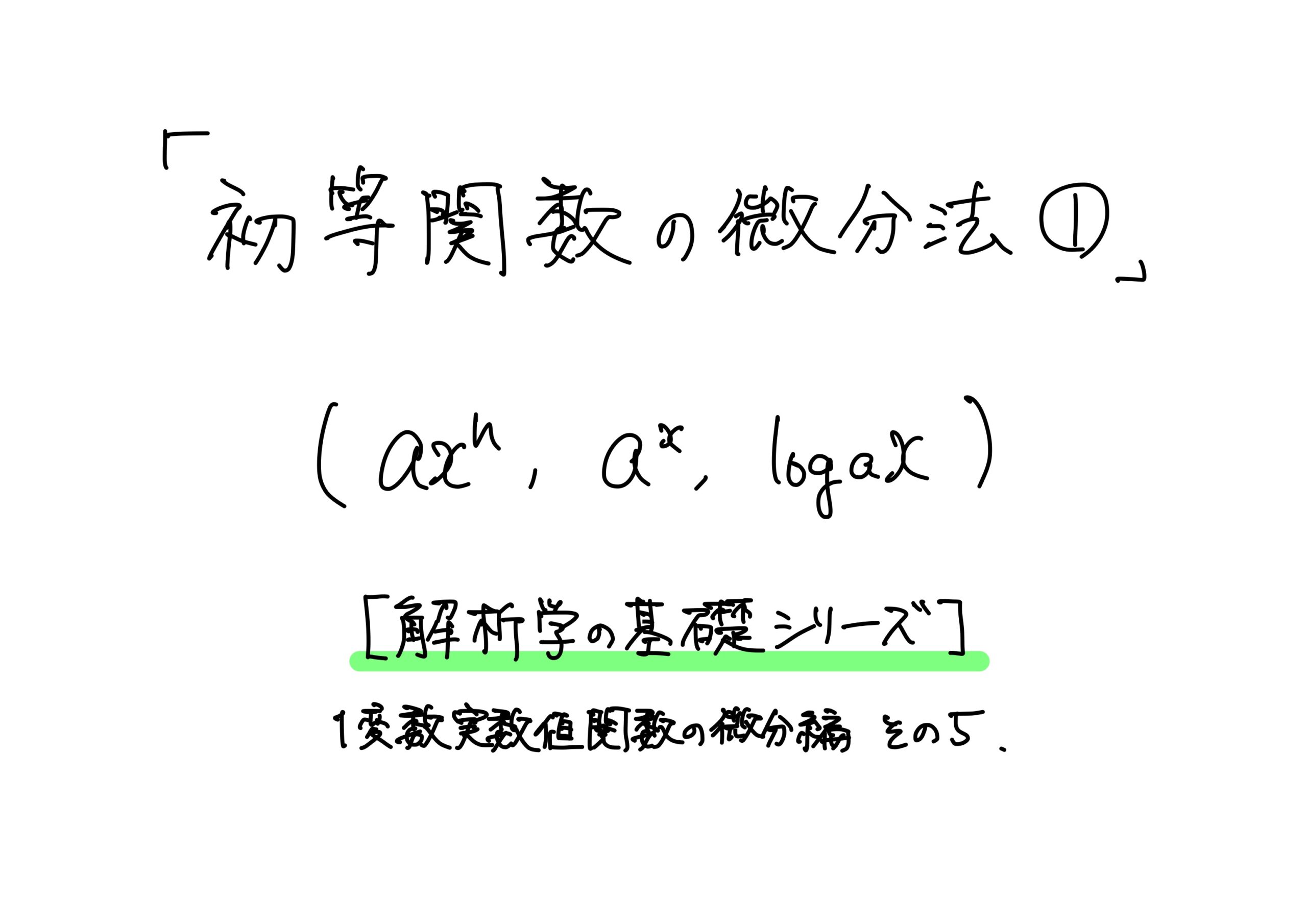



コメントをする