本記事の内容
本記事は1変数実数値関数の和・差・積・商の微分、微分可能な関数は連続な関数ということを解説する記事です。
本記事を読むにあたり、1変数実数値関数の導関数について知っている必要があるため、その際は以下の記事を参照してください。
関数の和・差・積・商の微分法
関数の和・差・積・商の微分法は高校で既に学習しています。
しかし、前提やら、どういう状況で成り立つのかということを厳密に覚えている方は実は少ないのではないでしょうか。
かくいう筆者も大学に入学したてのときはそうでした。
ここでは厳密に前提やらを確認しつつ、定理として明示します。
- \(\left(f(t)+g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)+g^\prime(t)\)
- \(\left(f(t)-g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)-g^\prime(t)\)
- \(\left(f(t)g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)g(t)+f(t)g^\prime(t)\)
- \(g(t)\neq0\)ならば、\(\displaystyle\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right)^\prime=\frac{f^\prime(t)g(t)-f(t)g^\prime(t)}{\left(g(t)\right)^2}\)
「微分係数ってなんだったっけ?」ということを思い出せば誠に簡単です。
微分係数とは何だったか、というと次です。
\(I=(a,b)\)を\(\mathbb{R}\)の開区間とし、\(f:I\to \mathbb{R}\)とする。 このとき、\(t\in I\)に対して $$ c=\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h} $$ という\(c\in \mathbb{R}\)が存在するとき、\(f\)は\(t\)で微分可能であるといい、\(c\)を\(f\)の導値、または微分係数という。このとき、 $$ c=f^\prime(t)=\frac{df}{dt}(t)=\frac{d}{dt}f(t)=\frac{df(t)}{dt}=\left(f(t)\right)^\prime=\left(Df\right)(t) $$ と書く。
詳しくは、【解析学の基礎シリーズ】変数実数値関数の微分編 その1を御覧ください。
和の微分
\(\left(f(t)+g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)+g^\prime(t)\)の証明
\(I\subset \mathbb{R}\)を\(\mathbb{R}\)の区間とします。
また、\(f:I\to \mathbb{R}\)、\(g:I\to\mathbb{R}\)が\(t\in I\)で微分可能だとします。
このとき、\(\left(f(t)+g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)+g^\prime(t)\)を示したいので、
$$
\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)+g(t+h)\right)-\left(f(t)+g(t)\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}
$$
が証明できれば良いです。
正直、明らかといえば明らかですが、筆者は「明らか」という言葉をあまり好んでいないため、ちゃんと証明します。
\begin{eqnarray}
\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)+g(t+h)\right)-\left(f(t)+g(t)\right)}{h}&=&\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)-f(t)\right)+\left(g(t+h)-g(t)\right)}{h}\\
&=&\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(t+h)-f(t)}{h}+\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right)\\
\end{eqnarray}
ここで、以下の事実の1.を使います。
\(I\)を\(\mathbb{R}\)の区間、\(f:I\to\mathbb{R}\)および\(g:I\to\mathbb{R}\)を関数、\(a\in\bar{I}\)、\(A,b\in\mathbb{R}\)とし、\(\displaystyle \lim_{x\to a}f(x)=A\)、\(\displaystyle \lim_{x\to a}g(x)=B\)とする。 このとき、次が成り立つ。
- \(\displaystyle \lim_{x\to a}(f(x)+g(x))=\lim_{x\to a}f(x)+\lim_{x\to a}g(x)=A+B\),
- \(\displaystyle \lim_{x\to a}(f(x)-g(x))=\lim_{x\to a}f(x)-\lim_{x\to a}g(x)=A-B\),
- \(\displaystyle \lim_{x\to a}f(x)g(x)=\left(\lim_{x\to a}f(x)\right)\cdot\left(\lim_{x\to a}g(x)\right)=AB\),
- \(B\neq0\)ならば、\(\delta_0>0\)が存在して、\(|x-a|<\delta_0\)なる\(x\in I\)に対して、\(g(x)\neq 0\)で、\(\displaystyle \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\displaystyle\lim_{x\to a}f(x)}{\displaystyle\lim_{x\to a}g(x)}=\frac{A}{B}\)
この事実の証明は、【解析学の基礎シリーズ】関数の極限編 その3を御覧ください。
今、変数は\(h\)です。
つまり、関数の和・差・積・商の極限における\(x\)が\(h\)で、\(a\)が\(0\)です。
また、\(f(x)\)が\(\displaystyle \frac{f(t+h)-f(t)}{h}\)で、\(g(x)\)が\(\displaystyle \frac{g(t+h)-g(t)}{h}\)です。
余談0.
\(\displaystyle u(t)=\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\)、\(\displaystyle s(t)=\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\)として、関数の和・差・積・商の極限における\(f\)が\(u\)で\(g\)が\(s\)と言ったほうが明快かもしれませんね。
余談0.終わり
さて、関数の和・差・積・商の極限の1.により、
\begin{eqnarray}
\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(t+h)-f(t)}{h}+\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right)
&=&\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\\
&=&f^\prime(x)+g^\prime(x)
\end{eqnarray}
です。
従って、
$$\left(f(t)+g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)+g^\prime(t)$$
です。
\(\left(f(t)+g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)+g^\prime(t)\)の証明終わり
次に、差です。
差の微分
\(\left(f(t)-g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)-g^\prime(t)\)の証明
和と同じなので、サクッと行きます。
\(I\subset \mathbb{R}\)を\(\mathbb{R}\)の区間とします。
また、\(f:I\to \mathbb{R}\)、\(g:I\to\mathbb{R}\)が\(t\in I\)で微分可能だとします。
このとき、\(\left(f(t)-g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)-g^\prime(t)\)を示したいので、
$$
\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)-g(t+h)\right)-\left(f(t)-g(t)\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}
$$
が証明できれば良いです。
さて、関数の和・差・積・商の極限の2.を使うことで、
\begin{eqnarray}
\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)-g(t+h)\right)-\left(f(t)-g(t)\right)}{h}&=&\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)-f(t)\right)-\left(g(t+h)-g(t)\right)}{h}\\
&=&\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right)\\
&=&\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\\
&=&f^\prime(x)-g^\prime(x)
\end{eqnarray}
です。
従って、
$$\left(f(t)-g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)-g^\prime(t)$$
です。
\(\left(f(t)-g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)-g^\prime(t)\)の証明終わり
次に、積です。
積の微分
\(\left(f(t)g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)g(t)+f(t)g^\prime(t)\)の証明
これは少々テクニカルです。
\(I\subset \mathbb{R}\)を\(\mathbb{R}\)の区間とします。
また、\(f:I\to \mathbb{R}\)、\(g:I\to\mathbb{R}\)が\(t\in I\)で微分可能だとします。
示したいことは、
$$
\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)g(t+h)\right)-\left(f(t)g(t)\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\cdot g(t)+f(t)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}
$$
です。
\begin{eqnarray}
&&\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)g(t+h)\right)-\left(f(t)g(t)\right)}{h}\\
&=&\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)g(t+h)\color{red}{-f(x)g(t+h)+f(t)g(t+h)}-f(t)g(t)}{h}\\
&=&\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)-f(t)\right)g(t+h)+f(t)\left(g(t+h)-g(t)\right)}{h}\\
\end{eqnarray}
さて、関数の和・差・積・商の極限の1.を使うことで、
\begin{eqnarray}
&&\lim_{h\to 0}\frac{\left(f(t+h)-f(t)\right)g(t+h)+f(t)\left(g(t+h)-g(t)\right)}{h}\\
&=&\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(x)}{h}\cdot g(t+h)+\lim_{h\to 0}\left(f(t)\cdot\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right)
\end{eqnarray}
です。
また、関数の和・差・積・商の極限の3.を使うことで、
\begin{eqnarray}
&&\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\cdot g(t+h)\right)+\lim_{h\to 0}\left(f(t)\cdot\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right)\\
&=&\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\cdot \lim_{h\to 0}g(t+h)+\lim_{h\to 0}f(t)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\\
\end{eqnarray}
です。
ここで、\(\displaystyle\lim_{h\to 0}f(t)=f(t)\)、\(\displaystyle\lim_{h\to 0}g(t+h)=g(t)\)です。
後者については証明を与えます。
「当然じゃね?」と思うかもしれませんが、証明します。
補題1.の証明
示したいことは、
$$(\forall \epsilon>0)\ (\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ \left(\forall h\in I:0<|h|<\delta\Rightarrow|g(t+h)-g(t)|<\epsilon\right)$$
です。
\(g\)は\(t\)で微分可能ですので、
$$
(\exists c\in\mathbb{R})\ {\rm s.t.}\ c=\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}
$$
です。
すなわち、
$$(\forall \epsilon>0)\ (\exists \delta_0>0)\ {\rm s.t.}\ \left(\forall h\in I:0<|h|<\delta_0\Rightarrow\left|\frac{g(t+h)-g(t)}{h}-c\right|<\epsilon\right)$$
です。
つまり、\(0<|h|<\delta_0\)を満たす\(h\in I\)に対しては、\(\displaystyle\left|\frac{g(t+h)-g(t)}{h}-c\right|<\epsilon\)が成り立っています。
従って、\(0<|h|<\delta_0\)を満たす\(h\in I\)に対しては、\(\displaystyle\left|\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right|-|c|<\epsilon\)が成り立っています。
故に、任意の\(\epsilon>0\)に対して\(\displaystyle\delta=\frac{\epsilon}{\epsilon+|c|}\)とすれば、
\begin{eqnarray}
|g(t+h)-g(t)|&=&\left|h\cdot \frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right|\\
&=&|h|\cdot \left|\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right|\\
&<&\delta\cdot (\epsilon+|c|)=\frac{\epsilon}{\epsilon+|c|}\cdot (\epsilon+|c|)=\epsilon
\end{eqnarray}
となるので、\(\displaystyle\lim_{h\to 0}g(t+h)=g(t)\)です。
補題1.の証明終わり
さて、補題1.により
\begin{eqnarray}
&&\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\cdot \lim_{h\to 0}g(t+h)+\lim_{h\to 0}f(t)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\\
&=&\left(\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\right)\cdot g(t)+f(t)\cdot\left(\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right)\\
&=&f^\prime(t)g(t)+f(t)g^\prime(t)
\end{eqnarray}
となるので、証明完了です。
\(\left(f(t)g(t)\right)^\prime=f^\prime(t)g(t)+f(t)g^\prime(t)\)の証明終わり
余談1.
積の微分の証明は高校数学でも証明されています。
証明のエッセンスとしては、「帳尻を合わせるために、\(f(t)g(t+h)\)を加えて、引く」です。
これは関数の和・差・積・商の極限の3.および4.を示すときにも同じ手を使っています。
つまり、積、商の極限の証明のエッセンスは実は高校数学で既に学んでいた、ということです。
とはいえ、「そんなん覚えてねえです」という方が大半だと思います。
かくいう筆者もそうでした。
しかし、「エッセンスは高校数学で学んでいたんだなあ」と思うと高校数学も馬鹿にできないなと思いました。
余談1.おわり
最後に商の微分です。
商の微分
\(g(t)\neq0\)ならば、\(\displaystyle\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right)^\prime=\frac{f^\prime(t)g(t)-f(t)g^\prime(t)}{\left(g(t)\right)^2}\)の証明
\(I\subset \mathbb{R}\)を\(\mathbb{R}\)の区間とします。
また、\(f:I\to \mathbb{R}\)、\(g:I\to\mathbb{R}\)が\(t\in I\)で微分可能だとします。
示したいことは、
$$
\lim_{h\to 0}\frac{\displaystyle\frac{f(t+h)}{g(t+h)}-\frac{f(t)}{g(t)}}{h}=\frac{1}{\left(g(t)^2\right)}\left(\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\cdot g(t)-f(t)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right)
$$
です。
\begin{eqnarray}
\lim_{h\to 0}\frac{\displaystyle\frac{f(t+h)}{g(t+h)}-\frac{f(t)}{g(t)}}{h}&=&\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)\cdot g(t)-f(t)\cdot g(t+h)}{h\cdot g(t+h)\cdot g(t)}\\
&=&\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)\cdot g(t)-f(t)\cdot g(t+h)\color{red}{+f(t)g(t)-f(t)g(t)}}{h\cdot g(t+h)\cdot g(t)}\\
&=&\lim_{h\to 0}\frac{g(t)\cdot\left\{f(t+h)-f(t)\right\}-f(t)\cdot\left\{\cdot g(t+h)-g(t)\right\}}{h\cdot g(t+h)\cdot g(t)}\\
&=&\lim_{h\to 0}\frac{\displaystyle g(t)\cdot\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-f(t)\cdot\frac{g(t+h)-g(t)}{h}}{g(t+h)\cdot g(t)}\\
\end{eqnarray}
ここで、\(\displaystyle\lim_{h\to0}\left(g(t+h)\cdot g(t)\right)\neq 0\)です。
実際、補題1.を使うことにより、
\begin{eqnarray}
\lim_{h\to0}\left(g(t+h)\cdot g(t)\right)=\lim_{h\to 0}g(t+h)\cdot \lim_{h\to0}g(t)=g(t)\cdot g(t)=\left(g(t)\right)^2
\end{eqnarray}
今、\(g(t)\neq0\)ですので、\(\left(g(t)\right)^2\neq0\)です。
従って、\(\displaystyle\lim_{h\to0}\left(g(t+h)\cdot g(t)\right)\neq 0\)です。
\(\displaystyle\lim_{h\to0}\left(g(t+h)\cdot g(t)\right)\neq 0\)ですから、関数の和・差・積・商の極限の4.を使うことができます。
関数の和・差・積・商の極限の4.により、
\begin{eqnarray}\
&&\lim_{h\to 0}\frac{\displaystyle g(t)\cdot\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-f(t)\cdot\frac{g(t+h)-g(t)}{h}}{g(t+h)\cdot g(t)}\\
&=&\frac{\displaystyle\lim_{h\to 0} \left\{g(t)\cdot\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-f(t)\cdot\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right\}}{\displaystyle\lim_{h\to 0}\left\{g(t+h)\cdot g(t)\right\}}\\
\end{eqnarray}
です。
また、関数の和・差・積・商の極限の2.と3.により、
\begin{eqnarray}
&&\frac{\displaystyle\lim_{h\to 0} \left\{g(t)\cdot\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-f(t)\cdot\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right\}}{\displaystyle\lim_{h\to 0}\left\{g(t+h)\cdot g(t)\right\}}\\
&=&\frac{\displaystyle\lim_{h\to 0} \left\{g(t)\cdot\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\right\}-\lim_{h\to 0} \left\{f(t)\cdot\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right\}}{\displaystyle\lim_{h\to 0}g(t+h)\cdot \lim_{h\to 0}g(t)}\\
&=&\frac{\displaystyle\lim_{h\to 0}g(t)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-\lim_{h\to 0} f(t)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}}{\left(g(t)\right)^2}\\
&=&\frac{\displaystyle g(t)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-f(t)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}}{\left(g(t)\right)^2}\\
&=&\frac{\displaystyle g(t)\cdot f^\prime(t)-f(t)\cdot g^\prime(t)}{\left(g(t)\right)^2}\\
\end{eqnarray}
従って、
$$
\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right)^\prime=\frac{\displaystyle g(t)\cdot f^\prime(t)-f(t)\cdot g^\prime(t)}{\left(g(t)\right)^2}
$$
です。
\(g(t)\neq0\)ならば、\(\displaystyle\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right)^\prime=\frac{f^\prime(t)g(t)-f(t)g^\prime(t)}{\left(g(t)\right)^2}\)の証明おわり
本当に成り立つのかネ?
成り立ちます。
簡単ではありますが、例を挙げます。
「簡単すぎてためにならねえぞ?」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、次次回(もうちょっと後かも)に代表的な初等関数の微分法について解説しますので、それまでお待ち下さい。
例. \(f:(0,2)\to\mathbb{R}\)が\(f(x)=x^3\)、\(g:(0,2)\to\mathbb{R}\)が\(g(x)=2x^2\)とします。
まず、
\begin{eqnarray}
f^\prime(x)=\left(x^3\right)^\prime=\lim_{h\to0}\frac{(x+h)^3-x^3}{h}=3x^2\\
g^\prime(x)=\left(2x^2\right)^\prime=\lim_{h\to0}\frac{2(x+h)^2-2x^2}{h}=4x\\
\end{eqnarray}
に注意しておきます。
和について
\begin{eqnarray}
&&\lim_{h\to0}\frac{(x+h)^3+2(x+h)^2-x^3-2x^2}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{x^3+3x^2h+3xh^2+h^3+2x^2+4xh+2h^2-x^3-2x^2}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{3x^2h+3xh^2+h^3+4xh+2h^2}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}(3x^2+3xh+h^2+4x+2h)\\
&=&3x^2+4x\\
&=&\left(x^3\right)^\prime+\left(2x^2\right)^\prime
\end{eqnarray}
従って、成り立ちます。
差について
\begin{eqnarray}
&&\lim_{h\to0}\frac{(x+h)^3-2(x+h)^2-x^3+2x^2}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{x^3+3x^2h+3xh^2+h^3-2x^2-4xh-2h^2-x^3+2x^2}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{3x^2h+3xh^2+h^3-4xh-2h^2}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}(3x^2+3xh+h^2-4x-2h)\\
&=&3x^2-4x\\
&=&\left(x^3\right)^\prime-\left(2x^2\right)^\prime
\end{eqnarray}
従って、成り立ちます。
積について
\begin{eqnarray}
&&\lim_{h\to0}\frac{(x+h)^3\cdot2(x+h)^2-x^3\cdot2x^2}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{2(x+h)^5-2x^5}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\frac{2x^5+10x^4h+20x^3h^2+20x^2h^3+10xh^4+5h^5-2x^5}{h}\\
&=&\lim_{h\to0}\left(10x^4+20x^3h+20x^2h^2+10xh^3+5h^4\right)\\
&=&10x^4\\
&=&3x^2\cdot 2x^2+x^3\cdot4x\\
&=&\left(x^3\cdot2x^2\right)^\prime
\end{eqnarray}
従って、成り立ちます。
商について
\begin{eqnarray}
\lim_{h\to0}\frac{\displaystyle\frac{(x+h)^3}{2(x+h)^2}-\frac{x^3}{2x^2}}{h}
&=&\lim_{h\to0}\frac{\displaystyle\frac{x+h}{2}-\frac{x}{2}}{h}\\
&=&\frac{1}{2}\lim_{h\to0}\frac{x+h-x}{h}\\
&=&\frac{1}{2}\lim_{h\to0}1\\
&=&\frac{1}{2}\\
&=&\left(x^3\cdot2x^2\right)^\prime\\
&=&\frac{2x^4}{4x^4}=\frac{6x^4-4x^4}{4x^4}=\frac{3x^2\cdot2x^2-x^3\cdot4x}{\left(2x^2\right)^2}\\
&=&\frac{\left(x^3\right)^\prime\cdot2x^2-x^3\cdot\left(2x^2\right)^\prime}{\left(2x^2\right)^2}\\
\end{eqnarray}
従って、成り立ちます。
結
今回は、和差積商の微分法の証明を与えました。
事実としては高校数学で学習していますし、証明っぽいものも高校数学で学習しています。
しかし、そもそも高校数学では極限が厳密に説明されているわけではないため、高校数学での和差積商の微分法の証明も厳密ではありません。
ただ、証明のエッセンスとしては高校数学で学習しています。
「高校数学で学習したし、サクッと終わるっしょ」と思っていましたが「厳密に証明しようと思うと、結構骨が折れるものだな」と感じました。
次回は合成関数の微分について解説します。
乞うご期待!質問、コメントなどお待ちしております!
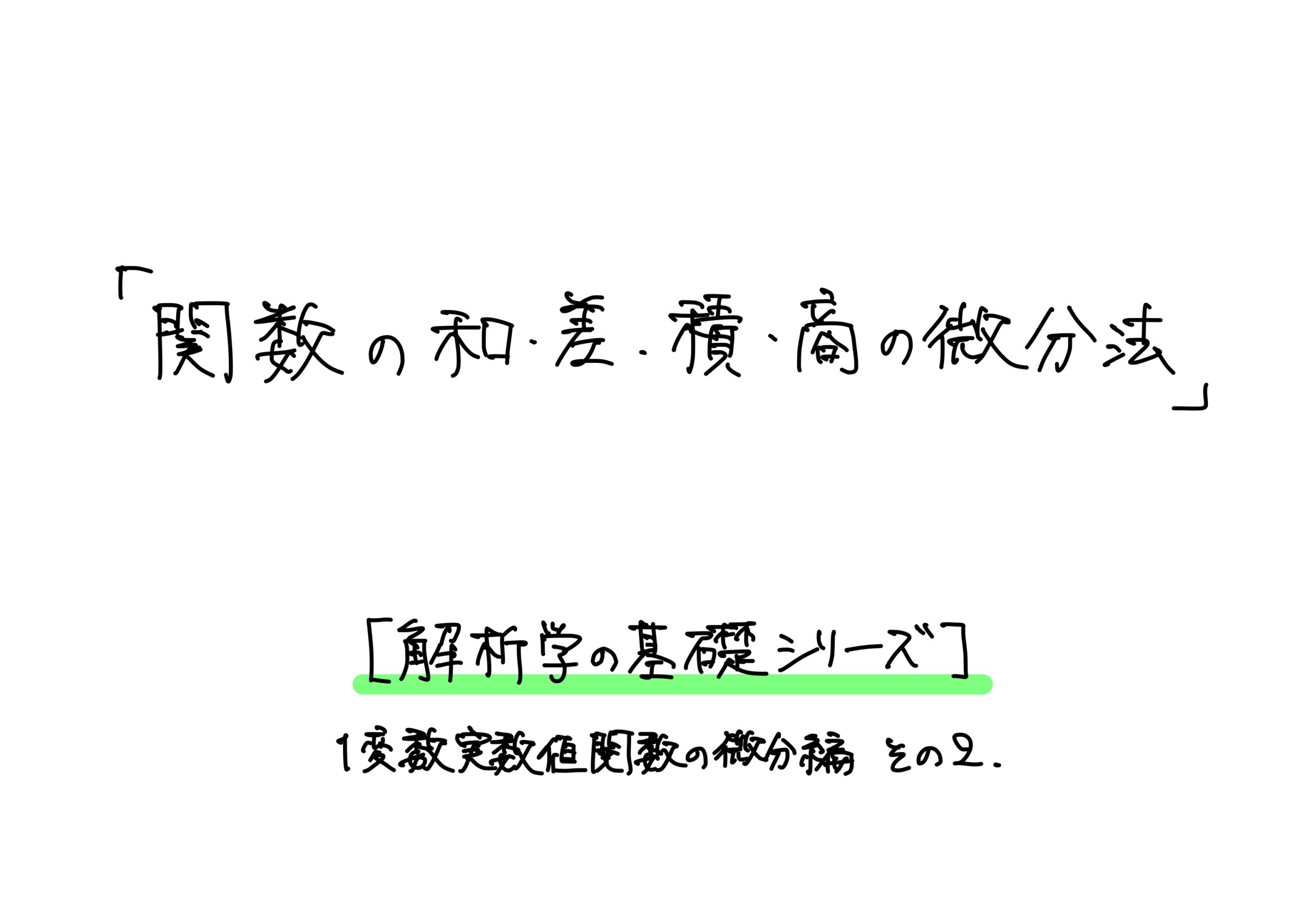



コメントをする