本記事の内容
本記事は「線型空間って何?」「線型結合って何?」「部分空間って何?」ということについて解説する記事です。
本記事を読むにあたり、論理の初歩と集合の初歩について知っている必要があるため、以下の記事も合わせて御覧ください。
↓論理の初歩(シリーズ化しているため一部の記事のリンクを掲載しています。)
↓集合の初歩(シリーズ化しているため一部の記事のリンクを掲載しています。)
そういえば、ベクトルって何よ?
今までさも当然のように2つの数の組を\(2\)次元のベクトル、3つの数の組を\(3\)次元のベクトルというように\(n\)個の数の組を\(n\)次元のベクトルというように呼んできました。
というのも「ベクトルって高校数学で習ったよね?」という前提に立っていたからです。
では、高校数学では”ベクトル”がどのように説明されていたかというと
だったかと思います。
確かに、\(2\)個の数の組は平面で表すと座標に対応して、原点\(O\)からその座標への矢印を描くと「向き」を持っているし、その矢印の大きさは原点とその点との距離として考えることができます。
しかしながら、これはあくまで直感的です。
勿論、間違っている、といっているわけではありません。
しかし厳密でない、と言っているのです。
では、「ベクトルとは何か?」というと、結論としては以下です。
です。
つまり、線型空間と呼ばれる集合の要素をベクトルと呼んで、\(n\)個の数の組は線型空間の要素なのでベクトルと呼べる、という話なのです。
ここで注意なのが、勿論先の通り\(n\)個の数の組はベクトル(線型空間の要素)ですが、「線型空間って\(n\)個の数の組を集めた集合なのかあ」というと違います。
といもの、これは後で述べますが、\((m,n)\)型の行列すべてを集めた集合も、開区間\((a,b)\)上の実数値連続関数すべてを集めた集合も線型空間となります。
すなわち、\((m,n)\)型の行列もベクトルですし、開区間\((a,b)\)上の実数値連続関数もベクトルなのです。
何が言いたいか、というと「ベクトル」と言われたとて必ずしも\(n\)個の数の組ではない、ということです。
ただ、このシリーズではもっぱら\(n\)個の実数の組について、すなわち今まで扱ってきたベクトルを扱いますので「ベクトルと言われたらば、今まで通りのベクトルなんだな」と思って頂いて結構です。
しかし、「必ずしもそうじゃないよ」ということを念頭に置いてほしい、ということです。
線型空間(ベクトル空間)
先の導入を読んでいただいた方は「もしかして?」と思ったかもしれませんが、要は線型空間とは\(n\)個の数の組が満たす条件を抽出して一般化したものです。
もっと端的に言えば、\(\mathbb{C}^n\)(\(\mathbb{R}^n\)でもOK)を一般化したものが線型空間です。
線型空間を一言で
一言でいうと、先の通り\(\mathbb{R}^n\)の一般化、ということなのですが、もうちょっとだけ具体的に言うと、
です。
「じゃあ特別な条件って何よ?」という話ですが、平たく言うと
- 和については交換則、結合則、単位元と逆元の存在が保証されている。
- スカラー倍については結合則、分配則、単位元の存在が保証されている。
という条件です。
「なにいってっかわかんねえ」となるかもしれませんが、「ふーん」程度でOKです。
直感的に言うとそんなところです。
で、線型空間って何スか?
では、「線型空間とは何か」という厳密な話をしましょう。
線型空間の説明はちょっと長いですが、今まで扱った\(\mathbb{R}^n\)をイメージしながら読むと「なるほどね」とイメージが付きやすいと思いますので、それを念頭に置いて読んでほしいです。
線型空間(ベクトル空間)
集合\(V\)が次の2条件Ⅰ.およびⅡ.を満たすとき、\(V\)を複素線型空間、複素ベクトル空間、\(\mathbb{C}\)上の線型空間(ベクトル空間)という。- 任意の\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V\)に対して、和と呼ばれる第三の\(V\)の要素(これを\(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\in V\)と書く)が定まり、次の法則が成り立つ。
- \((\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})+\boldsymbol{z}=\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})\quad\)(結合則)
- \(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}\quad\)(交換則)
- 零ベクトルと呼ばれる特別な要素(これを\(\boldsymbol{0}\)で表す)がただ1つ存在して、任意の\(\boldsymbol{x}\in V\)に対して\(\boldsymbol{0}+\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}\)が成り立つ。
- 任意の\(\boldsymbol{x}\in V\)に対して、\(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^\prime=\boldsymbol{0}\)となる\(\boldsymbol{x}^\prime\in V\)がただ1つ存在する。これを\(\boldsymbol{x}\)の逆ベクトルといい、\(-\boldsymbol{x}\)で表す。
- 任意の\(x\in V\)と任意の\(c\in\mathbb{C}\)に対して、\(\boldsymbol{x}\)の\(c\)倍と呼ばれるもう1つの\(V\)の要素(これを\(c\boldsymbol{x}\in V\)で表す)が定まり、次の法則が成り立つ、
- 任意の\(c,d\in\mathbb{C}\)に対して\((c+d)\boldsymbol{x}=c\boldsymbol{x}+d\boldsymbol{x}\)
- \(c(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=c\boldsymbol{x}+c\boldsymbol{y}\)
- 任意の\(c,d\in\mathbb{C}\)に対して、\((cd)\boldsymbol{x}=c(d\boldsymbol{x})\)
- \(1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}\)
この上の文章において「複素」の部分をすべて「実」で置き換えれば実線型空間が定まります。
ちなみに、1.により、任意の3つのベクトル\(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\in V\)に対して、\((\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}\)を\(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}\)とカッコをつけないで書いたり、足し算をする順序を変えて\(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}\)と書いてもOKだ、ということが保証されます。
これを見て、まず思うことといえば「ひゃあ、こら長いわ」だと思います。
筆者もそうでした。
しかし、ぜひ覚えてほしいです。
以前の記事の余談で数学と暗記についてをちょっと語りましたが、これは暗記してほしいものになります。
「こんな意味わかんねえものを覚えるなんてやだよ、無理だよ」と思うかもしれませんが、\(V\)を\(\mathbb{R}^n\)だと思えば割と「そりゃそうでしょ」となると思うので、\(\mathbb{R}^n\)と紐付けると覚えやすいと思います。
代数を、というより群を少し学んでいる方にとっては、「加法群であってスカラー倍に対して、分配則と結合則と単位元の存在が保証されてるのね」と覚えることが可能です。
とはいえ、このように覚えるにはそもそも群について覚える必要があるため、覚える手間はさほど変わりません。
入り口が群なのか線型空間の違いで、最初に出てきたほうを最初に覚える、という単にそれだけの話です。
ちょっとしたエッセンス(?)でした。
で、どんなのが線型空間なんスか?(線型空間の例)
まず、\(\mathbb{R}^n\)は線型空間です。
めちゃくちゃ簡単に確かめることができますが、殆ど先の線型空間が満たすべき条件を写経するだけになってしますので、省略します。
ここではベクトルって何よ?で述べた開区間\((a,b)\)上の実数値連続関数すべてを集めた集合が線型空間であることを確かめてみます。
例1.\(V\)を開区間\((a,b)\)上の連続な実数値関数の集合とします。
すなわち、
$$
V=\left\{f:(a,b)\to\mathbb{R}\middle| fは(a,b)で連続 \right\}
$$
つまり、\(V\)は関数の(写像の)集合だ、ということです。
任意の\(f,g\in V\)、任意の\(x\in(a,b)\)および任意の\(c\in\mathbb{R}\)に対して
$$
(f+g)(x)=f(x)+g(x)\\
(cf)(x)=cf(x)
$$
として和とスカラー倍を定めると、\(V\)は線型空間です。
ちょっと面倒ですが、確かめてみます。
「ほーん。だったらⅠ.とⅡ.を確かめればいいんでしょ?」ということですが、その前に確かめなければならないことがあります(結構忘れがちだと筆者は勝手に思っています)。
それは、\(f+g\in V\)と\(cf\in V\)です。
これらが成り立たないとⅠ.およびⅡ.を確かめようがありません。
①\(f+g\in V\)と\(cf\in V\)か?
ということで、まずは\(f+g\in V\)と\(cf\in V\)を確かめます。
確かめると言ってもほとんど明らかなものですが、\(f,g\in V\)ですので\(f\)および\(g\)は\((a,b)\)上で連続な実数値関数です。
故に、その和をとっても、すなわち\(f+g\)も\((a,b)\)で連続な実数値関数です。
実際、以下が成り立っていたからです。
定理2.
\(I\)を\(\mathbb{R}\)の区間、\(f:I\to\mathbb{R}\)、\(g:I\to\mathbb{R}\)とする。- \(a\in I\)とし、\(f\)と\(g\)は\(a\)で連続とするとき、次が成り立つ。
- \(f(x)+g(x)\)、\(f(x)-g(x)\)、\(f(x)g(x)\)は\(a\)で連続である。すなわち、
- \(\displaystyle \lim_{x\to a}(f(x)+g(x))=f(a)+g(a)\),
- \(\displaystyle \lim_{x\to a}(f(x)-g(x))=f(a)-g(a)\),
- \(\displaystyle \lim_{x\to a}(f(x)g(x))=f(a)g(a)\).
- \(\displaystyle g(a)\neq 0\)ならば、\(\dfrac{f(x)}{g(x)}\)は\(a\)で連続である。すなわち、 $$\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{f(a)}{g(a)}$$ である。
- \(f(x)+g(x)\)、\(f(x)-g(x)\)、\(f(x)g(x)\)は\(a\)で連続である。すなわち、
- \(f\)と\(g\)は\(I\)で連続であるとするとき、次が成り立つ。
- \(f(x)+g(x)\)、\(f(x)-g(x)\)、\(f(x)g(x)\)は\(I\)で連続である。すなわち、
- \(\displaystyle(\forall a\in I) \lim_{x\to a}(f(x)+g(x))=f(a)+g(a)\),
- \(\displaystyle(\forall a\in I) \lim_{x\to a}(f(x)-g(x))=f(a)-g(a)\),
- \(\displaystyle(\forall a\in I) \lim_{x\to a}(f(x)g(x))=f(a)g(a)\).
- \(\displaystyle g(a)\neq 0\)ならば、\(\dfrac{f(x)}{g(x)}\)は\(I’=\{x\in\mid g(x)\neq 0\}\)で連続である。すなわち、 $$(\forall a\in I’)\ \lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{f(a)}{g(a)}$$ である。
- \(f(x)+g(x)\)、\(f(x)-g(x)\)、\(f(x)g(x)\)は\(I\)で連続である。すなわち、
定理2.の証明は【解析学の基礎シリーズ】関数の極限編 その7を御覧ください。
というわけで\(f+g\)も\((a,b)\)で連続な実数値関数ですので\(f+g\in V\)です。
また、定理2.の\(g\)を定数関数だと思えば、\(cf\)も\((a,b)\)で連続な実数値関数ですので\(cf\in V\)です。
②線型空間の条件を満たすか確かめる。
- \(f,g,h\in V\)に対して\((f+g)+h=f+(g+h)\)か?
\begin{eqnarray}
\left\{(f+g)+h(x)\right\}(x)&=&(f+g)(x)+h(x)\\
&=&f(x)+g(x)+h(x)\\
&=&f(x)+(g+h)(x)\\
&=&\left\{f+(g+h) \right\}(x)
\end{eqnarray}
となるので、成り立ちます。 - \(f+g=g+f\)か?
$$
(f+g)(x)=f(x)+g(x)=g(x)+f(x)=(g+f)(x)
$$
となるので、成り立ちます。 - 零ベクトルは存在するか?
\(\boldsymbol{0}:(a,b)\to\mathbb{R}\)を任意の\(x\in(a,b)\)に対して\(\boldsymbol{0}(x)=0\)と定めると、\(\boldsymbol{0}\)は定数関数なので、\((a,b)\)で連続だから\(\boldsymbol{0}\in V\)です。
また、
$$
(\boldsymbol{0}+f)(x)=\boldsymbol{0}(x)+f(x)=0+f(x)=f(x)
$$
となりますので、\(\boldsymbol{0}\)は\(V\)における零ベクトルです。 - 逆ベクトルは存在するか?
任意の\(f\in V\)に対して、定理2.から\(-f\)も\((a,b)\)で連続な実数値関数ですので\(-f\in V\)です。
また、
$$
\left\{f+(-f) \right\}(x)=f(x)+(-f)(x)=f(x)+(-f(x))=f(x)-f(x)=0=\boldsymbol{0}(x)
$$
となるので、成り立ちます。
一意性については\(-f(x)\)のダミーとして\(\tilde{f}\)を用意して同じ計算をすると\(-f=\tilde{f}\)が導けるので、成り立ちます。 - 任意の\(c,d\in\mathbb{R}\)に対して\((c+d)f=cf+df\)か?
$$
\left\{(c+d)f\right\}(x)=(c+d)f(x)=cf(x)+df(x)=(cf)(x)+(df)(x)
$$
となるので成り立ちます。 - \(c\in\mathbb{R}\)、\(f,g\in V\)に対して\(c(f+g)=cf+cg\)か?
$$
\left\{c(f+g)\right\}(x)=c(f+g)(x)=c\left\{f(x)+g(x)\right\}=cf(x)+cg(x)=(cf)(x)+(cg)(x)
$$
となるので、成り立ちます。 - 任意の\(c,d\in\mathbb{R}\)に対して\((cd)f=c(df)\)か?
$$
\left\{(cd)f\right\}(x)=(cd)f(x)=c\left( df(x)\right)=c(df)(x)=\left\{c(df)\right\}(x)
$$
となるので、成り立ちます。 - \(1f=f\)か?
$$
(1f)(x)=1\cdot f(x)=f(x)
$$
となるので、成り立ちます。
以上のことから、\(V\)は実線型空間です。
いやあ、長かったですねえ。
真面目に確かめようとすると、8個(厳密には10個)の条件を確かめる必要があるので、誠に面倒ですが、基本的に真面目にやるしかありません。
お疲れさまでした。
線型空間のちょっとした性質
先の線型空間の零ベクトルと逆ベクトルの部分で、「零ベクトルと呼ばれるベクトルがただ1つ存在して…」という文言と「逆ベクトルがただ1つ存在する」という文言ありました。
実は、零ベクトルと逆ベクトルがただ1つだけ存在するということを述べなくても、別の条件から1つしか存在しないということが導けます。
そういう意味では零ベクトルが1つしか存在しないという文言、逆ベクトルが1つしか無いという文言は消してしまってもOKです。
定理3.
線型空間\(V\)において、零ベクトル\(\boldsymbol{0}\)は唯一つである。また、逆ベクトルは唯一つである。定理3.の証明
①零ベクトルについて
仮にベクトル\(\boldsymbol{0}^\prime\in V\)が任意の\(\boldsymbol{a}\)に対して\(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{0}^\prime=\boldsymbol{a}\)を満たしていたとします。
このとき、\(\boldsymbol{a}\in V\)は任意ですので、\(\boldsymbol{a}\)を\(\boldsymbol{0}\)としてもOKです。
故に、
$$
\boldsymbol{0}+\boldsymbol{0}^\prime=\boldsymbol{0}
$$
が成り立ちます。
また、線型空間の公理の3.の\(\boldsymbol{x}\in V\)は任意ですので、\(\boldsymbol{x}\)を\(\boldsymbol{0}^\prime\)としてもOKです。
故に、
$$
\boldsymbol{0}^\prime+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}^\prime
$$
ですので、\(\boldsymbol{0}^\prime=\boldsymbol{0}\)が成り立ちます。
②逆ベクトルについて
次に、\(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}^{\prime\prime}=\boldsymbol{0}\)とすると、
$$
\boldsymbol{a}^\prime+(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}^{\prime\prime})=\boldsymbol{a}^\prime+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{a}^\prime
$$
一方で、線型空間の公理の2.により、
$$
\boldsymbol{a}^\prime+(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}^{\prime\prime})=(\boldsymbol{a}^\prime+\boldsymbol{a})+\boldsymbol{a}^{\prime\prime}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{a}^{\prime\prime}=\boldsymbol{a}^{\prime\prime}
$$
となるので、\(\boldsymbol{a}^\prime=\boldsymbol{a}^{\prime\prime}\)が成り立ちます。
定理3.の証明終わり
次に、「当たり前な気がするけどちゃんと成り立ってるのね」という事実を証明します。
定理4.
\(\boldsymbol{a}\)およびスカラー\(\lambda\)に対して、\(\lambda\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}\)であれば、\(\lambda=0\)かまたは\(\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}\)である。定理4.の証明
簡単です。
\(\lambda\neq0\)とすると、\(\lambda^{-1}(\lambda\boldsymbol{a})=\lambda^{-1}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}\)です。
一方で、
$$
\lambda^{-1}(\lambda\boldsymbol{a})=(\lambda^{-1}\lambda)\boldsymbol{a}=1\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}
$$
となって\(\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}\)です。
定理4.の証明終わり
線型結合(一次結合)
線型結合を一言でいうと、
です。
「え?いる?これ?」と思うかもしれませんが、後に解説する線型独立やらを語るときに必要になってきます。
これをしっかり書くと以下です。
線型結合(一次結合)
線型空間\(V\)のベクトル\(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\dots,\boldsymbol{a}_n\)とスカラー\(c_1,c_2,\dots,c_n\)に対して、スカラー倍の和 $$ c_1\boldsymbol{a}_1+c_2\boldsymbol{a}_2+\dots+c_n\boldsymbol{a}_n $$ をベクトル\(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\dots,\boldsymbol{a}_n\)の線型結合または一次結合という。線型空間\(\mathbb{R}^n\)において、\(\mathbb{R}^n\)の標準基底
$$
\boldsymbol{e}_1=
\left(
\begin{array}{c}
1\\
0\\
\vdots \\
\vdots \\
0
\end{array}
\right),\quad
\boldsymbol{e}_2=
\left(
\begin{array}{c}
0\\
1\\
0 \\
\vdots \\
0
\end{array}
\right),\cdots,
\boldsymbol{e}_n=
\left(
\begin{array}{c}
0\\
\vdots\\
\vdots \\
0 \\
1
\end{array}
\right)
$$
を用いると、任意の\(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\)は
\begin{eqnarray}
\boldsymbol{x}&=&
\left(
\begin{array}{c}
x_1\\
x_2\\
\vdots \\
x_n
\end{array}
\right)=
x_1
\left(
\begin{array}{c}
1\\
0\\
\vdots \\
\vdots \\
0
\end{array}
\right)+
x_2
\left(
\begin{array}{c}
0\\
1\\
0 \\
\vdots \\
0
\end{array}
\right)+\cdots+
x_n
\left(
\begin{array}{c}
0\\
\vdots\\
\vdots \\
0 \\
1
\end{array}
\right)\\
&=&
x_1\boldsymbol{e}_1+x_2\boldsymbol{e}_2+\dots+x_n\boldsymbol{e}_n
\end{eqnarray}
と書き表すことができます。
すなわち、任意の\(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\)は標準基底\(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\)の線型結合として表される、ということです。
部分空間(部分ベクトル空間)
では次に、線型空間の部分集合についてお話します。
部分空間って何スか?
部分空間を一言でいうと、
という単にそれだけです。
これをしっかり書くと以下です。
部分空間、部分ベクトル空間
線型空間\(V\)の空でない部分集合\(W\)が、\(V\)における和とスカラー倍の演算によって線型空間になるとき、\(W\)を\(V\)の部分空間、または部分ベクトル空間という。ポイントとしては、\(V\)の和とスカラー倍という演算に対して、というところです。
要するに同じ演算によって線型空間となるときに\(W\)は\(V\)の部分空間といいます。
つまり、\(W\subset V\)だったとしても、必ずしも\(W\)は線型空間ではないですし、\(W\subset V\)でかつ\(W\)が線型空間だったとしても、\(W\)の演算と\(V\)の演算が異なっていれば、\(W\)は\(V\)の部分空間ではありません。
「え、ちょっとまって。もしかして部分空間だと示すんだったらまた8個の条件を確認しなきゃいけないの?」と思うかもしれませんが、なんと、有用な事実があります。
部分空間であることの必要十分条件
定理5.(部分空間の必要十分条件その1)
線型空間\(V\)の部分集合\(W\)が部分空間であるための必要十分条件は次の3条件が成り立つことである。- \(W\neq \emptyset\quad\)(\(\emptyset\)は空集合)
- \(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\Rightarrow \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W\)
- \(\boldsymbol{a}\in W\)、\(\lambda\in\mathbb{R}\Rightarrow\lambda\boldsymbol{a}\in W\)
筆者調べではありますが、この定理の証明は「明らかだよね」ということで殆ど書かれていない書籍が多い感じがします。
勿論、すでに部分空間を学んでいる筆者はその気持ちもわからんではないのですが「いや、ちゃんと示そうよ」と思うので、しっかり証明します。
定理5.の証明
①\(W\)が線型空間\(V\)の部分空間\(\Rightarrow\)1.、2.、3.の証明
\(W\)が線型空間\(V\)の部分空間だとします。
このとき、\(W\)は\(V\)と同じ和、スカラー倍で線型空間です。
(1.の証明)
\(W\)は\(V\)の部分集合であって、かつ\(V\)と同じ和とスカラー倍によって線型空間ですので、任意の\(\boldsymbol{a}\in W\)に対して、\(0\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}\in W\)です。
従って、\(\boldsymbol{0}\in W\)だから\(W\neq\emptyset\)です。
(2.の証明)
\(W\)は線型空間ですので、任意の\(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\)に対して、その和\(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W\)です。
(3.の証明)
\(W\)は線型空間ですので、任意の\(\boldsymbol{a}\in W\)および任意の\(c\in \mathbb{R}\)に対して、そのスカラー倍\(c\boldsymbol{a}\in W\)です。
②1.、2.、3.\(\Rightarrow\)\(W\)が線型空間\(V\)の部分空間の証明
これは、①に比べると8つの条件を確かめる必要があるので、ちょいと面倒です。
まず、2.および3.から任意の\(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\subset V\)に対して\(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W\)で、かつ任意の\(c\in\mathbb{R}\)に対して\(c\boldsymbol{a}\in W\)です。
故に、線型空間の公理の1.~8.を確かめる事ができます。
\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in W\subset V\)、\(c,d\in \mathbb{R}\)に対して
- \((\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})+\boldsymbol{z}=\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})\)か?
そもそも、\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in W\subset V\)ですので、\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in V\)です。
ここで、\(V\)は線型空間ですので、\((\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})+\boldsymbol{z}=\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})\)が成り立っています。 - \(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}\)か?
これも同じです。
そもそも、\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in W\subset V\)ですので、\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V\)です。
ここで、\(V\)は線型空間ですので、\(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}\)が成り立っています。 - 零ベクトルが存在するか?
これもほぼ同じです。
3.により、任意の\(\boldsymbol{a}\in W\)と任意の\(c\in\mathbb{R}\)に対して、\(c\boldsymbol{a}\in W\)です。
\(c\in\mathbb{R}\)は任意ですので、\(c\)を\(0\)としてもOKです。
従って、\(c\boldsymbol{a}=0\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}\in W\)です。
故に、零ベクトルが\(W\)に存在します。 - 逆ベクトルが存在するか?
これもさっきとほぼ同じです。
3.により、任意の\(\boldsymbol{a}\in W\)と任意の\(c\in\mathbb{R}\)に対して、\(c\boldsymbol{a}\in W\)です。
\(c\in\mathbb{R}\)は任意ですので、\(c\)を\(-1\)としてもOKです。
従って、\(c\boldsymbol{a}=-1\cdot\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\in W\)です。
当然ながら\(\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{0}\in W\)です。
故に、逆ベクトルが\(W\)に存在します。 - 任意の\(c,d\in \mathbb{R}\)、任意の\(\boldsymbol{x}\in W\)に対して\((c+d)\boldsymbol{x}=c\boldsymbol{x}+d\boldsymbol{x}\)か?
任意の\(\boldsymbol{x}\)と任意の\(c,d\in\mathbb{R}\)に対して、そもそも\(W\subset V\)なので、\(\boldsymbol{x}\in V\)です。
\(V\)は線型空間なので、\((c+d)\boldsymbol{x}=c\boldsymbol{x}+d\boldsymbol{x}\)が成り立っています。 - 任意の\(c\in\mathbb{R}\)、任意の\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in W\)に対して\(c(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=c\boldsymbol{x}+c\boldsymbol{y}\)か?
これも同じです。
そもそも\(W\subset V\)なので、任意の\(c\in\mathbb{R}\)、任意の\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in W\)に対して、\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V\)です。
\(V\)は線型空間なので、\(c(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=c\boldsymbol{x}+c\boldsymbol{y}\)が成り立っています。 - 任意の\(c,d\in\mathbb{R}\)、任意の\(\boldsymbol{x}\in W\)に対して\((cd)\boldsymbol{x}=c(d\boldsymbol{x})\)か?
同じです。
そもそも\(W\subset V\)なので、任意の\(c,d\in\mathbb{R}\)、任意の\(\boldsymbol{x}\in W\)に対して、\((cd)\boldsymbol{x}=c(d\boldsymbol{x})\)です。 - \(1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}\)か?
3.から任意の\(\boldsymbol{a}\in W\)と任意の\(c\in\mathbb{R}\)に対して、\(c\boldsymbol{a}\in W\subset V\)です。
\(c\)は任意ですので、\(c=1\)としてもOKです。
故に、\(V\)について\(1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}\)が成り立っているので、\(W\)でも成り立っています。
定理5.の証明終わり
実は、この必要十分条件をさらに言い換えることができます。
定理6.(部分空間の必要十分条件その2)
線型空間\(V\)の部分集合\(W\)が部分空間であるための必要十分条件は次の3条件が成り立つことである。- \(W\neq \emptyset\quad\)(\(\emptyset\)は空集合)
- 任意の\(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\)および任意の\(c,d\in\mathbb{R}\)に対して、\(c\boldsymbol{a}+d\boldsymbol{b}\in W\)
要するに、定理5.の2.と3.が定理6.の2.と同値だ、と言っているわけです。
すなわち、
\begin{eqnarray}
&&\left(\forall \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\Rightarrow \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W\right)\land \left( \forall \boldsymbol{a}\in W,\ \forall c\in \mathbb{R}\Rightarrow c\boldsymbol{a}\in W\right)\\
&\Leftrightarrow&
(\forall \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W)\ (\forall c,d\in\mathbb{R})\ c\boldsymbol{a}+d\boldsymbol{b}\in W
\end{eqnarray}
というわけです。
とどのつまり、\(W\)の任意の要素の任意の線型結合がまた\(W\)の要素だ、と言っているわけです。
これを証明しましょう。
定理7.
\(W\subset V\)を線型空間\(V\)の部分空間だとする。 このとき、以下が成り立つ。 \begin{eqnarray} &&\left(\forall \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\Rightarrow \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W\right)\land \left( \forall \boldsymbol{a}\in W,\ \forall c\in \mathbb{R}\Rightarrow c\boldsymbol{a}\in W\right)\\ &\Leftrightarrow& (\forall \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W)\ (\forall c,d\in\mathbb{R})\ c\boldsymbol{a}+d\boldsymbol{b}\in W \end{eqnarray}定理7.の証明
①\(\Rightarrow\)の証明
$$
\left(\forall \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\Rightarrow \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W\right)\land \left( \forall \boldsymbol{a}\in W,\ \forall c\in \mathbb{R}\Rightarrow c\boldsymbol{a}\in W\right)
$$
が真だとします。
このとき、
任意の\(\boldsymbol{a}\in W\)と任意の\(c\in\mathbb{R}\)に対して\(c\boldsymbol{a}\in W\)なので、\(\boldsymbol{a}\)とは別の\(\boldsymbol{b}\in W\)、\(c\)とは別の\(d\in\mathbb{R}\)に対しても\(d\boldsymbol{b}\in W\)です。
また、\(\forall \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\Rightarrow \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W\)であることから\(c\boldsymbol{a}+d\boldsymbol{b}\in W\)です。
②\(\Leftarrow\)の証明
$$
(\forall \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W)\ (\forall c,d\in\mathbb{R})\ c\boldsymbol{a}+d\boldsymbol{b}\in W
$$
だとします。
このとき、\(c,d\in\mathbb{R}\)は任意なので\(c=d=1\)とすることで
$$\left(\forall \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\Rightarrow \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W\right)$$
が示されます。
また、\(c=0\)とすることで
$$\left( \forall \boldsymbol{a}\in W,\ \forall c\in \mathbb{R}\Rightarrow c\boldsymbol{a}\in W\right)$$
です。
従って、同値です。
定理7.の証明終わり
とどのつまり、「\(W\subset V\)が線型空間\(V\)の部分空間であることを示しなさい。」と言われたらば、定理6.の条件を満たすかどうかを調べればOKということになります。
ちなみに、最も単純な部分空間の例は、線型空間\(V\)の零ベクトル\(\boldsymbol{0}\)だけからなる集合\(\{\boldsymbol{0}\}\)です。
基本的な部分空間の作り方
次の定理は線型空間\(V\)が与えられたときに\(V\)の部分空間を作る基本的は方法です。
定理8.
\(V\)を\(\mathbb{R}\)上の線型空間、\(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r\)を\(V\)のベクトルだとする。\(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r\)の線型結合全体の集合、すなわち $$ W=\left\{x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\dots+x_r\boldsymbol{a}_r \middle| x_i\in\mathbb{R},\ i=1,2,\dots,r\right\} $$ は\(V\)の部分空間である。定理8.の証明
定理6.を使って証明します。
$$
W=\left\{x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\dots+x_r\boldsymbol{a}_r \middle| x_i\in\mathbb{R},\ i=1,2,\dots,r\right\}
$$
とします。
①\(W\neq \emptyset\)の証明
簡単です。
\(W\)の要素は\(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r\)と\(x_1,\dots,x_r\in\mathbb{R}\)を使って
$$
x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\dots+x_r\boldsymbol{a}_r
$$
と書かれています。
このとき\(x_i\in\mathbb{R}\ (i=1,\dots,r)\)は任意ですので、\(x_1=1\)として、それ以外を\(0\)とすれば、\(\boldsymbol{a}_1\in W\)となるので、\(W\neq \emptyset\)です。
②任意の\(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\)および任意の\(c,d\in\mathbb{R}\)に対して、\(c\boldsymbol{a}+d\boldsymbol{b}\in W\)の証明
任意の\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in W\)に対して、
\begin{eqnarray} \boldsymbol{x}&=&x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\dots+x_r\boldsymbol{a}_r,\\
\boldsymbol{y}&=&y_1\boldsymbol{a}_1+y_2\boldsymbol{a}_2+\dots+y_r\boldsymbol{a}_r\\
\end{eqnarray}
と書かれます。
このとき、任意の\(c,d\in\mathbb{R}\)に対して\(c\boldsymbol{x}+d\boldsymbol{y}\in W\)であればOKです。
ここで、\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in W\subset V\)で、\(V\)は線型空間ですので、この\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\)に対して\(V\)の線型空間の公理を使うことができます。
従って、
\begin{eqnarray}
c\boldsymbol{x}+d\boldsymbol{y}=
(cx_1+dy_1)\boldsymbol{a}_1+(cx_2+dy_2)\boldsymbol{a}_2+\dots+(cx_r+dy_r)\boldsymbol{a}_r
\end{eqnarray}
です。
これを見ると、
$$
(cx_1+dy_1)\boldsymbol{a}_1+(cx_2+dy_2)\boldsymbol{a}_2+\dots+(cx_r+dy_r)\boldsymbol{a}_r
$$
もまた\(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r\)の線型結合ですので、
$$
(cx_1+dy_1)\boldsymbol{a}_1+(cx_2+dy_2)\boldsymbol{a}_2+\dots+(cx_r+dy_r)\boldsymbol{a}_r\in W
$$
となるから、\(c\boldsymbol{x}+d\boldsymbol{y}\in W\)です。
定理8.の証明終わり
この定理8.によって保証されている部分空間\(W\)を\(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r\)によって生成される、または張られる部分空間といって、\(S[\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r]\)で表します。
また、\(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r\)を\(W\)の生成系といいます。
部分空間の例
実は、連立一次方程式に関連した集合は線型空間\(\mathbb{R}^n\)の部分空間です。
定理9.
\(m,n\in\mathbb{N}\)、\(A\)を\((m,n)\)型の行列とする。このとき $$ W=\left\{\boldsymbol{x}\in \mathbb{R}^n\middle|A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\right\} $$ は\(\mathbb{R}^n\)の部分空間である。証明は簡単です。
今回は定理5.を使います。
定理9.の証明
\(m,n\in\mathbb{N}\)、\(A\)を\((m,n)\)型の行列とします。
①\(W\neq \emptyset\)の証明
\(A\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}\)ですので、\(\boldsymbol{0}\in W\)だから\(W\neq \emptyset\)です。
②任意の\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in W\)に対して\(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\in W\)の証明
次の事実を使います。
定理10.(分配則)
\(m,n,r\in\mathbb{N}\)、\(k,h\in\mathbb{C}\)とする。このとき、3つの行列\(C\)に対して、以下が成り立つ。- \(A\)が\((m,n)\)型、\(B\)及び\(C\)が\((n,r)\)型のとき、\(A(B+C)=AB+AC\)
- \(A\)と\(B\)が\((m,n)\)型、\(C\)が\((n,r)\)型のとき、\((A+B)C=AC+BC\)
- \(A\)および\(B\)が共に\((m,n)\)型のとき、\(k(A+B)=kA+kB\)
- \(A\)および\(B\)が共に\((m,n)\)型のとき、\((k+h)A=kA+hA\)
定理10.の証明は【線型代数学の基礎シリーズ】行列編 その2を御覧ください。
定理10.から任意の\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in W\)に対して
$$
A(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=A\boldsymbol{x}+A\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}
$$
です。
従って、\(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\in W\)です。
③任意の\(\boldsymbol{x}\in W\)、任意の\(c\in\mathbb{R}\)に対して\(c\boldsymbol{x}\in W\)の証明
次の事実の2.を使います。
定理11.(スカラー倍の性質)
\(k,h\in\mathbb{C}\)、\(m,n,r\in\mathbb{N}\)とする。\((m,n)\)型行列\(A\)と\((n,r)\)型行列\(B\)と\(k,h\)に対して次が成り立つ。- \((kh)A=k(hA)\)
- \(k(AB)=(kA)B=A(kB)\)
- \(0A=O_{mn}\quad\)
- \(1A=A\)
定理11.の証明は【線型代数学の基礎シリーズ】行列編 その2を御覧ください。
任意の\(\boldsymbol{x}\in W\)と任意の\(c\in\mathbb{N}\)に対して
$$
A(c\boldsymbol{x})=cA\boldsymbol{x}=c\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}
$$
となるので、\(c\boldsymbol{x}\in W\)です。
従って、定理5.から\(W\)は\(\mathbb{R}^n\)の部分空間です。
定理9.の証明終わり
結
今回は、線型空間を導入して、線型結合と部分空間について解説しました。
線型空間は数学を語る上で非常に重要です。
というもの、あらゆる分野で線型空間を前提にして話をすすめることが多いからです。
また、ベクトルとは何か、というと線型空間の要素のことなのでした。
故に、関数だってベクトルになりうるわけです。
あくまで線型空間の要素をベクトルと呼ぶのであって、それが数の組とは限りません。
次回は線型従属(一次従属)、線型独立(一次独立)について解説します。
これらは線型空間の風貌を知るために誠に重要な概念です。
乞うご期待!質問、コメントなどお待ちしております!



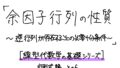
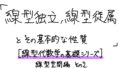
コメントをする